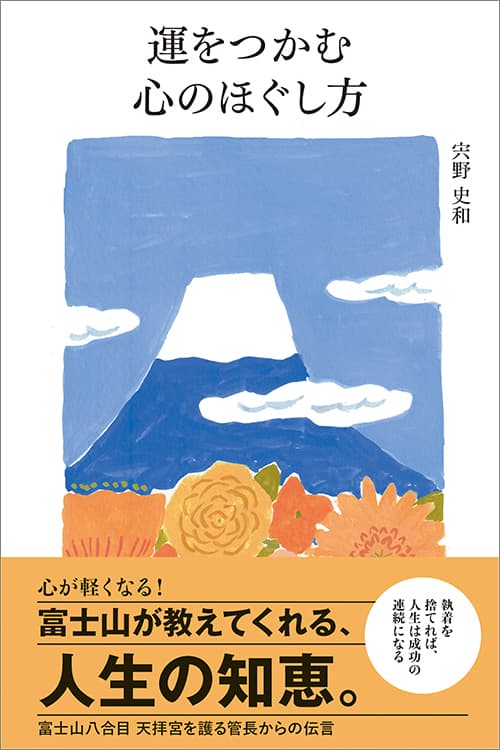日本宗教連盟・理事「世帯年収1000万円の家庭の中は空っぽだ」なぜ宗教家が”借金するなら金融機関から”とアドバイスするのか

日本宗教連盟・理事であり、神道扶桑教・管長の宍野史和氏、お金と日本人について語る。「何か特別な理由があって東京にいる人は、たとえお金がなくて生活に困っていても、本当のところは困っていないんです」ーー。
※本稿は『運をつかむ心のほぐし方』(プレジデント社)から抜粋・再構成しています
目次
借金は雪だるま式に際限なく増える
今も昔も、身を持ち崩す多くは、酒かギャンブルが引き金になっているのではないでしょうか。年がら年中、酒を飲み続けているような人も実際にいますが、やはり人間の体なので限界というものがあります。
しかし、この「限界」という考え方が通用しないのがギャンブルの怖さです。借金地獄に自分から陥りたいという人などいるわけがありません。そこまで落ちてしまう前に止めればいいのにと思いますが、それができないものなのです。 私は博打をまったくしないので詳しいことはわかりませんが、はじめはみなさん手元にある自分のお金で博打を打つわけです。たとえば、100万円あった全財産をすべて博打でスッてしまった人がいたとしましょう。
今度はその100万円を取り戻すために金融機関で100万円の借金をする。つまりこの時点でマイナス200万円になっています。そして、200万円を取り戻すために200万円を借り、400万円を取り戻すために400万円を借り……と、借金は雪だるま式に際限なく増えていってしまうのです。
四方八方の知人・友人にお金を借りまくっているパターン
けれど、金融機関でお金を借りること自体は悪ではありません。それは、そういうシステムだから。ギャンブルが原因でなくても、お金がなければ借りないと仕方がないわけです。
それよりも少し質が悪い借金が、四方八方の知人・友人にお金を借りまくっているパターンです。金融機関からお金を借りているのなら、極論を言えば自己破産をして自分を犠牲にすればいい。しかし、知人・友人にお金を借りている場合は、ただただ周りの人に迷惑をかけてしまうだけなのです。
競馬でも何でもそうですが、馬は何にも悪くない。ボートも悪くない。当然、お金を貸してくれた知人・友人も悪くない。これはもう完全に自分だけが悪い。
それは本人もわかっていることなので、ある意味、反省しながらお金を借りているはずなんですね。
中途半端に事業に手を出して、見事に失敗してしまった経営者
しかし、ときどき多額の借金をしているにもかかわらず、まったく反省すらしていない人がいる。それは誰かと言うと、中途半端に事業に手を出して、見事に失敗してしまった経営者です。
長年勤めた会社を祝福されながら引退して、ガッポリ退職金が出ました。時間があるぶん今度は自分のやりたいことをやろうと会社を興して夢を叶えたい。それは、自分が稼いできたお金なのですから、何をしようとけっこうです。
ただ、いけないのは明確な事業計画もなしに多額のお金をかけてしまう人。
「今からあのギャンブルに一千万円賭けたいので貸してください」と銀行にお願いしても貸してくれるわけがありません。でも、「事業資金として一千万円が必要です」とお願いした場合には、事情がまったく変わってくる。そして、その場合、案外貸してくれる。
失敗したときにはギャンブルの予想を外したときよりもはるかに大きな損失
ギャンブルに注ぎ込むために金融機関で調達したお金には、後ろめたさという要素が含まれています。いや、もはや後ろめたさしかないでしょう。ですが、夢を実現するための事業資金には、借りたお金とはいえ後ろめたさなど微塵も含まれていないのです。
例えば、飲み屋さんで散財したとて、そこには働いている従業員さんもいれば、納入業者の酒屋さんやおしぼり屋さんもいる。「風が吹けば桶屋が儲かる」という話のように、その散財がまったく人の役に立っていないかというと、そんなわけがない。
むしろ、経済のことを考えるとお金をたんまり持っている人はどうぞ気兼ねなく散財してくださいという話になる。
事業が成功すれば何も言うことはありませんが、失敗したときにはギャンブルの予想を外したときよりもはるかに大きな損失となります。酒やギャンブルに狂うことよりも中途半端な事業欲こそが何倍も罪深く、究極の道楽であるということを忘れてはいけません。
先進国日本で深刻化する貧困問題
日本は先進国でありながら、貧困問題が深刻化しています。
「相対的貧困」と呼ばれる、中間的な所得の半分(2018年時点で127万円)に満たない世帯は、45.7%にも及んでいます。
貧困は孤独と密接な関係にあります。内閣官房孤独・孤立対策担当室による
「人々のつながりに関する基礎調査(令和3年=21年)」を見てみましょう。
まず、年齢別に見た孤独感を示したデータによると、「20~29歳」「30~39歳」がもっとも孤独を感じている人の割合が多く、以降は年齢が増すごとに孤独感は軽減されていきます。
さらに、世帯年収別に見た孤独感を示したデータによると、「100万円未満」の世帯がもっとも孤独を感じていて、こちらも世帯年収が増すごとに孤独感は綺麗に軽減されていきます。
社会全体の「孤独」はどんどん増えていくことに
つまり、働いてはいるけれど貧困に喘いでいる層がもっとも孤独を感じていることになる。
働いているにもかかわらず、収入が生活保護の水準(またはそれ以下)である「ワーキングプア」と呼ばれる層は、厚生労働省によると全労働者の約1割に達しています。
これは単なる偶然ではなく社会現象だと思っていて、国家が対策をしなければならない問題だとも思っています。
というのは、このままの状況が続けば、今孤独に苛まれている20代と30代はこの先もずっと孤独を抱えることになるからです。
歳を取れば孤独を克服できるわけではありません。むしろ、これから20代になる人たちも貧困に喘ぐことになるのであれば、社会全体の「孤独」はどんどん増えていくことになるでしょう。
国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査」によれば、給与所得を得ている人のうち年収が1000万円以上ある人の割合は全体のわずか5%だといいます。一方、厚生労働省の「令和3年 国民生活基礎調査の概況」によると、世帯年収で1000万円以上は12%に過ぎません。
年収1000万円の家庭の中は空っぽ
夫婦ふたりで1000万円稼いでいればちょっといい生活ができているかもしれませんが、家の中は空っぽです。夫婦が共働きをしている家庭では、孤独を抱えるのは残された子どもになってしまうのです。
日本を取り巻く貧困問題が改善されれば、社会を包んでいる孤独感も減っていくかもしれませんが、あいにく今の政治にはあまり期待ができません。そこで思うのは、「執着」を捨てることで孤独感を減らすという考えが必要ではないかということです。
たとえば東京に住もうとなれば、どんなに狭い部屋でも家賃だけで平気で10万円は財布から毎月出ていってしまいます。
その「東京に対する執着」を捨てたとするならば、年収が300万円に満たなくても地方であれば十分に生活できるかもしれません。