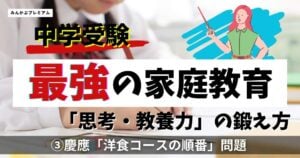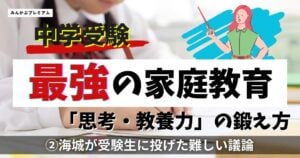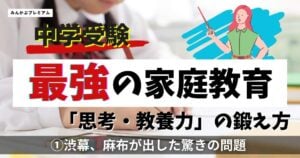絶対に覚えて!中学受験本番で超役立つ3つの計算テク…偏差値40の学校でも平然と出題される「点数を上げる効率的トレーニング法」
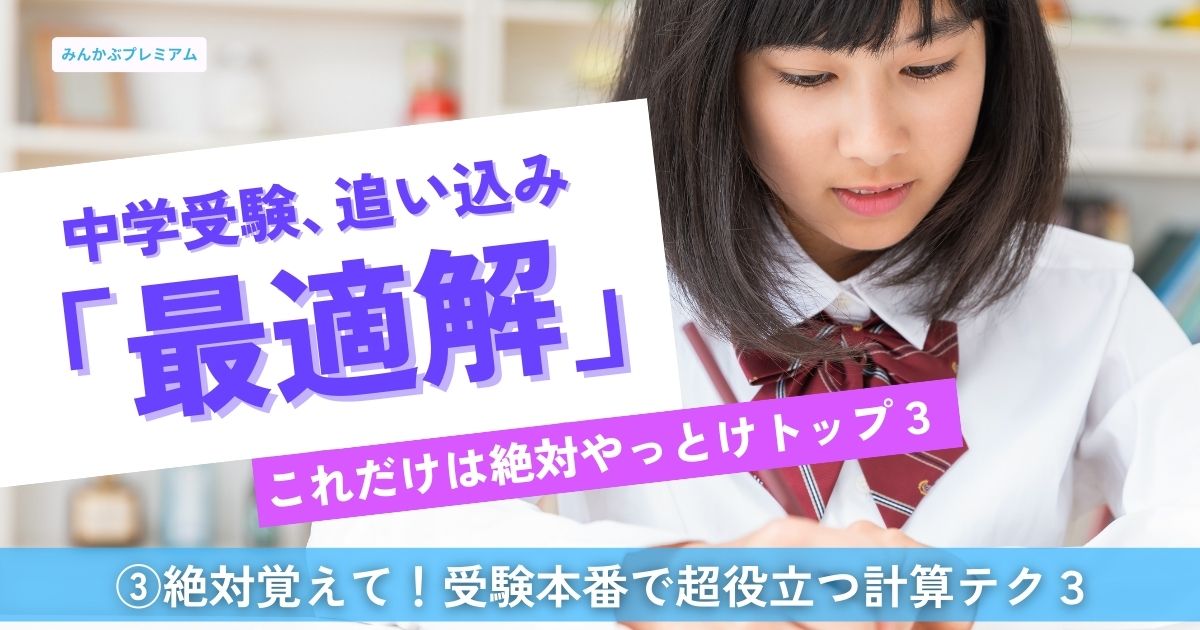
例題1:59×10.8-236×0.7+4×29.5=
この問題、あなただったらどう解くだろうか?
最近の中学受験では、こういった複雑な計算問題がどこの学校でも当たり前のように出題される。
「ちょっとしたテクニックを使えば、式をまとめて簡単に解く事ができます」とジーニアスの松本氏。※正解と素早く解くテクニックは記事中盤で紹介します。
テクニックを使う計算問題は、以前は主に難関校で出題される傾向にあったが、最近は偏差値40程度の学校でも出題されるようになってきたという。
「中堅校でも出題が目立つようになったため、計算テクニックについては4、5年生からトレーニングした方がいいでしょう。文章題や図形の計算でも活用でき、計算速度のアップやミスの減少にも繋がります」
入試本番の計算にも役立つテクニックについて、3つ紹介する。
目次
式の頭から解いてはいけない
例題1のような問題は、式の頭から解いてはいけません。計算の順序を入れ替えたり、同じ数をまとめたりできないか、手を動かす前に考えるのです。
例題1:59×10.8-236×0.7+4×29.5=
まず、236は59の4倍だとすぐに気づきたいところです。次に29.5は59の半分です。
そうすると、この式は59でまとめることができますね。
例題1:59×10.8-59×4×0.7+2×59=
59×10.8-59×2.8+2×59=
と式を変形することができます。さらにまとめれば、
59×(10.8-2.8+2)=
最初に比べて格段にシンプルになりましたね。
59.8×10=598 となります。
大人は気づけても子どもは気づけない数字の入れ替え
次は下記の問題です。先ほどより解きやすいと思います。
例題2:3.14×12+3.14×18=
図形問題では3.14のかけ算がたくさん出てきます。毎回かけ算をするのは、時間もかかるしミスの元です。
この場合は、12と18をまとめて3.14×30にしてしまいましょう。
3.14×(12+18)= 94.2となります。
大人からすると比較的簡単ですが、小学生はなかなか工夫してくれません。慣れておかないと小6になっても、不器用に地道に解き続ける子が多いですね。