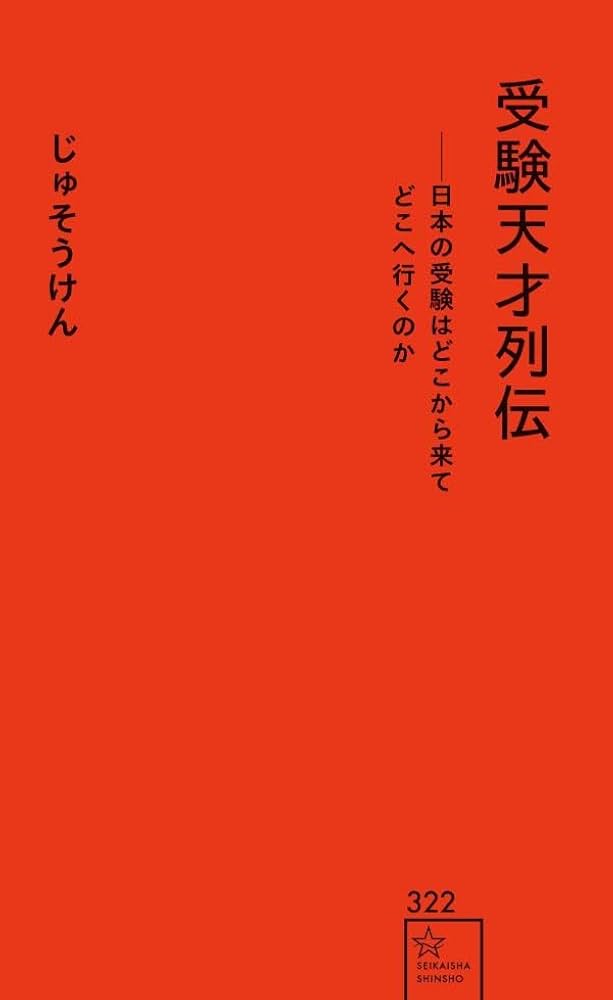「国Ⅰ成績より模試成績で盛り上がる」受験教者集団“東大官僚”あるある…成功者より「勉強できる奴」が偉い

新進気鋭の学歴研究家・じゅそうけん氏。そんなじゅそうけん氏が、東京大学卒・元経済産業省官僚で制度アナリストの宇佐美典也氏、現役東大生で『ドラゴン桜』の監修も務める西岡壱誠氏と、東大で出会った天才たちの実態について語り合う。全4回中の4回目。
※本記事はじゅそうけん著「受験天才列伝―—日本の受験はどこから来てどこへ行くのか」(星海社新書)から抜粋、再構成しています。
第1回:なぜ?40年東大合格者NO.1の開成を蹴って「都立日比谷」に進む生徒が増えている…中学受験激化による地殻変動
第2回:私大の5割強が定員割れでも日本社会に根付く「学歴至上主義」…もはや「4大卒」はブランドでもなんでもない
第3回:「近頃は法学部でなくても東大って言うんですか」知られざる神童政治家の“学歴厨”列伝…東大に3度落ちた岸田、勉強せず東大合格の鳩山邦夫
目次
東大生が「勝てない」と感じた東大生
西岡 宇佐美さんは、東大に入って「マジでこいつには勝てねえな」「こいつマジどうなってんの」みたいな「天才」と出会いましたか?
宇佐美 何人かいましたね。一人記憶に残っているのは、いまアメリカの大学で統計の教授をやっておられる方です。文科一類から東大に入られたのですが、めちゃくちゃに数学ができた。学部在籍中にして、すでに博士課程の人と同じくらいのレベルに達していたらしい。「金融とかやったらすごく稼げるんじゃない?」と尋ねたら、「そういうことじゃないんだよな、興味ないんだ」みたいな反応だったのが記憶に残っています。
あと、私たちの世代で有名な天才といえば、やっぱり長尾健太郎さんですよ。
じゅそうけん 数学者であり、平成を代表する受験天才でもある方です。
宇佐美 長尾健太郎さんは、小学校の時から凄かった。僕の一学年下だったのですが、小5の時に小6の模試で一番を取っていたような感じでしたよ。もう初めの段階から格が違いました。そして私が一浪したので長尾さんと同学年になり、大学でも何回かお話ししたのですが、ごく普通の青年だった。本当に優秀な「できるやつ」というのは振る舞いが自然です。
意外と“普通”な天才たち
じゅそうけん 確かに「天才=奇人変人」のイメージありますけど、意外と話してみると普通なものですか。
宇佐美 そう、ほんとうにできるひとは、奇人変人ぶりを自己演出する必要がないんだろう。だけど、ゼミの発表とかになると、ひとりだけ全然次元が違うぞ、となるのが天才たち。レベルが高すぎて、もう話している内容がわからない。西岡さんの周りにもいましたか?
西岡 色々な方がいましたが、天才タイプのひとは「自分の興味があること」への熱量がすごいですよね。何の評価にもならないような課題でも、分厚いレポート出してくるような感じ。
宇佐美 そう、特に「文科三類のできるやつ」には面白い人が多かった。普段は学校にもあんまり来ないようなほぼ世捨て人のような生活をしてるのに、たとえば「映画論」とかになった瞬間に凄まじい映画評を書いてくるみたいなね。もうほんとに好きで好きでたまんないんだろうなというのが伝わってくる。
あとは、自分の社会での居づらさを一つの大著論文に仕立てあげてくる、みたいなタイプもいる。凡人は「自分がこじらせてるだけだ」と諦めてしまうものですけど、それを社会問題にまで仕立てあげる強引なまでの力がある。
西岡 謎の馬力があるタイプですよね。
宇佐美 「俺が居づらいのは社会構造に問題があるからだ」みたいなことを、一人で家で論文として書いちゃうんだからすごいですよ。文科二類であれば、ゲーム理論とか駆使して「結局は愛なんだ」「金は結局愛がなければまわらないってことを証明したいんだ」といって博士課程にいくぞと意気込んでるやつもいたな!
じゅそうけん ……すごいですね。
成功したやつよりも「勉強できるやつ」が偉い
宇佐美 そういう天才たちは「自分のこだわりをこだわり抜いた結果、今ここにいますよ」っていうオーラを放っているんです。そして周囲も、社会的成功や金銭的満足よりも「勉強できるやつ」が本当は偉いんだよなと認めている。これは東大カルチャーの良い部分かもしれないですね。
西岡 そういう雰囲気の中に身を置いていると、自分はそれとは違う人間だなというか、俺、東大に居ていいのかなみたいなことで思い悩んだことはありますね。東大生が誰しも多少なりとも考えることかもしれませんが。
宇佐美 私もそういう雰囲気と馴染まないタイプでした。学生時代の一時期は、風呂なしアパートに住んで、東大構内のシャワーを使っていたんです。そこに集まってくるような学生と仲が良かった。東大では珍しい「盗みが発生する空間」で、自分も一回、バイト代が入った日に盗まれて、うわーと思った。
自分は「受験天才」的なあり方に距離をおきたかったから、そういう空間で社会経験を拡げることが嫌ではなかった。若い頃の自分は特に、他の学生とすこし違うことをして、自己演出的に「おれはすげえぞ」と見せたかったのかもしれないですね。それくらい、東大に入れば誰しも「こいつには勝てねえな」という経験をするんじゃないでしょうか。
国Ⅰの順位より模試の順位
じゅそうけん さらに宇佐美さんにぜひお伺いしたかったのは官僚の世界における「受験天才」のリアルについてです。大蔵省(現・財務省)出身の片山さつきさんが、鳩山邦夫さんに対して「私は全国模試1位でした」とマウントを取ったという学歴厨エピソードは有名ですよね。ほかにも、僕たちのまだ知らない「受験天才エピソード」や「学歴厨エピソード」が、霞が関に眠っているのではないでしょうか。
宇佐美 まさに「模試の成績」は語り継がれますね。「模試1位同士でナンバーワン・ツー争いをずっとやってる」みたいなこともありました。自分は予備校に行っていなかったからその手の情報に疎くて、大学入学時にも入省時にも事情に詳しくなかったのですが、「予備校勢」みたいな連中が「あれが模試上位の〇〇か」みたいなことを言い合っているのを目にしてきました。
じゅそうけん 「模試の成績」は、学歴好きが最もテンションが上がる話題の一つです。昭和の頃からずっと変わらない組織文化といわれます。
宇佐美 ヤンキーみたいなんですよ。「あれが関西の雄!」みたいに一目置き合っている。もちろん模試の成績だけじゃなく「学歴」が話題になることもありますよ。
じゅそうけん 国家公務員採用総合職試験(旧Ⅰ種)の試験の順位よりも「模試」の点数のほうが幅を利かせるんでしょうか。
宇佐美 はい、総合職試験よりも、明らかに「予備校模試の1番・2番」のほうが格式が高いんです。もちろんⅠ種の試験で1番とか2番みたいな飛び抜けた成績の人は目立つし、財務省は採用試験の点数にもある程度こだわるかもしれませんが、それ以外の省庁はそこまでこだわらない。
人事担当者にとっても、採用試験での点数は「横並びになったときにどちらを優先するか」くらいの限定された意味しか持たないですから、多くの人は「受かっているわけだから、とりあえずいいよね」くらいの感覚だと思います。それに比べれば、予備校模試の成績優秀者はずっと語り継がれるし、格式が高い。
じゅそうけん そこまで格式が高いとは、驚きです。模試の順位表は、上位者だけの名前が開示されるから、特異な文化を生み出しやすい仕組みでしたよね。