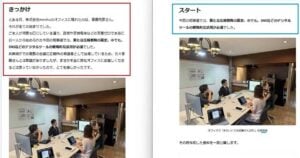鈴木エイト「兵庫県知事選後、デマ拡散した立花氏を評価する現状分析のできない人々」…SNSが「オールドメディアに勝った」は本当か

2025年、日本の政治は新たな局面を迎えようとしている。少子高齢化や経済格差、国際情勢の変化など、多くの課題が山積する中で、国民の一票がどのような未来を切り拓くのか。その行方に注目が集まる選挙イヤーを前に、ジャーナリスト・作家の鈴木エイト氏に話を聞いた。これまで数々の選挙の裏側を明かしてきた鈴木氏が、2025年の選挙にどのような予測を立て、どのような論点を見据えているのか。みんかぶプレミアム特集「業界大予測」第3回。
目次
ネットを使った選挙運動に「規制」が入る可能性
2025年は参院選と都議選など、大きな選挙が控えている。
昨年は「公職選挙法」「選挙と報道」という観点から、様々な問題点が顕在化した。東京15区補選におけるつばさの党による選挙妨害問題、都知事選での選挙掲示板ポスター問題、兵庫県知事選ではSNS等でのデマ情報が拡散し選挙結果に影響を与えた。公平性と公正性が担保されるべき選挙の場が荒らされている状況だ。
2013年に公職選挙法の一部が改正され、ネットを使った選挙運動が解禁されて以降、どうすれば公選法違反に問われないかというラインで選挙運動の手法が模索されてきたともいえる。
公選法改正の議論もあるなか、実際には現行法において収益アカウントへの規制、具体的にはプラットフォーマー側に対する規制がなされていくと見ている。「公選法が現状に追い付いていない」のではなく、公選法を現状に厳密に適用して公平性と公正性を保つべき局面であるからだ。本年は7月の参院選までに、悪質なデマなどに対し公職選挙法をどう適用していくかといったことが整理されていくだろう。
兵庫県知事選では悪質デマが横行…速やかなファクトチェックと適切な報道が行われるべき
そして何より、選挙報道には大きな変化が起こるはずだ。24年はSNSやYouTubeを介して不確かな情報が拡散し、選挙運動中に踏み込んだ報道を控えたことによる弊害が顕在化した。放送法を気にするあまり、選挙報道の量的公平を保つことだけに苦心してきた各メディアだが、実際には質的な公平を保つことで事足りるからだ。
現にBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会は、2017年2月に決定第25号「2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての意見」として選挙報道をめぐる報道の公平性についての意見書を公表している。選挙に関し放送法が定める「政治的に公平であること」との条文は「倫理規範」であり、「公平性」とは、当該選挙区の候補者に同じ時間を割く類の量的な公平ではなく、各報道局が自主的に基準を判断する質的な公平だとしている。公選法に関しても「表現の自由を濫用し、しかも、その結果、選挙の公正を害することにならない限りは、選挙に関する報道と評論を自由にできる」としており、各メディアは適切な選挙報道ができるはずである。
兵庫県知事選では民意を歪めるような悪質なデマが横行する状況があり、一部の切り取り映像によって選挙動画で収益を上げる動きが爆発的にデマを拡散させた。もちろん表現の自由は担保されなくてはならないが、悪質なデマをさせてよい理由にはならない。告示後、公示後であっても速やかなファクトチェックと適切な報道によって、そのようなデマの拡散を封じることが求められている。