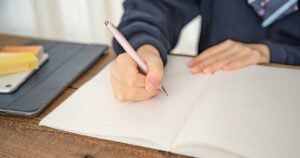中学受験「塾の合格実績を真に受けるな」…塾代表が暴露する「正しい見方」説明会では絶対に教えない「本当のところ」
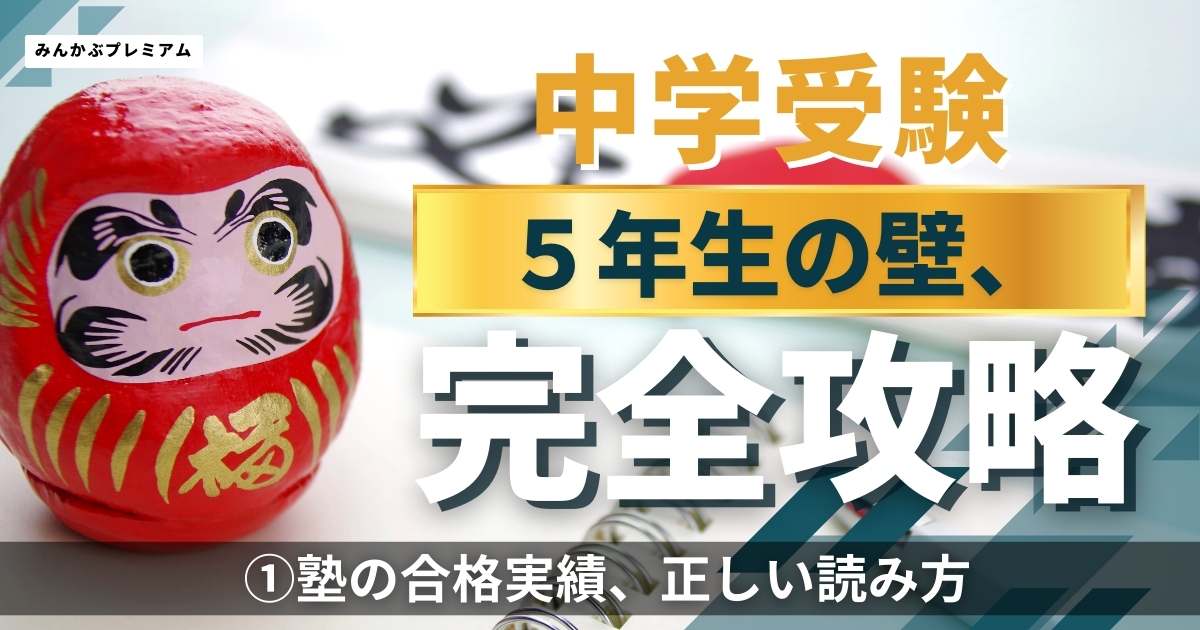
中学受験は、子どもだけの戦いではない。親の関わり方次第で、子どもの学びの質も、受験の結果も大きく変わる。それに加えて大きな役割を果たすのが、塾の役割だ。
塾の指導力、サポート体制、先生との相性などによって、子供の学力の伸びは大きく変わってくる。独学で乗り切れる高校受験、大学受験と異なり、塾通いが必須である中学受験において、塾選びは最初で最大の選択なのだ。
今回は個別指導塾Growy代表で、中学受験塾選びのプロフェッショナルであるユウシン氏に「塾選びのポイント」「塾との相性の見極め方」「伸び悩んだ際の対処法」を伺った。短期集中連載全2回の第1回ーー。
目次
説明会で教えてくれない受験塾の本当のところ
中学受験塾と聞いてまず想起するのが、下記のような大手塾かと思います。
関東:サピックス、早稲田アカデミー、日能研、四谷大塚、(希学園)
関西:浜学園、希学園、馬渕教室、能開センター、日能研関西
これらの塾は、首都圏・関西圏の主だった駅の前に教室を構え、数千人〜数万人規模の生徒が学んでいます。
一方で生徒数 数十〜数百人規模の中小塾も存在します。少人数で面倒見の良い塾、特定のエリアの学校に高い合格実績を上げている塾、大手塾で伸び悩んだ子を短期間で逆転に導く塾など、際立った特徴を持つ塾が多いのが特徴です。
多くのご家庭が2〜3箇所の見学で決めているのが実情かと思います。ただ、比較してみないと見えづらい、プロの視点から親御さんから知っておいてほしい特徴があります。
各塾の特徴はみんかぶの過去記事にて紹介しているので、今回は選び方のポイントをさらに深くご説明します。
予習メインか復習メインか
中学受験塾の授業の進め方は大きく、予習型と復習型にわかれます。
四谷大塚など予習型の塾の場合、半年分の教材をご家庭に渡し、受験生は予習をしたうえで授業に臨むという形式をとっています。
一方、サピックス、日能研、浜学園などの場合、テキストの事前配布がなかったり、予習をしないようにという方針だったりします。予習をさせないのは、授業で新しい知識を得る喜びを感じてもらうためです。
新鮮な気持ちで新しい知識を得る喜び、楽しみがあるのは魅力的ですが、事前に内容を知っておいて授業でそれを定着させるというコツコツ型の学習の方が向いている子も多いです。
学習スタイルがかなり違うので、まずはこの点をしっかり理解しておいてください。
授業外のフォローの密度
塾によって拘束時間や指導の仕方が大きく異なります。例えば希学園の場合、授業後も10時頃まで生徒を教室に残るよう促し、そこで今日習った内容の定着や宿題の消化をさせます。