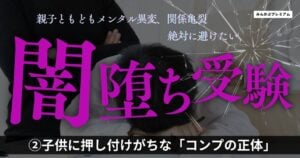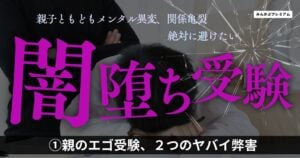学習塾代表「無理な中学受験は、子ども将来の年収を下げるリスク」塾よりサッカー教室に通わせるべき子ども特徴と毒親が読むべき本3選

ここ数年、高まり続ける中学受験の熱。
以前に比べ、中学受験に関する報道や話題を目にする機会が格段に増えた。受験人口の増加に伴い、受験生本人やその親に対するプレッシャーも高まっている。
「受験生とはいえ、まだ生まれて10年程度の小学生に過ぎません。過度なストレスに晒されれば、家庭環境の悪化、集中力の低下、モチベーションの低下という形で返ってきます」
そう語るのは学習塾伸学会代表の菊池洋匡さんだ。
「ストレスを過度に受けている子供は、途中で必ずサインを出しています。しかし、受験で失敗する家庭の多くは、それに気づかない。あるいは見て見ぬふりをします。『無理をさせても6年生2月の受験本番まで乗り切ればいい』というのは典型的な失敗パターンです」
世の中には受験の成功談に溢れているが、むしろ学ぶべきは失敗談だと菊池さん。
「成功談には典型的な“生存者バイアス”がかかっています。上手く行った人のエピソードに過ぎず、再現性がありません。失敗談を学べば、同じ轍を踏まないようにすることができるので、メリットが大きい。特にメンタルの面で言うと、受験生家庭の多くが同じような失敗をしています」
今回は「失敗しない」に焦点を当てて、子供の能力を最大化させる学習法を聞いた。短期集中連載全3回に第3回目ーー。
目次
どの家庭も必ず地雷を踏む
どんなにうまくいっている家庭でも、一度も子供を傷つけずに受験を完遂なんてことは滅多にありません。子どもが良い成績を取った時や、反対に望む結果が得られなかった時、さらには兄弟間に差が出た時など、ふとした瞬間に子どもの「地雷」を踏んでしまうことがあります。
もし「やってしまったな」と感じた時は、素直に謝ることが一番です。「ごめんね、お母さんも失敗しちゃった」「お父さんの言い方が良くなかったよね」と、誠心誠意伝えてください。子どもは親の一瞬の表情や態度に敏感に反応するもの。こういった時にごまかしは通用しません。
なぜ失言してしまったのか、その考えに至ったのか、感情の原因がどこにあるのかを考え、過去を振り返りながら自分を見つめ直すことが重要です。自分と向き合う作業は大切なのです。簡単ではないですが、長期的に取り組むことが本質的な解決策になると思います。
受験よりサッカー教室に通わせるべき
我が家は受験期の「負の遺産」を克服するまでに20年近くかかりました。受験期に同じような心の傷を負ってしまい、いまだにそれが解消されていない人も多いはずです。