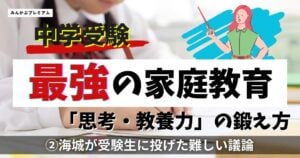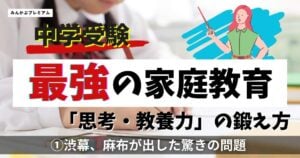桜蔭中、慶應中の入試ではなぜ「おせちの由来や洋食コースの順番」を問うのか…中学受験新時代、親ができる最初の対策
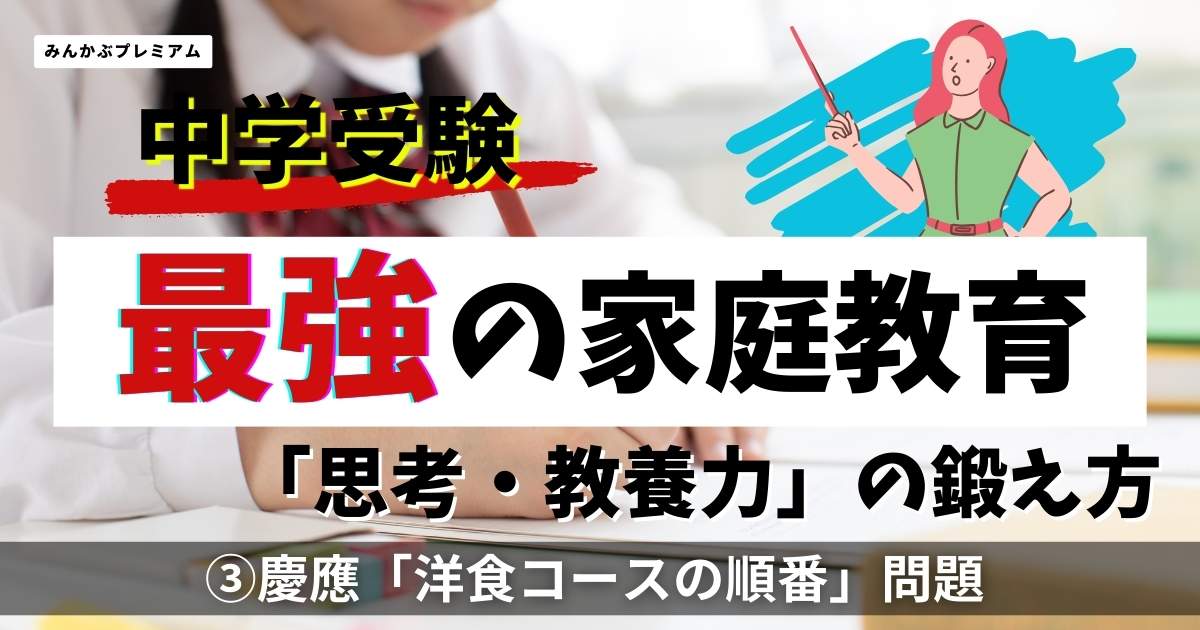
近年、中学受験はトップ校の出題傾向が変わり、知識・パターン問題偏重の入試から、深い思考力や高い教養力を含めた「知の総合力」を問う入試にシフトしつつある。
入試問題を長年研究している中学受験専門塾「 ジーニアス」の松本亘正代表は、トップ校入試の中で問われる能力が「質的」に変わってきたと断言する。
「聖光学院、筑駒、麻布、渋幕、女子学院といったトップ校では、塾のテキストの丸暗記だけでは解けない問題が数多く出題されるようになってきました」
変わるトップ校対策はどのように進めていけば良いのか。「ジーニアス」の松本氏に問題分析と解説を聞いた。全3回の第3回ーー。
目次
家庭での「なぜ」「どうして」が基礎力を鍛える
トップ校を中心に広まりつつある思考力・教養を求める入試問題。これらに対応するには、「家庭」の力が大事です。
まず、思考力についてですが、社会問題や日々のニュースに対して一緒に考えたり、親子で会話したりすることが大事です。人口減少、経済格差、物価高、選挙制度など最初はどのようなテーマからでも構いません。
子供と一緒に「なぜ、そう思うのか」「他の見方は考えられないか」といったことを会話することが、柔軟な思考を養います。
麻布中では以前、「明治時代になって、時計が社会的に広く普及した理由」を答える問題が出題されたことがあります。この問題の解答例は「工業化が進み、工場の稼働に合わせて働く人が増えた」「軍事的な作戦行動のため必要になった」というものです。
正解を知っているかどうかではなく、明治維新以降の時代背景や社会変化に思いを巡らせ、試行錯誤できるかどうかが問われている問題です。
家庭でも「なぜ」「どうして」を掘り下げることが、こうした問題を解く基礎力を鍛えることにつながります。正解に最短ルートで辿り着こうとするのではなく、思考過程を楽しむことを重視して親子での会話を楽しんでみてください。