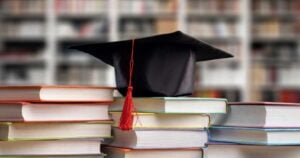中学受験「合否を分ける効率的な対策法」思考力型よりも処理能力…専門家が解説

中学受験上位層が目指すことの多い「早慶・GMARCH」といった有名大学の附属校。最近は、新しい附属校の偏差値も上昇傾向にある。
「同じ中学受験でも、進学校を目指すのか附属校を目指すのかによって、受験者層も学習スタイルもかなり異なります」。そう語るのは進学塾「VAMOS」代表の富永雄輔氏だ。
附属校の魅力は、大学合格実績を上げるために切磋琢磨する進学校とは異なり、それぞれが持つ「強み」を享受できる点だ。
外からは見えにくい大学附属校の魅力とは何なのか。OB・OGたちはなぜ母校に子どもを入れたがるのか。志望校選びで欠かせない重要ポイントを「中受のプロ」である富永氏が解説する。
目次
徹底した基礎固め、高得点勝負で勝ち抜く
偏差値が高止まりしている大学附属校ですが、効率的な対策方法を知っているかどうかで合否は大きく分かれます。まず、これらの学校では「御三家」や「上位進学校」のような思考力型の問題はあまり出題されません。
オーソドックスな処理能力を問う問題が、出題のほとんどを占めています。ひねった問題、複雑な条件の問題はあまり出題されません。そのため、徹底的に基礎を固めれば、合格に近づくことができます。
また、出題傾向も学校間で似ていることが多いので、「第一志望は大学附属校にする」と決めたら、併願校も大学附属校の中から探すと効率的に対策できます。
偏差値「60以上」の学校で出題されるような算数・理科の難問対策は不要です。むしろ、予習シリーズレベルの内容を徹底的に抑え、ミスなく得点することが重要です。合格ラインは「7割〜7.5割程度」と上位進学校に比べて高得点勝負になります。
ただ、「早稲田」「慶應義塾」の附属校は問題の難易度や受験者層がワンランク上になるので、個別の対策にかなり時間を割く必要があります。