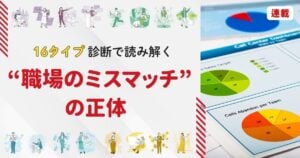ついにBTSが全員揃う。6月、彼らが揃う…我々はこの日を待ち続けた「そこには東アジアの現代文化の開花の一輪がある」

目次
担当氏からの不思議な依頼だった
ついにBTSが全員揃う。
6月、彼らが揃う。
私にとっては尊敬するRMが帰ってくる、SUGAが帰ってくる、みんな帰ってくる、そんな6月である。
ところで、5月。
担当氏からの不思議な依頼だった。
「日野さんの好きをもっと書いてください」
はて、私は「好き」を散々書いているつもりだ。
思えば19歳で商業誌デビューして34年。1990年代はゲームやアニメで散々書かせてもらった。多くのファンが読んでくれた。
スマホどころかWindowsもない時代、インターネットとやらにつながるようになった時代、そんな過渡期から私の「好き」を書いてきた。商業誌の依頼がなければ物書きはこの世に存在しないも同然だった時代、いまのように誰でも書いて、発信して、それこそ世界中に声を上げられる時代とは違った。メジャーにしろ、マイナーにしろ、書き手の商業誌デビューが明確にあった時代だ。
10代にして好きなゲームやアニメは仕事になった。のちに文芸も仕事になった。
それでも他の好きはあった。映画、ファッション、ジャズ、オーディオ、自転車、そして舞踏芸術、フィギュアスケート――芸術で言えばビスクドールも好きだった。自分の好きに限界はないのだから、好きなものは好きと楽しむべきだ。
いまも短詩型芸術の評伝はもちろん羽生結弦という歴史の子、時代の人である稀代のフィギュアスケーター。ニジンスキーやイサドラ・ダンカンといった舞踏芸術の偉人、モハメド・アリのような神話となったファイターまで、私は「好き」を基準に書いている。
それなのに、まだ好きを書けと。そうか。
でもまあ、いっぱいある。
さて、どうしようという時、とくに仕事にしていない「好き」があった。いくつかあったが、彼らなら書きたい。
BTSだ。
羽生結弦もまたBTSが好きだ。氷上を離れ「Dynamite」をパイロット姿で踊る姿はよく知られている
メンバーの中ではRM(キム・ナムジュン)が好きで尊敬している。SUGA(ミン・ユンギ)もそうだ。全員好き(オルペン)だが、そこは論として勘弁していただきたい。どうしても多くの読者に普遍的な伝え方をするため日本語訳も含め平易な書き方になることも。そこは羽生結弦を書く時もそうだが一般読者にも向けた媒体なので専門用語に限界はある。知る人には当たり前の用語にも注釈のつくこともまたお許し願いたい。良いものはなるべく多くの人にも伝えたい、私の執筆主題はそこにある。
そういえば、羽生結弦もまたBTSが好きだと話している。氷上を離れ「Dynamite」をパイロット姿で踊ったり、彼が座長を務めるアイスショウ『notte stellata』(2023年版)でも氷上で踊ってくれたりもした。会場で流れる曲にもBTSがある。かつて羽生結弦は「インスピレーション」「魅せ方の幅」としてBTSに対するリスペクトを語っている。とくにメンバーの中ではJIMIN(ジミン)だとも。いわばジミンペン寄りのオルペン、オルペン寄りのジミンペンということになる。
私は文筆家でもあり詩人・俳人でもある。〈日野百草 俳句〉〈日野百草 俳人〉とか検索すればそれなりには出てくる。その視点で言うなら短詩型芸術とラップのリリック(内面を主とする歌詞)は同一線上にある。俳句の切れ字や韻はまさにライム(ラップの韻)だ。
私は中村草田男の句〈浮浪児昼寝す「なんでもいいやい知らねえやい」〉や尾崎放哉の自由律〈咳をしても一人〉は最高のリリックだと思っている。そこには社会へのやるせなさと自分自身のやるせなさ、激しい怒り、その先の利他がある。
ちなみにラッパーならノトーリアス・B.I.G.や2パックからエミネム、ドレイクなど好むが、RMもまた私の好きの延長線上にある。インターネットでラップと出会う世代であったRMという新しい可能性として――。
RMはかつて詩人になりたかったと語っている(「ローリング・ストーン」2021年6月)。韓国は詩の国(とくに自由詩)であり、詩人は偉大な存在で世間の尊敬を集める。高銀(コ・ウン)や金芝河(キン・ジハ)など世界的な詩人もいる。彼らもまた詩人として、自分の為しうる限りに社会のため、声無き声のために、それこそ命がけで声を上げた。RMもまた現代の詩人である。詩とは散文詩であろうが漢詩だろうが短詩だろうが
そういえば、担当氏は「日野さんが問題にするのはパッションでしょう?」と言った。
その通りだ。情熱がなければ私は書かない。
「そうですね、好きでないものは書きません」
「BTSなら、書きますよ。RMとか」
はっきり言った。ある日本のアイドルグループや羽生結弦でない別の男子フィギュアスケーター、そうした提案は却下してきた。
私は偉ぶっているわけでも、そうした対象を貶めているのでなく文筆家として、芸術修士として私が書きたいか、書きたくないかしかない、それだけだ。羽生結弦は書きたいから書いている、それだけだ。そもそも詩人とはそういうものだ。
もちろん、注文があれば何でも書く書き手もまたプロだ。立派な職人だと思う。しかし私はそうではない。重ねるが、それだけのことだ。
「BTSなら、書きますよ。RMとか」
それでいきましょうと担当氏は即答だった。彼はまだ30代、先の羽生結弦やBTSと同世代、本当に時代は変わったな、そう思った。
まだインターネットのなかった時代から――そう1980年代、私の東アジアに対する興味もまた尽きなかった。高校時代、中学から文学や詩ばかりを読み続けて自然とそちらにも傾いた。そうした傾向に、まだ世は冷淡だった。
冷戦下、中国はもちろん韓国、北朝鮮はまだ近くて遠い国だった。冷戦のあったころとそれ以降、まずこれを踏まえないといけない。日本ではいまや多くは無かったかのようにしているが、韓国では民族分断の歴史がいまも続いている。政治的な話はともかく、BTSすら取り巻く現実である。
政治や経済でない、コンテンツとしての韓国
思えば全斗煥(チョン・ドファン)政権時代だったと思う。まだ韓国は北朝鮮と同様に謎の国だった。1988年のソウルオリンピックからようやく日本に韓国の大衆文化が知られるようになった。
高校時代、私は柏にある新星堂のカルチェ5という書店で『朴正煕の時代 韓国「上からの革命」の十八年』という本を買った。なぜ朴正煕(パク・チョンヒ)だったのか定かでないが、いつぞや観たクーデターの映像がショッキングだったこと、写真のレイバンのサングラスがなかなかにかっこよかった、そんな田舎の高校生レベルの入口だったように思う。
もちろん「漢江の奇跡」と呼ばれた改革の数々もダイナミックでそそられた。朴正煕、毀誉褒貶の人だが、現代韓国を築いたひとりであることは確かなように思う。
実際、残虐な独裁者であった朴正煕がのちに再評価された。韓国が「恨」から一歩、前に進んだ、そんな時代だった。
ちなみにその従前は日本語読みで「ぜんとかん」「ぼくせいき」と呼ぶ時代が長く、私もいまだに脳内ではそうした読み方になる癖がある。盧泰愚(ノ・テウ)政権とソウル五輪のパルパル(1988年)あたりから日本でもハングル読みになったように記憶する。是非はともかく、そういう時代だった。
政治や経済でない、コンテンツとしての韓国を始めて意識したのは少し遅い。19歳、1992年ごろだったか一人暮らしを始めた世田谷、砧のレンタルビデオ店で借りた林權澤(イム・グォンテク)監督の『シバジ』(韓国では1987年公開)だった。
私は母が浅香光代の弟子で若いころは新東宝系の女優経験もある日本舞踊の分家家元だったため五社協定時代の邦画を同世代に比べればよく観ていたが、邦画に比べてもというか、邦画にはない独特の空気があった。李氏朝鮮時代の代理母の話だが主演の姜受延(カン・スヨン)がヴェネツィア国際映画祭で主演女優賞を獲ったこともその時知った。