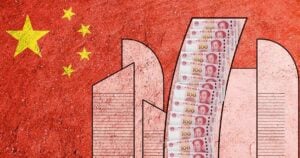トランプ関税を中長期的に0%にすることが夢ではない理由…日本が関税交渉を有利に進めるために持っている重要なカード

トランプ関税発動によって、日本経済の先行きに翳りが見えてきている。ところが、国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏は「トランプ関税を中長期的に0%にすることが夢ではない」という。いったい、どういうことなのかーー。みんかぶプレミアム特集「危機の時代を生き抜く」第2回。
目次
トランプ関税は3つの関税で出来上がっている
トランプ関税を巡る日米交渉が暗礁に乗り上げそうになっている。アメリカとイギリスの関税交渉は多くの手がかりを与えており、日本政府はトランプ関税の性質を詳細に分析して適切な対処を行うことが重要だ。そこで、本稿ではトランプ関税を3つの種類に分けて、各々に対して適切な対応策を提案したい。
トランプ関税は3つの関税で出来上がっている。それは「一律関税」「相互関税」「セクター別関税」だ。この3つの関税は各々目的が異なっているため、それらに噛み合う形で回答を出すことで、トランプ関税を0%に持っていくための大義名分が得られることになる。
第一に「一律関税」について検討してみよう。一律関税は全ての国に対して課された10%の関税であり、米国と緊密な関係を持つイギリスですらその免除を勝ち取ることはできなかった。
これは10%の一律関税は貿易赤字を解消するためのベーシックな意味合いを持つ関税だからだ。10%という数字の根拠には様々な憶測があるが、おそらく根拠はピーター・ナヴァロが過去に算出した公平な貿易が実現した際に約10%の貿易赤字が削減されるという主張にあると推定される。したがって、対米貿易赤字国かつ化石燃料を持つイギリスには直ぐに10%関税を引き下げるだけの輸入拡大の材料がほぼ無かったということだ(いずれは免除されるだろうが、他国に範を見せるために一旦は一律関税が留保された形となったものと思う)。
日本が関税交渉を有利に進めるために持っている重要なカード
一方、日本は米国に対する貿易黒字国である。そのため、日本は輸入を拡大することを通じて、米国に対してプラスのメリットを与えることが可能だ。鍵となるのはやはりエネルギーの輸入である。日本はエネルギー資源を持たない国であり、他国に化石燃料の供給源を求めるしかない。そのため、米国のシェールガス・シェールオイルの輸入を拡大することはエネルギー安全保障の観点からも理にかなっている。特に2月の日米首脳会談で、石破首相が約束したアラスカ資源開発へのコミットメントを本気で進めるなら、米国共和党からは非常に歓迎されることになるだろう。また、イギリスが受け入れたエタノールの輸入拡大も共和党支持基盤の米農家への支援となり、交渉材料としては有効なツールとなるはずだ。
また、トランプ政権が欧州の付加価値税を参入障壁と見做している以上、日本が消費税減税を実施して内需拡大の姿勢を見せることも一つの手である。石破政権は消費税減税を拒否する姿勢を示しているが、日銀が5月1日に発表した展望レポートで2025年・2026年の物価下振れリスクを指摘していることを踏まえ、消費税減税を決断することは国内経済事情に鑑みて何らおかしなことではない。