ロスジェネ世代が苦しんでいるのは“自分のせい”?雨宮処凛が考えるいま必要な支援とは
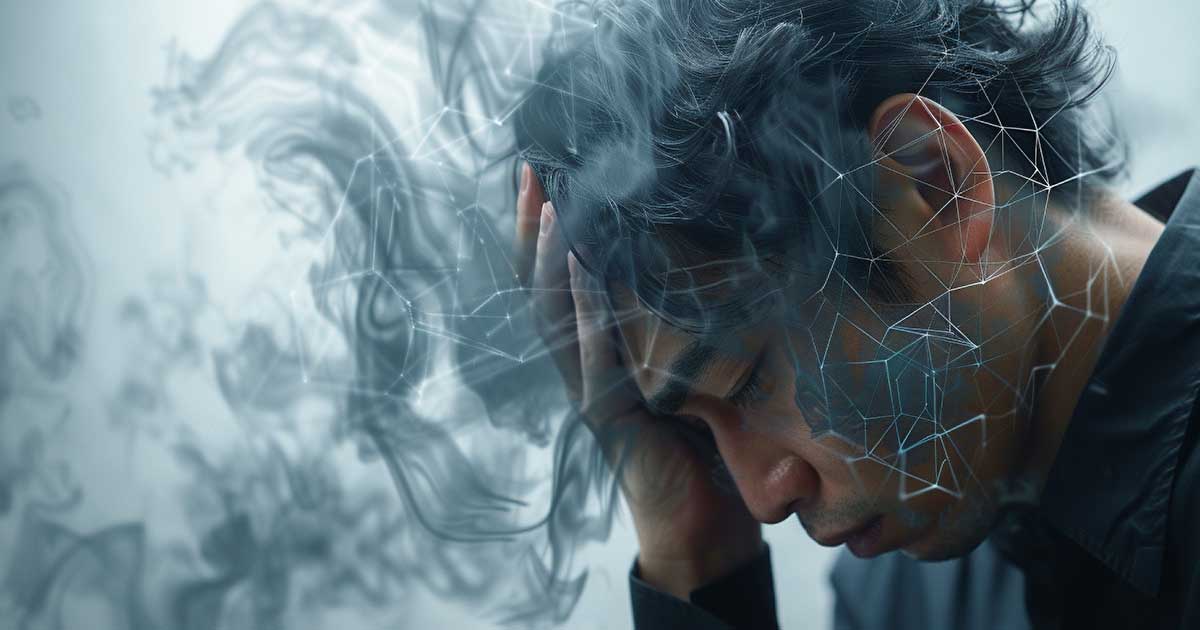
1700~2000万人にも及ぶとされるロスジェネ世代。しかし作家で反貧困ネットワーク世話人の雨宮処凛氏によれば、「ロスジェネ世代はなかなか連帯して声を挙げない」と話す。その大きな原因となっている「自己責任論」と、いま貧困状態にあるロスジェネ世代に必要な支援について、雨宮氏が掘り下げる。
目次
「社会のせいだ」と言えないロスジェネたち
ロスジェネ世代は、「非正規雇用で結婚も子どもを持てないのも自分のせい」という「自己責任論」を強く押し付けられた世代でもあります。小さいころから「なんでもかんでも社会のせいにするのは卑怯者」と言われてきた、あるいはそのようなメッセージを感じてきた人も多く、自己責任論を内在化してしまっています。
ただ仮に「社会のせいだ」と言ったところで、世間から「何甘えたことを言っているんだ」とボコボコにされることも分かりきっています。なので、自己防衛のために先回りして自己責任論を口にする側面もあると思います。
今回の参院選で「日本人ファースト」に多くの人が熱狂したのは、いまの日本の貧しさも大きな原因だと思います。少し前までは「日本は経済大国で、自分たちはお金持ちだ」と思っていたのに、いつの間にか日本経済が衰退して自分たちも没落していたことが、どうしても受け入れられない。停滞や不満、不安の原因を外国人のせいにしてしまえば、自己責任からも逃れられます。
ロスジェネ世代は、連帯もあまりしません。コロナ禍、困窮者支援団体の相談会には貧困状態に陥ったロスジェネ世代の方もたくさん来られますが、「僕はいま、たまたま家も仕事もないけれど、それは不運が重なっただけ。ここに来ているような人とは違う」といったことを口にする人も少なくありません。
自己責任が刷り込まれてしまったために、同じような境遇にある人にも厳しい目を向ける。「今報われていない人はすべて本人に落ち度がある」という価値観の内面化です。連帯は、共感できたり尊敬できたりする間柄でしか生まれません。そのために、同じロスジェネ世代で貧困状態にある人同士であったとしても、なかなか連帯が生まれないのです。
ロスジェネ世代は一枚岩ではない
結果として当事者からなかなか声が挙がらず、「これは社会の問題であり、構造の問題なのだから、みんなでなんとかしよう」という機運も高まりません。もしロスジェネ世代が一致団結して声を上げれば、数が多いのでものすごい力を発揮できると思うのですが、ずっと分断されている。
ただ、この分断は、誰かが意図して生み出したものではないと思います。なぜなら、日本では市民運動などで社会を変えようとして良くなった経験があまりにも乏しい。その結果、「自分たちには力がある」とほとんどの人が思えない。
自己責任論のやっかいなところは、ずっと抱え続けるのが厳しいからこそ、バッシングやヘイトなどとセットになっているところだと思います。
参院選で突如注目された外国人問題もそうですし、公務員バッシングや生活保護バッシング、高齢者ヘイトなどもそうです。「こいつらのせい」としてしまえば、人は束の間、自己責任から解放される。
またロスジェネ問題の難しさは、一口に「ロスジェネ世代」と言っても、一枚岩ではないところにあります。正社員として就職し、結婚し、子どもを持つロスジェネ世代もたくさんいます。正社員と非正規雇用、既婚と未婚、子持ちと子なし、とこれだけでも6通りあるわけです。ひとつの世代にこれほど多様化したライフスタイルがあるというのは戦後日本でも初めてではないでしょうか。
ですからたとえば政府が子育て支援を表明した場合に、好意的に受け止める層と「俺たちのほうが大変なのに」と不満を募らせる層の対立が生まれがち。「ロスジェネ=非正規雇用」といった雑な語られ方をすることもありますが、決してそうではありません。まずロスジェネの中にも多様なニーズがあることを知ってほしいと思います。
ロスジェネ支援はみんなが安心できる社会づくりにつながる
これからロスジェネがどうやって生きていくかを考えたときには、非正規雇用でも独り身でも子どもがいなくても問題なく生きていけるような社会保障制度を整備することが不可欠だと思います。















