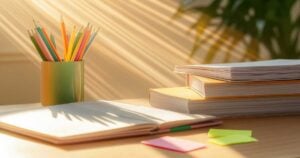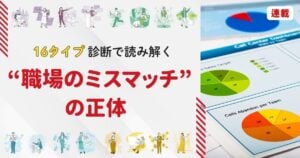焦って難問対策に手を出すのは非効率だ!中受プロが教える「過去問の使い方」

中学受験をめざす6年生にとって「夏をどう過ごすか」は合否につながる大きな分かれ道だ。この夏で大きく伸びる子もいれば、なんとなく過ごしてしまい、後から悔やむ子もいる。
「焦って過去問や難問対策に手を出すのは非効率。どこが伸びしろか、よく見定めたうえで学習の焦点を絞り込みましょう」
そう語るのは、大手中学受験塾の室長を18年務める中学受験Walker氏。中受のプロが教える合格に直結する「6年生の夏休みの過ごし方」とはー。インタビュー全3回の第2回。
目次
過去問は「基礎固め」が済んでから
「過去問は夏の早いうちにやらせるべきですか?」とよく聞かれますが、「焦ってやるのは逆効果」です。
なぜなら、夏の段階では、まだ過去問に太刀打ちできる実力が備わっていない子がほとんどだからです。この時期に第一志望校の過去問を解いても、得点はだいたい30%前後です。半分正解できればかなり優秀なレベルです。
過去問を解けないと子供が自信をなくしたり、モチベーションを落としたりする原因にもなります。ですから、夏のうちは「本格的に解く時期ではない」と心得てください。夏の段階では、親御さんが出題傾向を下見しておくのがベストな使い方です。算数なら計算問題が何問出るのか、理科ならどの単元が頻出なのか。そうした出題の全体像を軽く把握しておくだけでも、今後の学習方針が立てやすくなります。
「解いて丸をつけただけ」の学習ではNO
では、過去問はいつから始めるのか。それは「基礎固め」が終わってからです。過去問は志望校との距離を測って、縮めていくための教材です。基礎が固まっていなければ、解けなかった問題を分析したり、解けるようにしたりするのが難しい。こうなると、「解いて丸をつけただけ」の学習になってしまいます。
偏差値60以下の学校であれば、標準問題と過去問のレベルの差がそこまで大きくないため、基礎固めをしっかり行いましょう。10月以降の着手でも十分間に合います。
偏差値60以上の学校を目指す子なら、9月から4〜5年分を目安に取り組み始めて良いと思います。
9〜10月にある程度の量を解いておき、その結果をもとに11〜12月は弱点の補強に集中する。そうすることで、最終的な得点力が上がりやすいですね。