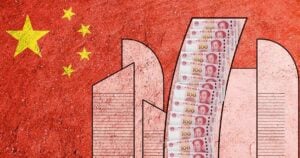終了のお知らせ…トランプ「ESGは詐欺」地球環境と金融は結局両立しなかった

「ESG」という言葉は、かつて金融の世界に大きな期待を背負っていた。資金を動かすことで地球環境を守り、社会の課題を解決し、同時に企業統治も改善される──そんな理想が描かれていた。しかし現実は、理想ほど美しくはなかった。政治の思惑に翻弄され、数値は取り繕われ、理念は形だけと化していった。残ったのは、資本と社会をどうつなぐべきかという「空白」である。いま、その空白を埋めようとするβアクティビズムやインパクト投資といった新しい動きが、少しずつ姿を見せはじめている。日経新聞の編集委員である小平龍四郎氏が、「次の金融のかたち」を探るーー。
目次
「善意の投資」が幻想と化した日──ESG信仰の崩壊
前回のコラムで筆者は、ポストESG投資として「βアクティビズム」という考え方を紹介した。本稿はその続編の位置づけだ。市場全体の底上げを図る「β」からさらに一歩進み、企業活動が社会に良い影響をもたらすよう促す「インパクト」への進化だ。行き着く先はまだはっきりとは見えないが、世界の投資家たちはその方向に粛々と歩みを進める。日本の証券会社にこの地殻変動が見えているか。
かつて投資家たちは、夢を見ていた。資本を流せば、地球が救われる。ポートフォリオに善意を忍ばせれば、社会が変わる。「ESG」とは、その夢に貼られた美しいラベルだった。
環境(E)、社会(S)、企業統治(G)──三つの理想が同時に実現されるという、甘やかな構図。それは信仰に近かった。数字ではなく物語を信じ、ロジックではなく正しさの余韻に酔う。だからこそ、それが政治に足をすくわれたとき、幻想はひどく醜く砕けた。
夢の終わりに立ち尽くす投資家たち
金融に倫理を持ち込むこと自体が、そもそも矛盾だったのかもしれない。ESGは、金融の冷たい論理に温もりを与える夢だった。企業も投資家も、証券マンも官僚も、皆がその火に手をかざした。
ある者は「サステナブルファンド」と名乗り、ある者は「ESGストラテジスト」の肩書で講演を重ね、ある者は新聞に、ある者は統合報告書に、三文字を散りばめた。
けれど、それらの多くは「語りの技巧」に過ぎなかった。数字が正義を語ったのではない。正義が数字の衣をまとっただけだった。
そして2020年代半ば、夢から覚める者がひとり、またひとりと増えていった。
数字が示す退潮──日経紙面から消えていく「ESG」の三文字
ドナルド・トランプは、ESGを敵視した。統計局長を更迭し、中央銀行人事を私物化し、ESGを「詐欺」呼ばわりした。だが、彼が壊したのは理念ではなかった。暴いたのは、その理念のもろさと、信じる側の脆さだった。