ガソリン減税の代わりに「新税検討」報道に国民激怒&絶望…なぜ政府は消費税にここまでこだわるのか「問題の本質は全てここに」
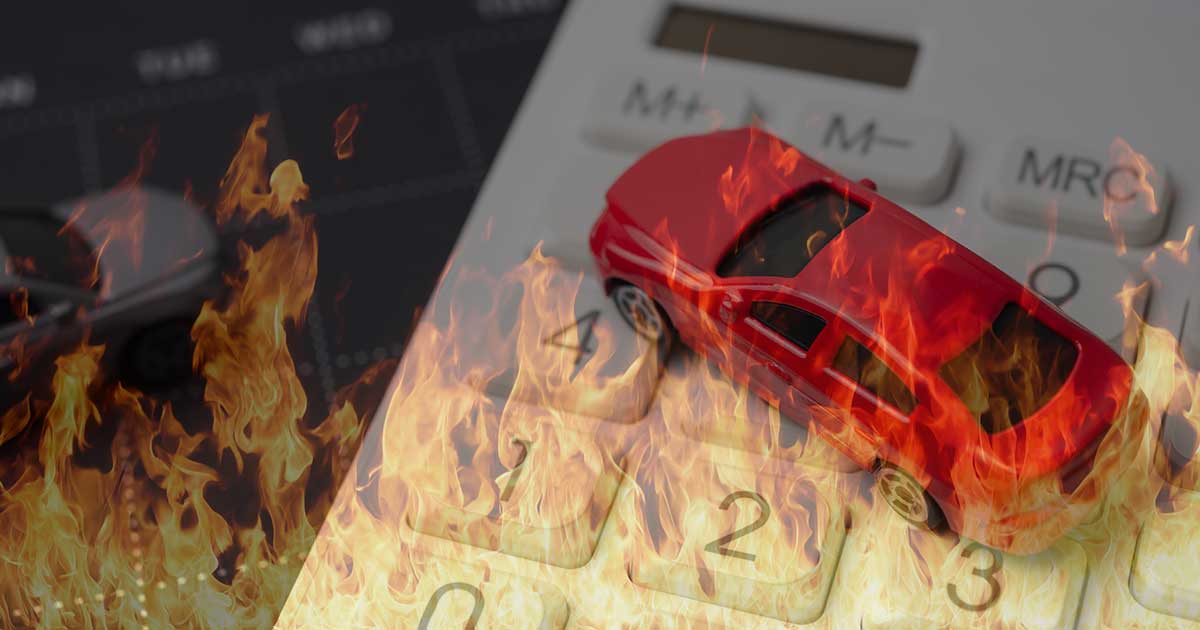
減税か給付かーー。参院選は減税を掲げた新興野党の急進と、給付を掲げた与党の大敗で終わった。そしてガソリン減税に向けて、進むはずだった。が、朝日新聞が報じた記事によると「老朽化が進む道路や上下水道などの維持・補修に充てる財源を確保するため、政府は新税の創設に向けた検討に入る」という。これでは、せっかく減税を選挙で勝ち取ったはずなのに何の意味もないではないのではないか。SNSでは「減税詐欺」「国民をバカにしている」という声があがる。
こうした「死んでも減税してたまるか」という政府の動きの背景には、日本の財政の悪化がある。なぜここまで悪化したのか。その理由の一つに、政治家が決して手放そうとしない「安定財源」の存在がある。それが消費税である。1989年の導入から35年以上、消費税は「景気変動に強い」「高齢者からも取れるから若者に有利」「生涯所得で見れば逆進性は緩和される」といった肯定論で正当化されてきた。だが、実態は異なる。
消費税は「公平な負担を広く求める税」などではなく、消費者を人質にして借金を膨張させ、政治を堕落させる制度である。その本質を直視しなければ、財政再建も社会保障改革も進まない。本稿では、財政と制度の仕組みをもとに、消費税が背負う「三つの大罪」を減税インフルエンサーのキヌヨ氏が詳しく検証する。
目次
第一の大罪──財政規律を壊し、借金を拡大させた罪
消費税はしばしば「財政健全化の切り札」として語られてきた。確かに、所得税や法人税に比べれば景気変動に左右されにくく、安定的に税収が確保できる。だからこそ財務官僚は「消費税こそが国の土台」と強調し続けてきたのだ。
しかし、この安定性が実は最大の害悪だった。財政法第4条で赤字国債の発行を原則禁止している。戦後の財政規律を守る「最後の砦」だった。ところが、現実には毎年「特例公債法」を成立させ、赤字国債を常態化させている。その裏で、国債市場の投資家が日本国債を安心して購入できる理由がまさに消費税なのである。
不況時であっても必ず入る税収。法人税のように赤字企業から取れないものではなく、売上に対して確実に課される。これを市場は「返済の抵当」とみなし、「巨大な内需を持つ日本の政府はまだ借金しても返せる」と判断してきた。
つまり、国民の消費が政府の借金の抵当に差し出されてきたのである。消費者は財政規律の守護者ではなく、借金を正当化するための人質にされてきたと言える。
借金まで増やす二重の害悪を持つ消費税
その結果、1989年度に6兆円程度だった新規国債発行額は、バブル崩壊後も右肩上がりに膨らみ、2020年代には50兆円を超える年も珍しくなくなった。国債残高はGDP比で260%を超え、主要国で最悪の水準に陥っている。
ここで見逃してはならないのは、他の税と違って、消費税は税負担そのものだけでなく、借金まで増やす二重の害悪を持つことである。所得税や法人税は景気変動に応じて税収も減り、自然と歳出にブレーキがかかる。しかし消費税は安定的に取れるがゆえに、政府に「まだ借金できる」という錯覚を与え、歳出の暴走を許した。
消費税が本来果たすべき「財政健全化」ではなく、財政規律を壊す構造的要因として機能してきたのである。これが第一の大罪である。
第二の大罪──現役世代の市場と雇用を奪った罪
消費税は「高齢者からも取れるから現役世代に有利」という説明が繰り返されてきた。一見もっともらしく聞こえるが、経済全体の構造を無視した議論である。
消費税は消費行動そのものに課税するため、国内需要を恒常的に抑制する。特に所得の低い層は消費性向が高く、わずかな税負担の増加でも支出を削らざるを得ない。これが波及して企業の売上が落ち込み、投資を先送りし、雇用を減らす。現役世代は縮小した市場で働かざるを得ず、賃金上昇やキャリアアップの機会を奪われるのである。
















