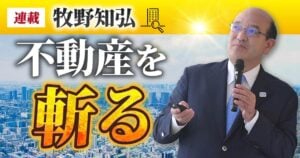高騰する湾岸エリアの土地は過大評価か 不動産のプロが喝破する湾岸タワマンの不都合な真実「客観的な事実として…」

都心マンション価格は天井知らずの高騰を続け、溢れる情報と「バブル崩壊」の警鐘に、多くの住宅購入検討者が迷いを深めている。こうした状況に振り回されないための“基礎体力”こそ重要だと語るのは、不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏だ。
土地の本質的価値を読み解く方法から、コロナ禍以降のマンション価格高騰のカラクリ、将来的な不動産価値の見極め方、さらには首都圏の穴場エリアまで、同氏に縦横無尽に論じていただいた。短期連載全4回の第1回。(取材日:8月12日)
目次
溢れる不動産情報に振り回されないための“基礎体力”の鍛え方
――本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、新しい著書『不動産の教室』(大和書房)についてお聞かせください。帯には「バブル崩壊に備えよ」とかなり刺激的な言葉が書かれていますね。
よろしくお願いします。ああ、これですね(笑)。この帯は出版社さんがつけるものなんです。ですから、私自身が「バブルだ」「バブルが崩壊する」と主張したくて書いた本ではまったくありません。むしろ、この本の中ではバブルやバブル崩壊については、実はあまり書いていないんです。
どちらかというと、この本は不動産の「基礎」をきちんと知っていただくための、いわば教科書のような本を目指しました。不動産のあれこれについて、歴史も遡りながら、真面目に、そして丁寧に解説しています。
不動産選びの迷いを断ち切る“一生モノ”の知識とは
――これまでの牧野さんの著書は新書が多く、手軽に知識を得られるイメージがありましたが、今回はより体系的に、深く学べる内容になっているのでしょうか。
そうですね。本書は5章立てになっていまして、各章でそれぞれ5つの質問を設けて、それに答える形で構成しています。ですから、興味のある章から読んでいただいてもまったく問題ありません。
不動産に対して、なんとなく「もやっ」と感じている疑問や不安を、この本を読むことで解決していただければと思います。1冊読めば、かなり体系的に不動産というものを理解できるようになるはずです。歴史については、それこそ江戸時代のことから書いてありますから。
なぜ現代のマンション購入に“江戸時代の知識”が役立つのか
――江戸時代からですか! 歴史を知ることは、現代の不動産選びにも役立つのでしょうか。
もちろんです。たとえば、地名に「沼」という文字がつく土地は避けたほうがいい、というような話を聞いたことがあるかと思いますが、それも歴史的な背景を知っていれば納得できます。
ひとつ例を挙げましょう。東京の六本木にある「東京ミッドタウン」。あそこは旧長州藩・毛利家の大名屋敷があった場所です。実は、大名屋敷の跡地というのは、比較的地盤が強固で、高台にあって災害の被害を受けにくい場所に建てられていることが多い。つまり、昔の大名屋敷の跡地という情報を知っていれば、マンション選びの際に、その土地が比較的安全な立地である可能性が高い、という一つの判断材料になるわけです。
私たちが今いるこの汐留も、その名の通り、昔は海で、潮の流れを食い止めるために整備された土地です。新橋や京橋、日本橋に「橋」がつくのは、昔は船で物資を運んでいて、そこが荷揚げ地だった名残です。ちなみに新橋は、もともと木材が集まる場所だったので、今でもその名残で木材組合があったりします。
このように、土地が持つ歴史的な意味や役割を知ることは、不動産の本質的な価値を見抜く上で、非常に大きなヒントを与えてくれるのです。
豊洲・勝どきの土地評価は、多くの人が思うほど高くない
――歴史的背景という観点からすると、現在の湾岸エリア、たとえば豊洲や勝どきといった埋立地のタワーマンションの価値はどのようにご覧になっていますか? 価格は天井知らずで高騰していますが。