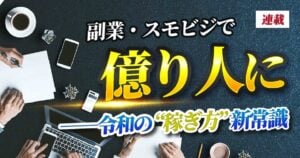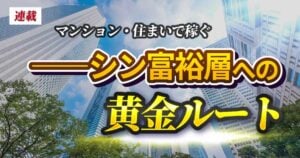投資にかけたその時間、無駄じゃないですか?億越え投資家がたどり着いた「手間をかけない投資」の魅力

20年超のインデックス投資歴を有する水瀬ケンイチ氏は、インデックス投資こそが「投資に時間も労力もかけず、仕事や趣味、家族との時間を大切にしながら資産形成ができる合理的な手法」だと説く。なぜインデックス投資が成果を生み出すのかについて、水瀬氏が解説する。全3回中の3回目。
※本著は『彼はそれを「賢者の投資術」と言った 水瀬ケンイチのインデックス投資25年間の道のり全公開』(Gakken)から抜粋、再構成したものです。
第1回:「これこそ私の求めていた投資法だ」山崎元氏がもっと信頼した個人投資家が、インデックス投資にたどりついた理由
第2回:長期的なリターンを逃すのは“売買のタイミングを測る”から……億越え投資家「最後はインデックス投資に帰ってくることになる」
目次
成績がいいのは「投資に時間を使わない投資家」
投資に費やす時間と投資成績の関係については、意外な研究結果がある。モーニングスター社のマイケル・ポンペイアン氏による『Behavioral Finance and Wealth Management』(第2版、2012年)では、投資に費やす時間が多い個人投資家ほど、運用成績が低い傾向があることが示されている。具体的には、週に10時間以上投資関連の活動(情報収集、分析、売買など)を行う投資家の平均リターンは、月に1、2時間程度しか費やさない投資家よりも約1.5%低いことが示されている。
私の場合、個別株のチャート分析やファンダメンタル分析にのめり込みすぎて、生活が破綻しかけていたのだが、インデックス投資に切り替えたときは、拍子抜けするくらいやることがほとんどなかった。世界がぱあっと彩りをとりもどしたように感じ、止まっていた時間が動き出したような感覚があった。平日も土日祝祭日も常に心にあった黒い霧が晴れ、心が楽になった。
投資に費やす時間が減ったことで、家族との時間、趣味の時間、健康のための時間が増えた。20代後半でチャート分析やファンダメンタル分析に夢中になっていたころには休日もほとんど投資の勉強に時間を費やしていたが、インデックス投資に切り替えてからは、週末に家族と旅行に出かけたりするだけでなく、国内だけでなく、カナダのウィスラーでスノーボードを楽しんだり、北海道でカラフトマスやサケ釣りを楽しんだり、推しのサッカーチームを追いかけてスタジアムがある全国様々な県を訪れたり、趣味もよりアクティブになった。
遠く離れた場所にいる会いたかった人にも会いに行けるようになってきた。最近では野鳥観察という新しい趣味も始めることができた。長い時間野鳥が現れるのを待つことも多いのだが、東京都内にもかかわらず、瑠璃色に背中と翼が輝くカワセミを発見したときの感動は新鮮だった。聞くところによると、海外のカワセミはまた違った色をしているらしい。ぜひ探しに行きたいものである。まさに人生の質が変わったと実感している。
私にとって、最も優れた投資戦略とは、最も手間がかからない投資戦略だったのだ。価値観は人によって異なることは承知しているが、投資をやっていない人が大半であるという現実を考えると、投資が趣味でも仕事でもない人が世の中にはたくさんいると考えられる。手間がかからないことの価値は、一般的にも相応に高いといえるではないだろうか。