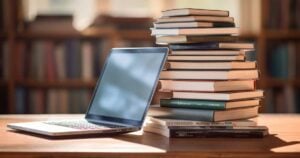「暗記」が面白くなる!大河解説YouTuberが教える受験で悩まない「歴史学習法」

中学受験で求められる内容は、ハイレベルな算数、高度な心情理解が求められる国語、複雑な実験考察が求められる理科など、深く、そして多岐にわたる。
そんななかで、家庭で求められる暗記量が非常に多く、受験生が苦戦しがちなのが歴史だ。授業だけでは到底覚えきれず、家庭での取り組みが学力に直結する。
「日本の受験教育で“歴史って単に暗記するだけの科目でしょ?”“年号や人名をひたすら覚えさせられて、嫌いになってしまった”という人は一定数います。しかし、これは非常にもったいない」
大河ドラマの解説を中心に、YouTubeチャンネル『戦国BANASHI』で歴史関連動画を発信しているミスター武士道氏によると、「歴史が楽しい」と思えるかどうかで、理解の深さや知識の身につき方が大きく変わるという。
子どもを歴史好きにさせるには、どうすれば良いのか。どうやれば歴史の知識が定着しやすくなるのか。ミスター武士道氏に聞いた。全3回の第1回。
目次
「歴史は暗記科目」という誤解が生まれる理由
最初に「歴史嫌い」や「歴史が苦手」な人が生まれてしまう背景について考えてみたいと思います。
学校や受験で扱う歴史は、結果や結論ばかりに焦点を当てがちです。試験に出題されるのは、「誰が何をしたのか」「何年に何が起きたのか」がメインです。そのため、歴史上の出来事の名前を覚えたり、人名を暗記したりすることに重点をおいて学習させたほうが効率的なのかもしれません。
しかし、歴史上の出来事の結末だけを覚える学習では、無味乾燥にしか感じられないでしょう。歴史の面白さは「どうしてそうなったのか」のプロセスにあります。
「1615年大阪夏の陣で豊臣家が滅亡。徳川幕府の支配が安定」と教科書的に暗記するのではなく、「関ヶ原の戦い以降も大阪城に居を構えた豊臣家。それを何としても潰したかった徳川家康。その積年の対立が2度の戦いで終結する」という流れや背景を知ることで歴史はぐっと面白くなります。
こうした「物語性」は歴史のテキストにはあまり載っていません。できればご家庭で、歴史漫画や小説、ドラマなどで「なぜ」「どのように」という部分を補ってあげてください。
私は中学受験の専門家ではありません。「一つ一つの出来事にそこまで時間はかけられないよ」という声もあるかと思います。
しかし、歴史上の出来事には“流れ”や“背景”があるという感覚を掴んでおくことで、学習がより楽しく、効率的になるのではないでしょうか。