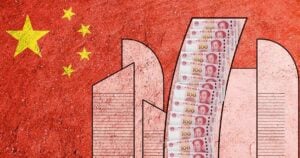やばいぞ来週終わる!ふるさと納税が9月でポイント付与終了「制度で損するのはこんな人」…高まる駆け込み需要に「最後のチャンスだ」

庶民のひそかな楽しみとなってきた「ふるさと納税」が10月から変わるのをご存じだろうか。2008年5月にスタートした制度自体は存続するものの、寄付に応じて得られてきた仲介サイトのポイント付与が禁止されるのだ。返礼品や節税に加え、ポイント獲得を期待してきた人々からは嘆きの声が漏れる。経済アナリストの佐藤健太氏は「たしかにポイント競争は過熱してきた面があるが、いちいち国が規制するのはいかがなものか。高まっている『駆け込み需要』は行政への反発とも映る」と指摘するーー。
目次
ふるさと納税で東京都の減収額は計1兆円を超す
自分の故郷や思い出の地域など、好きな自治体に寄付できる「ふるさと納税」は2008年5月にスタートした。人口減少に伴う自治体の税収減や地方創生を目的に創設された制度で、毎年1月1日から12月31日まで年間を通じて寄付することができる地方応援の形だ。好きな自治体に寄付することで所得税や住民税の「節税」ができ、さらに返礼品までもらえると利用者は増えてきた。
利用者は2020年度に約400万人となっていたが、2022年度には約740万人にまで拡大。2024年度、全国の自治体には過去最高の約1兆2728億円が寄付された。総務省が今年7月末に発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果」を見ると、2024年度のふるさと納税受け入れ件数は約5879万件に上る。住民税の控除を受ける人は約1080万人で、2009年度の3万人程度と比べると爆増してきた。
住民税の控除適用者数が最も多いのは、東京都の約200万人が最多だ。2位は神奈川県の約104万人、3位は大阪府の約89万人、4位は愛知県の約78万人、5位は埼玉県の約68万人と続き、大都市圏に多いことがわかる。制度がスタートしてから東京都の減収額は計1兆1593億円にも達している。
逆に、ふるさと納税受入額が多いのは兵庫県宝塚市の約257億円がトップで、2位は北海道白糠町の約212億円、3位は大阪府泉佐野市の約182億円となっている。全体の寄付額である1兆2728億円に対し、ふるさと納税の募集に要した費用は自治体財源が6826億円と53.6%を占め、「返礼品」は3208億円(25.2%)、「事務所費等」1676億円(13.2%)だった。