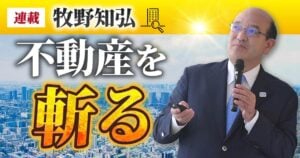FX平均利回り月40%、株は2年で4倍・・・両方で利益確保する会社経営者の利確タイミングと「スイングトレードに手を出さない」ワケ

会社を経営する傍ら、中長期投資やFXのトレードの道も極めるクロ(黒田雄士)@型とデータの鬼(@fxrealtradelive)さん。
株とFX両方で利益を残しているクロさんにリスクリワードの比率、FXで戦う時間帯について伺いました。インタビュー全3回の第2回。
目次
守るべきシンプルなトレードルール
ーーFXをメインで取引されているクロさんですが、現在はどの通貨でトレードをされているのでしょうか。
ユーロドル、ポンドドル、ユーロ円、ポンド円、ドル円の5つを基本として見ています。ほかに余裕があれば豪ドル/米ドルや豪ドル/円など、オセアニア通貨のメジャーなものをチェックすることはありますが、マイナー通貨はなるべく触らないようにしていますね。
ーーそのトレードルールについて教えてください。
メジャー通貨ペアのトレードで共通して使えるように、ルールはなるべくシンプルにしています。
基準にしているのは1時間足で、その日のデイトレードでは「どちらの方向で攻めるか」という目線をまず決めます。その後、4時間足や日足で20、40、50、100の4本の単純移動平均線(MA)を確認します。僕の設定については、X(旧Twitter)の固定ポストにもまとめてあるのですが、そのMAがエントリーしたい方向に対して逆方向を向いていないかを確認します。
目線も良く、MAとローソク足の間に空間も十分にあると判断できたら、次は5分足や15分足を見ます。そこで、僕が持っている「3つのMAタッチのパターン」のいずれかに当てはまったときに、プルバック(相場が上昇や下降のトレンドを描いている途中で、一時的に逆方向へ戻す動きのこと。押し目買いや戻り売りの好機とされている)を待ち、条件が揃ったら指値を入れて待機する。基本的にはそういう戦い方をしています。
リスクリワードの設定は?
ーーリスクリワードは決めていますか?
「1:1」にすることはなく、だいたい「1:2」から「1:3」で決めていますね。利益を大きく狙えない時はリワードを2で抑えますし、「これなら十分取れる」と判断できる時は3まで取りにいきます。ただ、それ以上は狙いません。
ーー1回の損切り許容率はどれぐらいでしょうか。
1回のトレードで約1%です。最初に設定した損切り幅が小さければ、その分利食い幅も小さくなるという形です。
ーーただ、FXの場合「まだ伸びるかもしれない」と思って握っていたら、急に反転してしまうこともありますよね。
結局、どこまで伸びるかは誰にも分からないため、リスクリワードを1:2以上に設定するのです。もちろん一発で大きく取れれば気持ちは良いですが、再現性がありません。それよりも「いつもこのリズムで利確と損切りを積み重ねて、最終的にプラスにしていく」という方が安定します。ルールを守っている限り負けないと分かれば、本人も安心して運用できますよね。
まだ伸びるかもしれないと握り続けるよりも、「ルールだからここで利確」と決めてしまうのが一番良いと考えています。
ーーでは、FXで取引する時間帯についてはどう決めていらっしゃいますか?
僕の場合、メインはロンドン時間の初動で、だいたい午後2時から夕方6時にトレードします。そのほかは朝、子どもの送り迎えなどの合間にチャートを見て、「これならいけそうだな」と思った時にトレードすることもあります。朝はクロス円といえど、そこまで大きく動かないので、あくまで「サブ」という位置づけです。
ーーニューヨーク時間で取引することはないのでしょうか?
今はルールとしてやらないようにしています。日中は仕事でトレードにも集中していますし、夜は子どもが帰ってきて家がバタバタする時間帯です。そんな中で、自分だけがPCなどの画面に張り付いてトレードしている姿は少しかっこ悪いかなと思うので、それなら夜は休む時間にしてしまおう、と決めました。
ーーファンダメンタルズはどれくらい重視されていますか?
ファンダメンタルズは、トレード判断には一切組み込んではいません。たとえば政策金利の結果が出たとしても、過去に同じ数字が出たとしても市場の反応はその時々で全く違います。つまり、マーケットがどう反応するかを先読みすることは不可能だということです。
また、FXは株に比べてスピード感が圧倒的に速いので、ファンダメンタルズを加味して一貫性ある分析を続けるのは難しい。だから僕はもう、考慮しないと決めています。
ーークロさんは株もされていますが、株で投資をする上でファンダメンタルズはどんな位置づけですか?
株はもちろん気にします。ただ、株は頻繁に売買するものではなく、1年以上持つこともあります。今も持っている銘柄については、景気動向に左右されにくいディフェンシブ株として引き続き保有して問題ないかを判断するために、日々の経済動向には目を光らせています。
依然としてインフレの流れは続くと見ていますので、その前提で保有を続けていますね。