誰が対象?高市総理のこだわり「給付付き税額控除」で“最大16万円給付”は本当なのか…主なメリット2つ
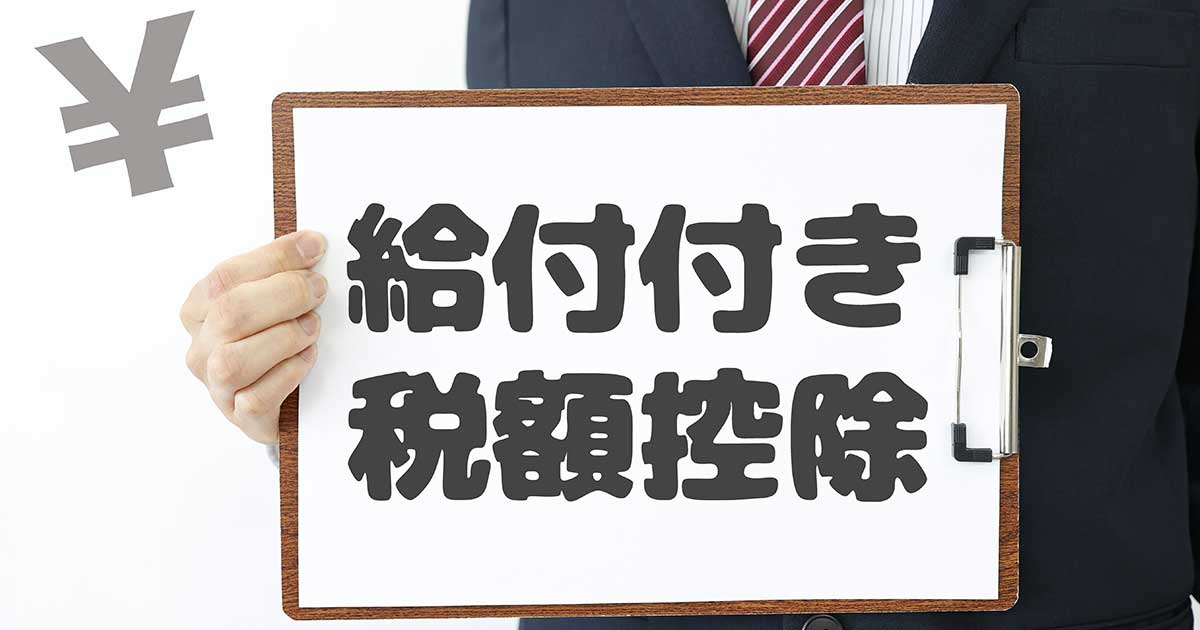
高市早苗総理大臣が誕生し「給付」か「減税」か、の議論に終止符を打つかもしれない。政府が検討しているのは、「給付付き税額控除」という制度で、いわば給付して減税するシステムだ。政治に詳しいコラムニストの村上ゆかり氏が解説するーー。
高市首相の解説本を発売しました!
目次
立憲案、世帯あたり最大16万円
給付付き税額控除とは、税金を減らすだけでなく、税金を払う力が弱い人にも現金で支援が届く仕組みのことだ。所得が低く税金をあまり納めていない人は控除の恩恵が少ないため、税金で減らせなかった分を給付として受け取れるようにする考え方である。
立憲民主党のプロジェクトチームが2025年春にまとめた原案では、1人あたり4万円の給付を基準とし、夫婦と子ども2人の世帯では合計16万円が上限となり、年収670万円未満は満額を受け取り、670万円から1232万円までは所得に応じて減っていき、1232万円を超えると給付はゼロになる。給付は公金受取口座に自動的に振り込む想定である。報道によると、必要な財源は約3.6兆円とされると報道されている(テレビ朝日)。
自民党は、制度の方向性として給付付き税額控除を検討対象に含めている。政党ごとの温度差はあるものの、自民党や立憲民主党以外の主要政党も「支援の即効性と持続性」を重視し始めており、立憲案はその先陣を切る形になっている。
給付付き税額控除、主な2つのメリット
給付付き税額控除のメリットは主に2つある。1つめは低中所得層の家計を直接支える点であり、食料品や光熱費など生活必需品の価格上昇分を埋める効果がある。2つめは所得の逆進性を緩和できる点で、消費税のように誰でも同じ税率で負担する仕組みは、所得が少ない人ほど負担感が重く、給付付き税額控除はその痛みを返す仕組みになる。行政インフラ面は確定申告、源泉徴収、マイナンバー制度などが整っており、技術的には不可能ではないかもしれない。
しかし現実的な障害は、制度信頼を損なうリスクにあるだろう。まず、正確な所得の把握には限界がある。所得情報は即時に反映されないことが多く、申告漏れも少なくない。特に個人事業主やフリーランスでは、最新の所得をリアルタイムで把握することは難しい。所得をもとに給付額を判定する制度では、わずかな誤差が不公平感を生む。
















