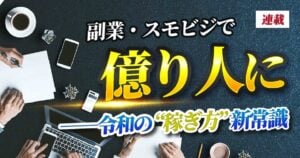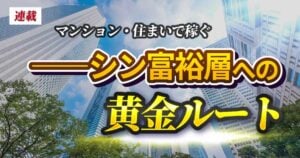飲み会がビジネスにつながる!「1つ1万円のお菓子」でもコミュニティビジネスなら売れてしまうかもしれない理由

コミュニティを率い、これまでにたくさんのプロジェクトを成功に導いてきた、実業家・投資家・映画プロデューサーの嶋村吉洋氏。しかし、なぜ人は嶋村氏のコミュニティに参加するのだろうか。嶋村氏の考えるコミュニティのあり方と、そのコミュニティがどうやってビジネスにつながっていくのかについて、同氏が語る。全3回中の2回目。
※本稿は嶋村吉洋著『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』(プレジデント社)から抜粋、再構成したものです。
第1回:あなたの人生を劇的に変える「コミュニティ」……常識を捨て、起業よりも先にコミュニティをつくれ
第3回:「集まって楽しい」の一歩先へ……コミュニティが売上を生み出していくための3つのステップ
目次
コミュニティは「楽して儲かる」場ではない
私の関わっているコミュニティは、すでにそれなりの規模になっているので、いろいろな人が集まってきます。中には「ここに入れば、儲かるかもしれない」と期待して、紹介されるままにイベントに参加する人もいるようです。
ただ、実際に会って話をしてみると、「楽に儲かると思っていたのに、3年は地道に働かないといけないと言われた」と言って去っていく人もいます。私自身は、どこで話しても割と現実的なことしか言わないのですが、「そんな話は聞いていなかった」と感じる人もいるようです。
でも、現実のビジネスを考えてみると、独立して起業した会社の多くは1年以内に姿を消します。10年後に残っている会社は、わずか6%程度だと言われています。それだけ、一つのビジネスが形になるのは難しく、時間がかかるものです。
世の中には「簡単に儲かる」ということを謳って、人を集めるコミュニティもあるようです。そうしたコミュニティが本当に存在するのか、あるいは詐欺的なのかはわかりませんが、私たちは地道に現場で汗をかき、みんなで協力しながらビジネスを立ち上げています。
「楽して儲かる」「すぐに儲かる」という話が好きな人は、他のコミュニティに行っていただくのがいいと思います。
チャレンジャーが自然と集まってくる環境
では、実際に私たちのコミュニティの中では、どのようにビジネスが始まるのか。
よくある例として、飲食店を考えてみます。「自分のお店を出したい」という人は、勉強会などで「こんな店をつくりたい」とか「こんな料理を出したい」といった話をします。
その段階で「出店したら必ず食べに行きます!」という、いわば“お店のファン”をつくるのです。実際にお店ができると、みんなが訪れるので、開店直後から、かなり盛り上がります。
こういう理由から、コミュニティがあることで「失敗しにくい」ということが、ある程度は言えるかもしれません。
ただ、コミュニティ内のお客様だけで回していっては、成功の規模は限られます。 そこで、私たちのコミュニティでは、コミュニティメンバーの友人や、一般のお客様が集まるように、コミュニティがいろいろな形で協力しています。
実際、私たちのコミュニティには、各分野の専門家が増えてきました。たとえば、メニュー開発やロゴデザインの製作、ホームページの作成やPRの方法、SNS運用まで、さまざまな面でアシストできるメンバーが揃っています。
出店の際には、不動産コンサルタントや税理士、行政書士なども協力してくれます。もちろん、仕事として関わる以上、報酬やコンサル料が発生します。それでも、普通にお店を立ち上げるよりも安く、早く、しかも専門家のアドバイスを受けながら進められるのは大きなメリットだと思います。
そして、有名になった仲間のお店が増えてきました。協力するのは専門家だけではありません。仕入れを共同で行ったり、場合によってはコミュニティ発の店舗に従業員として参加したりすることもあります。
コミュニティ内の積極的な協力も伴って、口コミが広がりやすいのです。開店日にはコミュニティメンバーが集まり、初日から行列ができることも珍しくありません。地道に活動することで、私たちもノウハウが蓄積されてきました。
おかげで私たちのコミュニティには「起業や店舗経営で成功する人が多い」という認識が共有されているようです。そのため、「自分もそうなりたい」と考える人が自然と集まってきています。