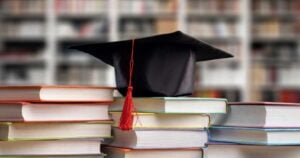「大学や学生の変化を知らないと、優秀な人材を取り逃してしまう」人口減少、学部増・・・進学塾代表が見る令和時代の採用術

近年、採用市場で「最近の学生は質が落ちた」という声を耳にする機会が増えた。以前と同じ学歴フィルターを使っているはずなのに、最近は優秀な学生に出会えない、せっかく優秀な学生に内定を出したのに他社に取られてしまった。
「かつては大学入試によって学生の能力がある程度振り分けられていましたが、今はそうではありません。同じ大学名でも、学生の能力差が非常に大きくなっているんです。特に、多くの企業が採用のボリュームゾーンとしているMARCH(明治、青山、立教、中央、法政)は、人口減少や大学教育の変化の影響を強く受けています。大学や学生の変化を知らないと、優秀な人材の取り逃してしまうかもしれません」
そう語るのは進学塾VAMOSの富永雄輔氏だ。採用担当者が知っておくべき現代の大学受験環境と、大学生の実像とは何か。全3回の第2回。
目次
人口減少、学部増で広がった間口
採用担当者の方にまず知っていただきたいのが、大学受験を巡る環境変化です。
18歳人口は1992年には205万人いたのが、2024年には106万人へと半減しました。一方で大学進学率は26.4%から59.1%へと倍増しています。入試倍率もバブル期には7〜8倍あったのが、現在は4〜5倍程度まで低下しました。
また、この期間でMARCHを始めとした有名大学の入学間口は広がっています。明治大学、法政大学、青山学院大学は相次いで夜間学部を廃止し、その分昼間学部が拡充しました。また、どの大学でも新学部が次々と設置されています。
一般入試の負担も軽減されています。2000年以降に新設された文系学部の多くでは、古文・漢文が入試から外されています。また、英検などの検定試験の結果を活用できるようになったり、共通テストを一部科目で代替したりする制度も広がっており、大学独自の個別入試の比重が相対的に減っています。
大学受験に関する最も大きな変化が、推薦・総合型選抜の拡大です。1995年時点では大学入学定員に占める推薦入試の割合は約30%程度でしたが、現在は約50%を占めています。
入試方式が多様化したことで自分が得意な方式を選べば、有名大学に滑り込むこと自体は難しくなくなりました。入りやすい学部学科・入試方式を選べば、かつてより、かなり簡単に入学できるため、同じ大学でも学力のばらつきは大きくなっています。
そして、今の大学生はかつての世代に比べて、大学名を重視していません。
かつてのように「浪人してでも絶対に◯◯大学に行く」という受験特化型の高校時代を送る人は減少傾向で、部活や課外活動に打ち込んで充実した高校生活を送り、自分が得意な方式で受験をして現役で進学するのが一般的になっています。
現役合格志向が高まっていることで、かつてであれば一浪して早稲田、慶應を目指していた学生が、現役でマーチに進学していることは、MARCHの学生の質を理解するうえで重要かと思います。
また、高校・大学時代の課外活動などで、学生の学力以外の質に大きな差がつくようになっています。