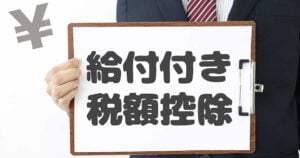もう限界!訪日客が地域の存続脅かす…舞妓を追って私道侵入、交通麻痺!政府が無計画に煽った「観光PR」ツケを支払う国民が悲鳴

観光地が静けさを失っている。京都の祇園では舞妓を追って路地に入り込み、私道を歩き回る外国人観光客が後を絶たないと報道されている。富士山では登山客が夜間に一斉に登り、渋滞のように列をなす。北海道の美瑛では畑の中に立ち入る観光客が増え、農地が荒らされる被害が相次いだ。鎌倉では、日帰り観光の集中によって交通が麻痺する日が多い。これらはいわゆる、オーバーツーリズム問題の一例である。コラムニストの村上ゆかり氏が解説する――。
目次
都市部の交通混雑、地域文化の消耗
国土交通省のデータでは、2024年の訪日外国人旅行者は約3,687万人に達し、過去最高を更新した。観光庁が掲げる2030年目標は6,000万人である。京都市の資料によれば、2024年の入洛客は約5,606万人で、混雑は観光と生活の境界を曖昧にしている。
観光は地域経済を潤す力を持つ。しかし、観光客が地域社会を圧迫するほどに増えれば、それは成長ではなく摩耗になってしまう。観光地の住民は疲弊し、観光客も質の低い体験しか得られなくなり満足度は下がる。観光の数値的な成功が、生活の質の低下を招いてしまう。今後さらに外国人観光客が増えれば、都市部の交通混雑、宿泊施設の逼迫、住居費の上昇、地域文化の消耗などが広がる。
国は2003年に「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を開始した。目的は訪日外国人旅行者1,000万人の達成であった(観光庁公式記録)。2008年には観光庁が設立され、2010年代に入ると予算は100億円を超えた。2014年度の観光庁予算は約104億円、そのうち85億円がインバウンド政策であった(日本観光振興協会年報2015年版)。2023年度には日本政府観光局(JNTO)の訪日マーケティング業務に約66億円が計上され、2025年度には「戦略的訪日プロモーション」に約130億円が配分されている(トラベルボイス報2024年12月27日)。
予算の大半は依然として主要都市に
政府のキャンペーンは世界各地で展開され、「YOKOSO! JAPAN」「Enjoy my Japan」などの広告がテレビやSNSを通じて流された。ターゲットはアジア、欧米豪、東南アジアの主要都市である。
国の広告映像等のPR素材・露出は京都・富士山・東京・大阪など“ゴールデンルート象徴地”に相対的に偏りがちである。観光庁の公式資料でも「ゴールデンルート」を軸としたプロモーションが中心とされている。地方誘客の方針も打ち出されたが、予算の大半は依然として主要都市に使われている。
このままいけば、さらに混みあう
地方は「第二ゴールデンルート」と呼ばれる補完的位置づけにとどまる。つまり国の観光PRは、結果的に特定の都市に観光客を集中させる装置となってきた。富士山も京都も、PRの象徴である。政府が作り出したイメージが、観光客を吸い寄せている可能性は高い。
国の観光PR施策には適正に事前評価やリスクマネジメントがされていないのではないか。観光庁の2023年度の事後評価シート(政策評価書)を見ると、「訪日観光客数」「旅行消費額」を成果指標としているが、「混雑度」「住民満足度」「環境負荷」が考慮された形跡が見当たらず、指標にも入っていない。
国際機関では観光の持続可能性を評価する基準が定められている。UNWTOは「観光の質の管理には、観光地の許容限界と住民の受容度の測定が不可欠」としている。しかし日本では数値目標が優先され、リスクの測定は行われていない可能性が高い。
観光庁が観光PR施策をこのまま強化すれば、京都のようにすでに限界に近い地域にさらに人が流れ込む恐れがある。観光庁は2030年までに「6,000万人・15兆円」を目指すとしており、現時点で外国人旅行者数は約3,686万人、消費額は8兆1,395億円である(観光庁統計2024年版)。観光庁としては目標達成のために訪日客を今の1.6倍、消費額を今の約1.8倍にしなければならない。この増加分がどこに行くかを考えれば、京都・大阪・東京・富士山がさらに混み合うことは明白である。地方に分散する構造がない限り、既存の人気地に集中するのは当然だ。
リスクマネジメントも行わず人を呼び込み続けた結果
観光を呼び込むこと自体が悪いわけではない。問題は、呼び込みの先にある混雑を想定していないことだ。リスクマネジメントも行わず人を呼び込み続ければ当然問題が起きる。こんな当たり前のことも見過ごされているのが、政府の今の観光政策である。
政府は、オーバーツーリズム対策の一環で、2025年から2026年度にかけて、出国税の引き上げを検討している。現在は一人当たり1,000円だが、報道によると3,000円以上に引き上げる案が自民党内で議論されている。2024年度の出国税収は約481億円と過去最高で、現在は観光施設の整備費などに使われており、出国税の引き上げによって得た財源で対策を充実させたい考えだと報じられている。出国税は、飛行機や船で出国する際に一律で徴収されるため、日本人にも外国人にも課されることになる。
政府が煽りすぎたツケを増税で国民が支払う
政府は「訪日外国人旅行者数」や「旅行消費額」を増やすことを目的とし、政府とJNTO(日本政府観光局)は税金を使って海外で日本の宣伝を続けてきた。2025年度には「戦略的な訪日プロモーション」に約130億円が配分されている。しかしそこには観光地の負担をどこまで想定しているのかという説明はない。
自民党PTは、FNNによれば、オーバーツーリズム対策の財源として出国税の引き上げを緊急提言する方針を示した。高市総理は国会で「出国税を3000円に引き上げてでも使いたい」と発言し、政府・国会での最終判断は今後の税制改正議論に委ねられている。だが、その財源が必要になったのは、観光を煽りすぎた政府自身の政策によるものではないか。京都や富士山での混雑、住民の苦情、自然環境の悪化は、政府がオーバーツーリズム問題を軽視したまま観光政策を続けた影響ではないのか。政府の政策によって生まれた問題で、出国税の引き上げという、国民に負担を課すことを検討するというのか。
観光体験の質を下げ、地域の持続可能性を脅かす
観光の本質的な問題は、数の拡大を重ねた結果、観光地そのものが疲弊し、魅力を失うことである。学術研究でも同様の警鐘が鳴らされている。例えば、García-Buades(2022)によれば、社会的キャパシティ超過は住民生活の悪化と観光体験品質の低下を同時にもたらす。また、Capocchi(2019)によれば、管理なき観光拡大は長期的に目的地の持続可能性を損なうとされ、MDPIの総合研究(2019)でも「観光地の収容能力(carrying capacity)を超えた訪問が、観光体験の質を下げ、地域の持続可能性を脅かす」と指摘している。Balliu(2025)では「観光客の過剰集中は、インフラや公共サービスへの負担を高め、住居コスト上昇や地域コミュニティの崩壊をもたらす」と分析している。
これらの研究は、観光を単に「呼び込む」だけの政策が長期的に地域経済を傷つけることを示している。観光地の魅力は人の暮らしと自然の調和によって保たれる。そこが壊れれば、旅行者は離れ、リピーターは減り、やがて観光産業そのものが縮小する。観光の数を増やすことは短期的な利益をもたらすが、質を失えば回復には時間がかかる。こうした現象は経済学で「外部不経済」と呼ばれる。
「外部不経済」とは、ある人や企業が利益を得るために行う活動が、他の人や社会に迷惑や損害を与えるにもかかわらず、その負担を自分では支払っていない状態のことだ。
政府がすべきは増税ではない
例えば、観光客が急増して道路が渋滞したり、ごみや騒音が増えたりしても、そのコストは旅行者ではなく地元住民や自治体が負担している。利益と負担が一致していないから、問題が放置されてしまう。つまり、観光の成長を促す政策が、同時に地域に“見えない損失”を生み出しているのである。
今の日本が抱えているオーバーツーリズムも典型的な外部不経済である。市場の仕組みだけでは、このような負担の不均衡を自動的に是正できない。だからこそ、政府は規制を増やすのではなく、情報と価格を使って外部不経済を見える化し、当事者が負担を分かち合える仕組みを整えるべきだ。
政府がすべきは増税ではない。現在の政府の観光政策そのものをまず検証し、観光庁やJNTOの宣伝費を再配分して、混雑緩和・交通整備・住民支援・環境回復に使うべきではないか。例えば、観光データを公開して地域と民間が自由に利用できるようにし、混雑を可視化して行動を分散させる。ただ禁止させるのではなく、情報と価格の工夫で人の流れを調整する仕組みを検討することも考えられる。それこそが、本質的に観光を持続させる方法であると筆者は考える。
観光政策の推進は、地域の生活が守られ、人々が誇りをもって迎え入れられる社会を築くことが大前提である。ろくにリスクも踏まえないまま、観光を「経済成長の道具」として扱い続けた結果に真摯に向き合い、安易な増税に頼らずに、政策評価による政策の根本的な見直しを政府が着手することを、筆者は強く願っている。