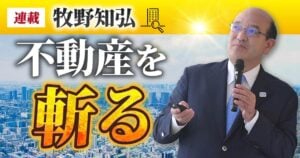“何もない”埼玉が、なぜか「住みたい街ランキング」で躍進を始めた…誇らしげに「浦和住み」をアピールする新人類の登場

『牧野知弘の住んでみるとよい街:浦和・大宮』
今年のリクルート発表「住みたい街ランキング2022 関東」で大いに話題を集めたのが、埼玉県勢のランクアップです。ベスト3の常連は横浜、吉祥寺、恵比寿なのですが、今年は、恵比寿に代わって第3位に大宮が、そして前年8位だった浦和も第5位、46位だった川越が第30位に入るなど躍進が目立ちました。
コロナ禍をきっかけとして、働く人たちの通勤に対する概念が激変していく現代、さてこの埼玉県勢の躍進は何を意味しているのでしょうか。
浦和民は皆「浦和に住んでいます」と胸を張る
浦和に住んでいる知人が数人いるのですが、彼らにどこに住んでいるかと聞くと、みなやや誇らしげに「はい、浦和です!」と答えます。浦和はかつて埼玉県の県庁所在地でしたが、2001年には平成の大合併によってさいたま市となり、現在は浦和区となっています。ところが彼らは「さいたま市に住んでいます」とは決して言わずに「浦和に住んでいます」と言います。東京の人間からすれば、浦和と大宮はあまり大きな違いがないように見えるのですが、浦和在住の方々に聞くと、多くの人が「いや、大宮ではなく浦和です」と胸を張るのです。それだけ浦和という街には人々を惹きつける何かがあるようです。
浦和は江戸時代には中山道の浦和宿として栄えてきました。もともと地域のほとんどが大宮台地上にあり、地盤は安定していて、明治以降は別荘地としても評価の高い地域でした。実はこの浦和に多くの人が押し寄せるようになったのが1923年に発生した関東大震災と言われています。震災以降、東京や横浜方面から多くの人々が難を逃れて浦和の地にやってきたと言われ、この頃から浦和の人口は増加していきます。多くの人が移住してきた理由として挙げたのが、地盤の良さに加え、東京へのアクセスの良さ、下水道整備率の高さ、そして教育環境の充実でした。
特に別所沼近辺はその風光のすばらしさから多くの画家が集結し、神奈川県の鎌倉と並び画家の街と称されるようになりました。
住環境が優れている浦和。これから地価は上がるのか?下がるのか?
さて現代の浦和の住み心地はどうでしょうか。大宮は大規模商業施設などが集積し、住むというよりも買い物、遊びのイメージが強いのですが、浦和駅に降り立つと、大宮とは異なり街全体に漂う気品と余裕を感じます。