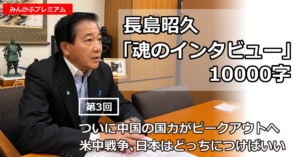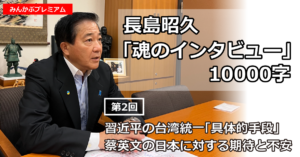「プーチンですら原発を破壊していない」…電力会社にテロ対策を求める非現実な規制委(長島昭久「魂のインタビュー」第1回)

安全保障の専門家として、自民党の保守系中堅議員のなかでもひときわ存在感を放っているのが、長島昭久衆議院議員だ。民主党政権時代には防衛大臣政務官および防衛副大臣として国防の実務を担った実績もある。
ウクライナのロシア侵攻を受けてエネルギー危機が深刻化しているなか、エネルギー安全保障の観点からも、原発再稼働を支持する国民の意見は高まってきている。
読売新聞社と早稲田大学先端社会科学研究所が実施した最新の世論調査では、規制基準を満たした原子力発電所の運転再開については「賛成」58%が「反対」39%を上回り、同じ質問を始めた2017年以降、計5回の調査で初めて賛否が逆転した。
岸田総理も8月24日、「特に、原子力発電所については、再稼働済みの10基の稼働確保に加え、設置許可済みの原発再稼働に向け、国が前面に立ってあらゆる対応を採ってまいります」と発言するなど、積極姿勢を見せている。
原発再稼働の是非について、安全保障の観点から語れる希有な現職政治家である長島氏に、みんかぶ編集部が聞いた――。(全3回の1回目)
目次
「脱原発」のドイツですら、原発再稼働に世論は傾いている
――連日、猛暑となった真夏を何とかやり過ごし、電力需給逼迫(ひっぱく)の危機は去ったかに思えます。
長島 実際は、深刻な状況が続いています。現在進行形で、より深刻化しつつあると言った方が正しいかもしれません。猛暑でエアコンをつけるご家庭が多くなることによる電力逼迫、その一方で節電だと言ってエアコンを消すことで熱中症患者が増える、という意味での〝危機〟は確かに去りましたが、ひと安心というわけにはいきません。
猛暑日というのは当然、晴れているので、太陽光発電の発電量が多くなります。しかし、9月に入ると秋雨前線による長雨や台風の影響によって日照時間が短くなるため、太陽光発電の発電量は減ってしまいます。再生可能エネルギーの最大の問題は、太陽光発電や風力発電などで気候が発電に適している間に発電した電気を貯めておけないことで、天気によって発電量が上下してしまう以上、再エネをベース電源とするわけにはいかず、必ず火力発電のバックアップを必要とします。
しかし、その火力発電も世界的な危機にさらされています。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵攻と、それに対して行われている対ロ経済制裁で、ロシアからの天然ガスなどの購入を止めたために、それ以外の産地の燃料が取り合いとなり、エネルギー価格が高騰。天然ガスや原油をロシアからの輸入に頼ってきた欧州各国はエネルギー政策の転換を迫られています。
特にドイツは、これまで「脱原発」を掲げてきた「緑の党」を含む連立与党が政権を担っているにもかかわらず、原発政策の見直しを国民から突き付けられています。2022年末に運転停止する見込みの原発の稼働を延長しろという声が日に日に高まっているのです。
日本も他人ごとではありません。日本では原発の稼働が全国で5基程度にとどまるなか、本来であれば脱炭素の流れに反する「エコではない」火力発電に頼らざるを得ず、しかも老朽化した火力発電所を無理やり動かして、電力需給を何とかまかなっている状態です。
しかも日本は火力発電の燃料になる天然ガスのほぼすべてを輸入に頼っていますが、そのうちオーストラリアからの輸入は約4割。しかしオーストラリアもロシア発のエネルギー危機で国内の天然ガス・石炭需要を満たせなくなる見通しから、輸出制限を検討し始めています。そうなれば、火力のバックアップ力も低下する中で、いよいよ日本の電力逼迫は抜き差しならない状態に陥ることになります。この危機を回避できるのは、原発の再稼働だけです。
日本国民も原発再稼働を求め始めた
――岸田総理は今年7月14日に「原発9基を再稼働させる」と発表しました。実際は「現在運転中の5基を含め、今後2022年中に既に再稼働が決まっている4基が予定通り稼働される」ことを指しているのであって、さらに追加で再稼働させるわけではないとわかりましたが、これをどう受け止めていらっしゃいますか。