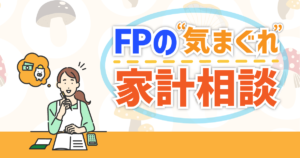第3回 物価高騰ナウ。支出が増えて家計がもう限界なんだけどどうしたらいい?

インフレ時代がやって来ました。電気、ガス、ガソリン代などエネルギー関連の物価が1年前より約20%も上昇し、食品もじわりと値を上げています。
支出の多い世帯では小手先の節約では間に合わず、家計が赤字になってしまうかもしれませんが、かと言って無理な引き締めをしても、すぐ我慢できなくなって長続きしないでしょう。
そこで今回は物価高に対処しつつ、ずっと持続可能な家計管理について学んでみましょう。
目次
家計の見直しは固定費から
支出を抑えるには毎月決まって出ていく固定費の削減が効果的です。
住居費
固定費のうち大きな比重を占めるのが住居費。賃貸なら家賃の安い部屋に住み替えるのも選択肢の一つ。
持ち家のローンが残っていて、かつ手元に余裕資金があるという人は住宅ローンの繰り上げ返済を検討してはいかがしょうか? 繰り上げ返済にはローン返済期間を短縮する方法と月々の返済額を減らす方法があります。金融機関に相談してどちらがよいか比べてみてください。
水道光熱費
電気料金はプランを変更すれば負担が減る場合があります。例えば東京電力では夜の時間帯に多く使う人向けに、夜は割安な電気代が適用されるプランなどがあります。
また電力とガスの自由化により、電力・ガス各社から電気とガスを合わせた料金プランも出されていますし、石油元売り会社の電気に乗り換えるとガソリン代が安くなったり、携帯会社の電気に乗り換えると携帯料金が割り引きされたりして支出を減らすことができます。
さらに年数の経った家電があれば買い替えを検討しましょう。
洗濯機はドラム式のほうが縦型より水の使用量が少なく、節水効果が高くなります。縦型でも節水タイプが出ているので家庭の状況に合わせて選べます。省エネや節水性能が高い最新型は価格も高めですが、長い目で見て価値を判断するのがよいと思います。
これから家の購入を予定しているという人には「省エネ住宅」をお勧めします。電気代を抑えると同時に、節税にもなるからです※。
※2022年度税制改正では、住宅ローン控除について、省エネ性能等の要件を満たした住宅をその他の住宅よりも優遇しています。これは国の「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた施策のひとつです。家のリフォームする場合も、自治体によっては省エネ基準を満たすと補助金が出る制度があります。
保険
複数の生命保険、損害保険、共済に加入している場合、保障内容が重複していることがあります。見直すときは家族分もまとめて見直しし、重複がないか確認するといいでしょう。
生命保険は年月の経過や家族構成の変化などにより必要な保障が変わってくるので、保険金額は適正か、特約は必要十分か、など定期的な見直しが必要です。
自動車保険はネット保険に変えることはもちろんですが、ほかにも年齢や運転者を限定したり車種を変更したりすると保険料が安くなります。
ローン・クレジット
クレジットカードのリボ払いやカードローンは利息が高めです。安易に利用しない、欲しいものは貯めてから買う、などのルールを守るようにしてください。
やみくもに節約するより「予算」を立てる
これまで経験したことのない物価高ですが、家計管理の基本は変わりません。優先項目を決めて収入の範囲内で生活できるように予算を立てましょう。
食費
食費は健康の基本なので、節約よりも中身が大事。物価上昇のせいで主食や生鮮食品の購入費が増えるのはやむを得ないと考えてください。