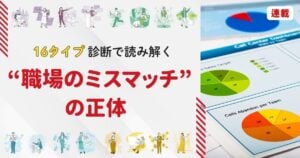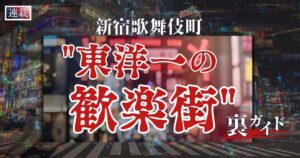【追悼】稲盛和夫「人生成功の方程式」この苦しみが、一流と二流を分ける

京セラの稲盛和夫名誉会長が24日に老衰のため亡くなりました。心よりご冥福をお祈りします。みんかぶマガジンで大変多く読まれた稲盛さまに関する記事を再度お届けしますーー。(初公開日:2022年7月18日)
観測史上最速の梅雨明け、東京都心で連続猛暑日を記録、各地での史上最高気温更新・・・。
うだるような暑さに気力と体力を奪われ、夏期休暇を前にすっかりやる気を削がれてしまっている人も少なくないだろう。コロナ禍で我慢してきた旅行やレジャーへのカウントダウンを頼りに、自らを奮い立たせようとするサラリーマン諸兄の姿が思い浮かぶ。こんな時、人々の「栄養剤」となるのはいつの世も、偉人たちの言葉だ。大成功の陰に隠された失敗から学び、心身ともに豊かな人生を歩む成功者のメッセージは胸に響く。今回のテーマは、超一流に学ぶ「くじけない働き方」だ。
コロナの前後でサラリーマンのメンタルはどう変わったか?
2020年初めから世界に広がった新型コロナウイルス。感染拡大を機に急増したのは、テレワークである。満員電車に揺られ、ヘトヘトになりながら出社と帰宅を繰り返したサラリーマンの働き方は、「未知のウイルス」によって一変することになった。
2年半たった今でも、夏にかけての感染再拡大をにらみ、在宅勤務を引き続き推奨する企業も多い。東京商工リサーチの調査によれば、2020年4月に緊急事態宣言が発令される直前のテレワーク実施率は17.6%だったものの、約2カ月後には56.4%に上昇した。東京都内の実施率は2022年3月でも62.5%と高い。
各種調査によると、在宅勤務を経験した従業員の満足度は高いものの、それと並行するように増加したのがメンタルヘルス不調だ。「テレワークでは上司や部下とのコミュニケーションが取りづらい」「仕事と家庭の垣根がなくなり、ストレスを強く感じるようになった」などの相談が相次ぐ。中には「自分が働くことの意味がわからなくなってきた」との声も寄せられる。
コロナ前でも、ストレスフルな生活に悩む人は多く、厚生労働省の労働安全衛生調査(2018年)によれば、仕事や職業生活に強い不安や悩み、ストレスがあると回答した人は58.0%に上っていた。過度なストレスを抱え、メンタル不調を抱える人は増加傾向で、就職後3年以内に退職する新入社員は大卒者で約3割、高卒者では4割近くに達していたというのが実情だった。
ストレスから解放されたと思ったら、新たな悩みが‥
翻って現在。汗だくになった通勤ラッシュから解放され、慌ただしかった日々が嘘のように感じる在宅勤務。自宅での時間は増え、職場でのストレスから解放された、はずだった。だが、その反面、こうした「凪」状態に改めて人生を振り返るという人が増えているという。時間に余裕ができた副作用といえるのだろうか、スマホを片手にSNSや動画配信サービスを利用しながら、出世の階段をのぼる同僚や、起業から「FIRE」を達成した友人の動向が気になり、ジェラシーを感じてしまう、という声も聞かれる。
「自分だけがブラックな環境で働いているのではないか」「いっそ、転職でもしようかな」「そもそもなぜ、俺はこんなところで働いているんだ」。職場の密な人間関係に時間と心を縛られていた頃には考える余裕がなかった、こんな自答をつい、繰り返してしまう、という人も増えているようだ。
なぜ人は働くのか―。この根本的な問いに説き明かしてくれるのは、京セラ創業者で「経営の神様」と呼ばれる稲盛和夫氏である。NTTドコモやソフトバンクとともに「3大携帯キャリア」の一角を占めるKDDIを創業し、80歳を前に政府の要請で日本航空に会長として乗り込んだ稲盛氏は、経営破綻したJALを再建に導いた「超一流」として知られる。経営哲学やリーダーシップの本質を数々の著書で披露しており、説得力のある言葉の一つひとつはいずれも、今を生きるサラリーマンに刺さるものだ。
才能よりも情熱が重要‥君は経営の神様の言葉を信じるか?
では「人はなぜ働くのか」という質問に、稲盛氏はどのように答えるのだろうか。それは「神様」が著した『生き方』(サンマーク出版)に詰まっている。
『一般によく見受けられる考え方は、労働とは生活するための糧、報酬を得るための手段であり、なるべく労働時間は短く給料は多くもらい、あとは自分の趣味や余暇に生きる。それが豊かな人生だというものです。そのような人生観をもっている人のなかには、労働をあたかも必要悪のように訴える人もいます。しかし働くということは人間にとって、もっと深遠かつ崇高で、大きな価値と意味をもった行為です。労働には、欲望に打ち勝ち、心を磨き、人間性をつくっていくという効果がある。単に生きる糧を得るという目的だけではなく、そのような副次的な機能があるのです』
たしかに社会生活を送る人間は、労働によって対価を得ること自体が目的になりがちだ。米国の心理学者であるアブラハム・マズロー氏は、人間の欲求を①生理的欲求②安全の欲求③社会的欲求④承認の欲求⑤自己実現欲求―と5段階で説明したが、稲盛氏の言葉はそこに「副次的な機能」をもたせる。労働は単に経済的価値のみならず、人間の価値を高めるものであると喝破しているのだ。
稲盛氏は若者へのメッセージも忘れない。著書『成功への情熱―PASSION―』(PHP文庫)では、このように説いている。