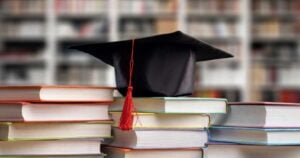中学受験、最強塾はサピックスか、グノーブルか、それとも…四谷・日能研を終わらせた常勝軍団抱える2つのリスク
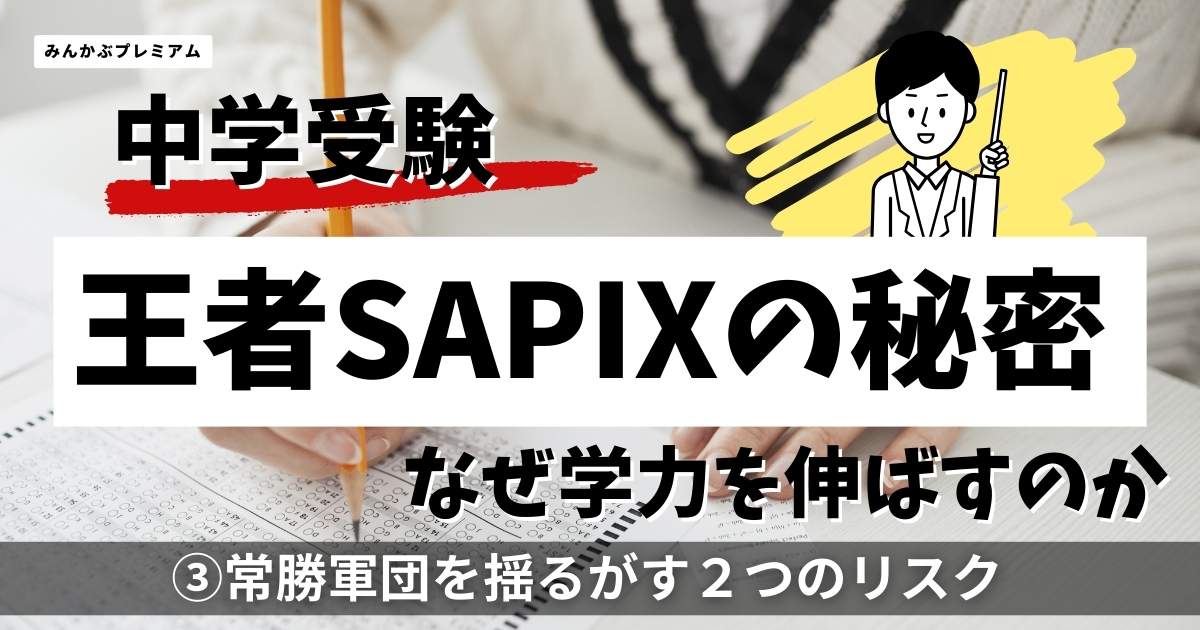
開成や桜蔭といった最難関校、その合格者の7〜8割がサピックス生だ。中学受験ではこの状況が、もはや「当たり前」のように受け止められている。
しかし、冷静に考えてみると、高校受験や大学受験では、特定の塾がここまでトップ校の合格者シェアを独占することはない。東大や京大の合格者数のうち、大手予備校の東進や駿台、河合塾などの占める割合は全体のそれぞれ2〜3割程度に過ぎず、当然塾なし合格者も存在する。
なぜ、中学受験だけは、サピックスの圧倒的一強体制が続いているのか?
今や、多くの家庭がサピックスを選び、それが「受験の王道」となっている。気づけばなんとなくサピックスに通わせる家庭も少なくない。
さぞかし、教師や教材の質が高いのかと思いきや、プロの目から見ると決してそんなことはないという。
「サピックスの教材や講師の質は『普通』です。プロから見れば特別にクオリティが高いわけではない。サピックスの強さの秘訣は、それとは全く違うところにあるんです」と、進学塾VAMOS代表の富永雄輔氏は語る。
なぜサピックスだけが勝ち続けるのか?その強さを生かせる家庭と、そうでない家庭の違いとは?今回の連載では、その疑問について掘り下げていく。全3回の第3回ーー。
目次
いかにして四谷・日能研時代を終わらせたか
2025年、サピックスの36期生が卒業します。近年、サピックスは1学年あたり約6000人の生徒を抱え、一大教育機関と化しています。
ここ数年、中学受験生の親御さんたちの中にサピックスOB・OGが目立つようになってきました。彼らは自分自身が中学受験をし、その成功体験・あるいはリベンジ意識を持って、子供をまたサピックスに通わせています。
親世代が中学受験をした約30年前、サピックスはまだそこまで目立たない塾で、四谷大塚や日能研が圧倒的に主流でした。
当時は「親子で教材を予習してから授業を受ける」というスタイルの塾が一般的でした。当時はまだまだ専業主婦が多く、中学受験ともなれば子供の学習につきっきりという家庭も多かったのです。
しかし、共働き家庭が増加し、多くの親は予習に手を回す余裕がなくなります。そこでサピックスの「授業の予習は不要。授業でわからなかったこと、理解を深めたい点を家庭で復習してほしい」という教育方針が広く親に受け入れられたのです。
教育業界の一大事件、SAPIX分裂騒動
当時のサピックスは、講師が生徒のレベルに合わせて課題を出したり、苦手な部分をフォローしたりと個別対応が手厚く、面倒見の良い塾として人気を集めました。多くの親御さんが体験したのは、この頃のサピックスでしょう。
その後、サピックスは大手予備校の代々木ゼミナールに買収されます。校舎数を拡大するにあたり、どこでも均一なサービスが提供できるようにマニュアルが整備され、講師の個別対応などは徐々に減っていきました。
この方針に納得できなかった講師たちが独立し、設立したのがグノーブル小学部です。独立時には校舎長、志望校対策クラス責任者などが多数参加したことで、教育関係者からは驚きの声が上がりました。
御三家第一主義の崩壊が始まった
これまでの中学受験では、学校の序列が御三家を頂点とするピラミッド型の序列がありました。そこに対して、サピックスは「御三家に進学するための塾」として圧倒的なブランドを築いてきました。
しかし現在は、親や子どもの志望校に対するニーズが多様化し、偏差値や学校の知名度よりも、我が子にとっての魅力を重視する家庭が増えているのです。