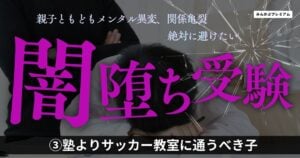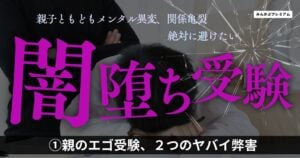中学受験で子どもにいら立ってしまうのは「親のコンプレックス」の問題…兄弟間の衝突を生んだ母の無知
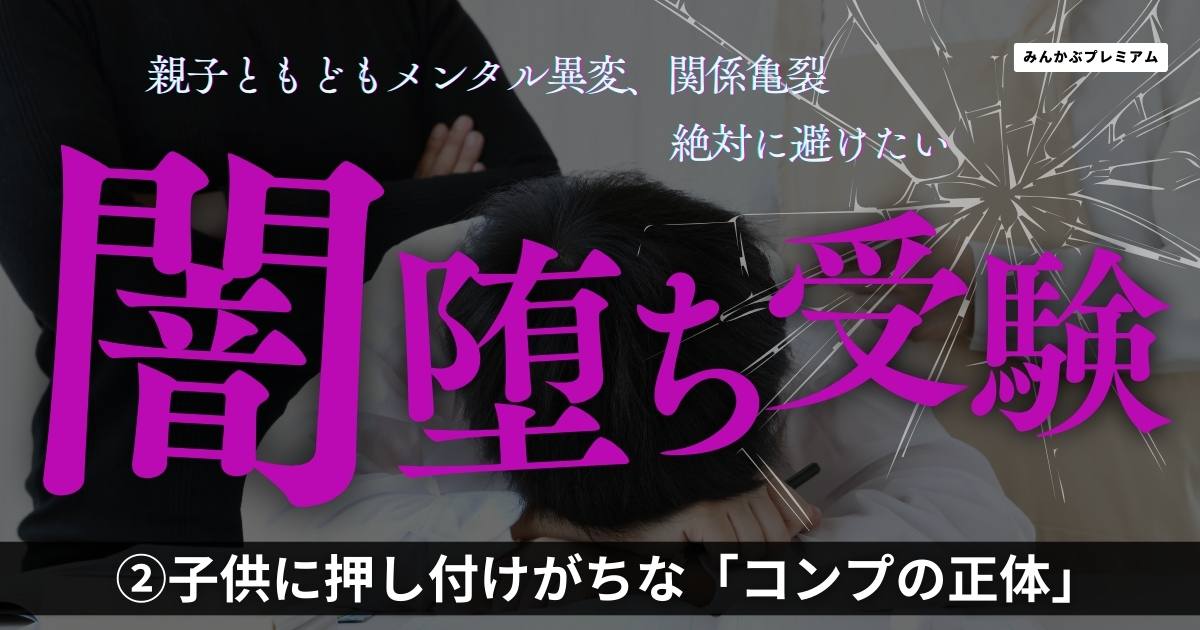
ここ数年、高まり続ける中学受験の熱。
以前に比べ、中学受験に関する報道や話題を目にする機会が格段に増えた。受験人口の増加に伴い、受験生本人やその親に対するプレッシャーも高まっている。
「受験生とはいえ、まだ生まれて10年程度の小学生に過ぎません。過度なストレスに晒されれば、家庭環境の悪化、集中力の低下、モチベーションの低下という形で返ってきます」
そう語るのは学習塾伸学会代表の菊池洋匡さんだ。
「ストレスを過度に受けている子供は、途中で必ずサインを出しています。しかし、受験で失敗する家庭の多くは、それに気づかない。あるいは見て見ぬふりをします。『無理をさせても6年生2月の受験本番まで乗り切ればいい』というのは典型的な失敗パターンです」
世の中には受験の成功談に溢れているが、むしろ学ぶべきは失敗談だと菊池さん。
「成功談には典型的な“生存者バイアス”がかかっています。上手く行った人のエピソードに過ぎず、再現性がありません。失敗談を学べば、同じ轍を踏まないようにすることができるので、メリットが大きい。特にメンタルの面で言うと、受験生家庭の多くが同じような失敗をしています」
今回は「失敗しない」に焦点を当てて、子供の能力を最大化させる学習法を聞いた。短期集中連載全3回に第2回目ーー。
目次
子供に押し付けがちな「コンプの正体」
親は子供に愛情があるあまり、「こうあってほしい」「こうあるべきだ」という思い込みを持ちがちです。そのこと自体が悪いとは思いません。
しかし、その理想像が親自身のプライドやコンプレックスに由来するものだと、子供を深く傷付ける言動に繋がりやすくなります。
「これくらいの偏差値の学校に行かないと、意味がないよ」
「親は勉強好きななのに、なぜあなたは頑張れないの」
「もっと頑張らないと、あの子に負けちゃうよ」
こうしたつい言ってしまいがちな一言の裏には、「理想的な子になってくれないと、親のプライドが満たされない」という思いがあります。子供からすれば、知ったことではないでしょう。
期待や苛立ちが生まれてしまうのは、親の内面の問題
確かに受験勉強を頑張るのは子供です。しかし、期待や苛立ちが生まれてしまうのは、親の内面の問題です。
「自分の中学受験で悔しい思いをした」
「家が貧しくて、受験できなかった」
「子供が勉強できないと周囲に思われるのが恥ずかしい」
そんな自分のコンプレックスが、傷付けるような言動や無理な勉強に繋がっていないか、慎重に確認すべきです。
教育は生育過程の価値観が問われます。プライドやコンプレックスなど、心の深い部分に根ざした価値観が刺激されるのは無理もありません。
普段は良い親として理性的に行動していても、ちょっと刺激されると無意識に過度な言い方をしたり、いうべきでない一言にストップがかからないということが起きてしまいます。
弟の子育てに影響を与えていた子ども時代の原体験
子供時代に与えられた「心の宿題」は、育児や教育に大きな影響を与えます。
身内の話で恐縮ですが、私の弟が子どもに対して「成果主義」な関わり方をしていました。しかし、未熟な子どもにとって、成果を出すための努力をすること以前に、どうすれば成果が出せるかを考えること自体困難なことです。