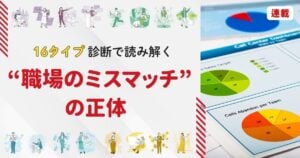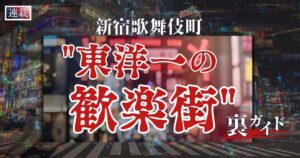なぜ「この株はあのとき売っておくべきだった」と後悔してしまうのか?行動経済学が明らかにする人間の心の仕組み

仕事場に株式投資、スポーツ観戦など、日常のさまざまなシーンでよく耳にする「やっぱりそうなると思っていた」。しかし行動経済学コンサルタントの橋本之克氏によれば、その感情も実は“後付け”なのだという。私たちはこの厄介な感情とどう向き合うべきなのか、橋本氏が解説する。全3回中の2回目。
※本稿は橋本之克著『世界は行動経済学でできている』(アスコム)から抜粋、再構成したものです。
第1回:「ディズニーの待ち時間」「通販番組」に学ぶ、周りの人間への嫉妬心を抑える方法
第3回:「150ドルもらえても、100ドル支払うほうがイヤ」……人はどうしても“不合理な判断”をしてしまう
目次
「前からわかっていた」は本当か?
同僚が仕事でミスをしたとき、「あの人はいつかトラブルを起こすと思ってたんだよ」と言ってしまう、株式投資で失敗したあとに「やっぱり、あのときに売っておけば良かった」などと言いたくなる。
みなさんも、さまざまな場面で「こうなることはわかっていた」と言いたくなった、言ってしまったことがあるのではないかと思います。ですが、本当に最初から「わかっていた」のでしょうか?それは正しい記憶でしょうか?
私たちはしばしば、最初からわかっていたと思い込んでしまうことがあります。この傾向を行動経済学では、「後知恵バイアス」と呼んでいます。
何かが起きたあとで、または結果を知ってから、事前にそれを予見していたかのように思い、そんな自分の考えが正しいと考えるのです。
あとから知った結果をもとに、結果を知る以前の自分の記憶を「以前から知っていた」と無意識に書き換えるわけですね。そうして自分の誤りを、棚上げします。
そうすれば、あるべき姿(正しい判断を下せる自分)と実態の矛盾による不快感やストレス、即ち「認知的不協和」を感じることもありません。