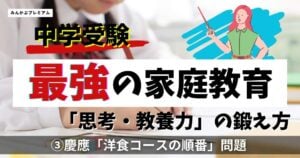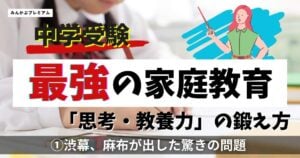海城中が受験生に投げた「課外活動評価の是非」問題…中受入試が大変化!トップ校が「家族」を大切にするワケ
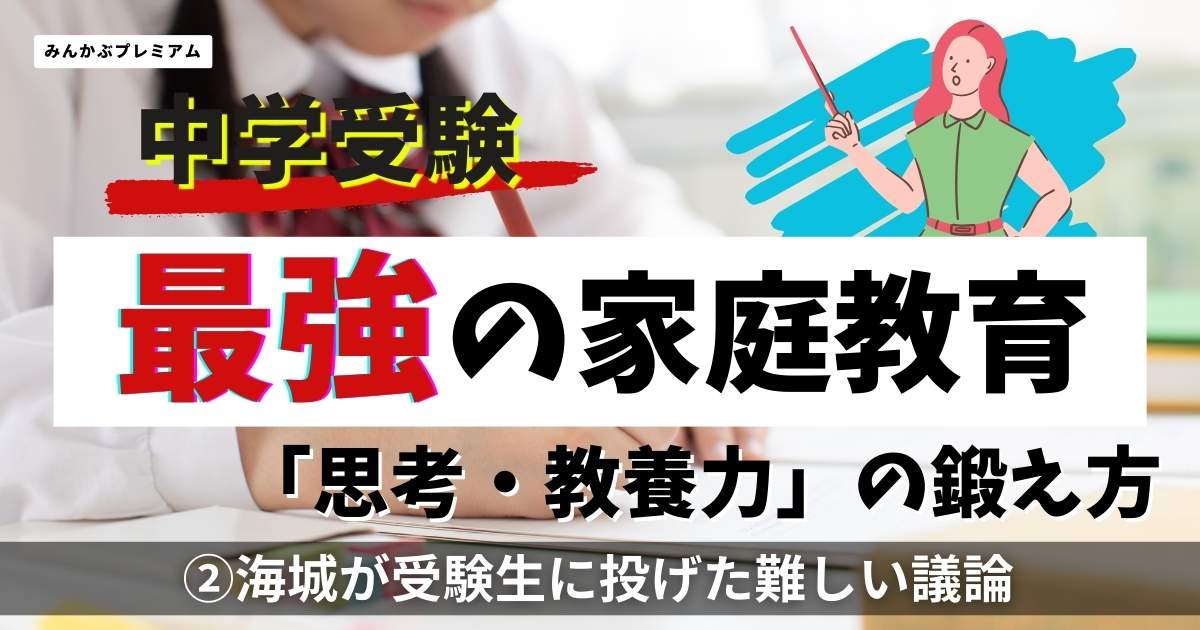
「中学受験は知識を詰め込んだ者が勝つ」。そのイメージはもはや古いものになろうとしている。トップ校の出題傾向が変わり、知識・パターン問題偏重の入試から、深い思考力や高い教養力を含めた「知の総合力」を問う入試にシフトしつつあるのだ。
中学受験の入試問題を長年研究している中学受験専門塾「 ジーニアス」の松本亘正代表は、トップ校入試の中で問われる能力が「質的」に変わってきたと断言する。
問われるのは、与えられた情報をもとにその場で考える思考力や幅広い教養・知識です」。トップ校が求める「質的」な変化の背景には何があるのか。そして、対策はいかに進めていけば良いのか。「ジーニアス」の松本氏に問題分析と解説を聞いた。全3回の第2回ーー。
目次
入試問題を変えた2つの要因
中学受験において、思考力や幅広い教養が問われるようになった背景には、2つの要因があります。1つ目の要因は大学入試の変化です。
2021年からセンター試験に代わり、大学入学共通テストがスタートしました。共通テストでは各教科で問題文が長文化し、データや資料の読み取りを求める問題が格段に増えました。
かつては、単なる「暗記科目」と見られていた社会でも、こうした流れは顕著です。
国公立大学の二次試験や私立大学の個別入試でも、資料考察・推論を求める問題は増えています。AIやIT技術の進歩によって、入試全体が暗記よりも思考や考察を求める傾向になりつつあると言えるでしょう。
また、昨今は大学定員に占める「総合型選抜」(旧AO入試)の割合が、年々増加傾向です。東大・京大をはじめとする旧帝大や早慶などでも、入学枠が広がっています。
総合型選抜の場合、中高時代に取り組んだ課外活動や社会問題・研究テーマへの考察力、理解力が問われます。学校側は「探究」の授業などを通じて、6年間かけてこうした力を育てていくのです。
大学受験は「一般入試」でも、「総合型選抜」でも、従来型の記憶力やテキストへの理解力だけでは対応しづらくなりつつあります。こうした変化を受けて、中学受験の出題傾向が変わりつつあるのです。