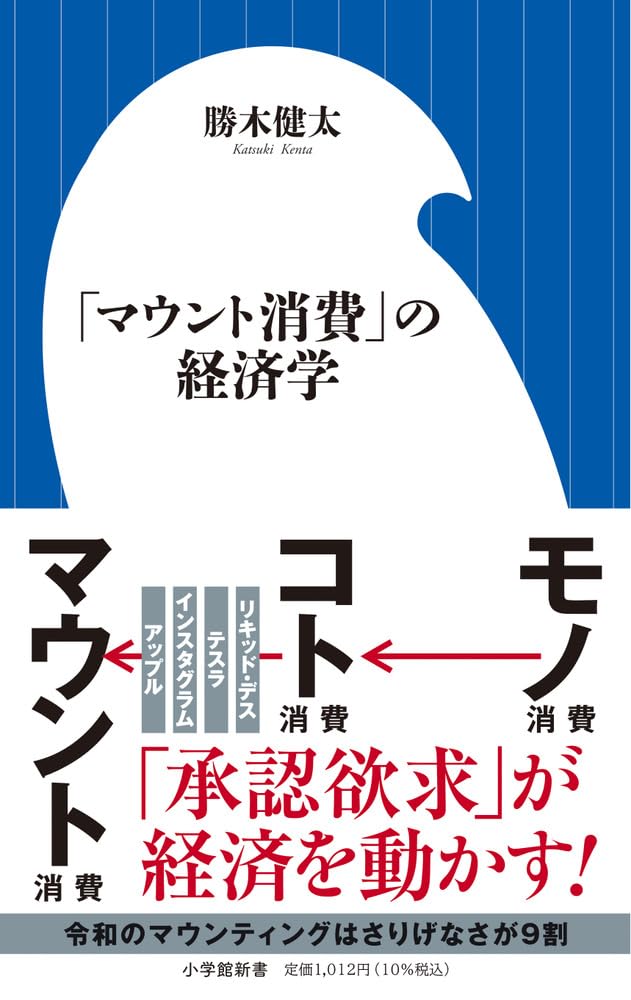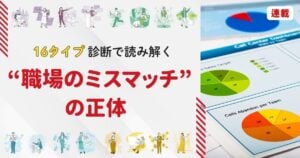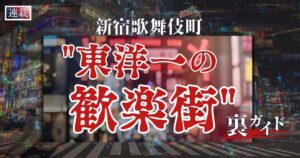令和のマウントは「さりげなさ」が9割!「Clubhouse」が失速した理由

人類は自分の優位性を示す「マウント」から逃れられない。一方で文筆家の勝木健太氏は、令和のマウントでは「自虐」や「困りごと」を添えてマウントを行う傾向が強まっているという。マウント事情の最前線について、勝木氏が解説する。全3回中の2回目。
※本稿は勝木健太著「『マウント消費』の経済学」(小学館新書)から抜粋、再構成したものです。
第1回:令和の経済を動かすのは“承認欲求”!世の中はモノ消費→コト消費→マウント消費へ
第3回:なぜサピックスは選ばれ、最強であり続けるのか…その答えは「マウント欲求」にあった
目次
中高年男性のマウント欲求を満たす銀座の会員制クラブ
銀座の会員制クラブは、接待や飲食の場としてだけでなく、中高年男性たちの「特別な存在でありたい」という「マウント欲求」を満たすための緻密に設計された舞台である。この空間において、高額な会員費やボトル代は「自分は上位のステータスを持つ特別な存在だ」という自己演出の手段として、極めて重要な役割を果たしている。
クラブの扉を開け、「一見さんお断り」という希少性に包まれた空間へ足を踏み入れる瞬間から特別な体験が幕を開ける。眩いシャンデリアが照らす豪奢な店内、ホステスの温かな笑顔、「お待ちしておりました」と迎えられる特別な席。その一連の流れは、顧客に「自分はこの場にふさわしい人間だ」と力強く認識させ、同時に社会的ステータスを再確認させる巧妙な仕掛けとして機能する。
この空間で過ごす時間は、高級な酒を楽しむためだけのものではない。「特別な自分」であることを実感し、その存在をさりげなく周囲に対して示す体験こそがこうした会員制クラブの真髄であり、何ものにも代えがたい魅力なのである。
この体験を支えているのは、綿密に練り上げられた空間演出と接客の妙である。たとえば、ホステスが「先日のビジネスの件、うまくいかれたようですね」と語りかける一言。それは世間話というより、「あなたは特別な存在ですよ」と暗に伝えるための気の利いた演出だ。このさりげない会話は、顧客が自身の存在意義やステータスを再確認するための重要な儀式であり、ホスピタリティを得ると同時に「自己肯定の場」としての役割を完璧に果たしている。
「一見さんお断り」が生み出す特別感
特に洗練された会員制クラブでは、それとなく「特別感」を演出するための機会が巧妙に設計されている。著名な常連客や有名人との自然な接点が用意されていることがその好例だ。隣の席に座る名うての経営者や芸能人が「お久しぶりです」と声をかけてくるだけで、顧客は「特別な人脈を持つ自分」を実感し、誇りに満ちた気分になる。こうした瞬間は、クラブ側が提供する「見えない演出」の極致であり、計算し尽くされた仕掛けが特別感を生み出すための隠れた原動力となっている。
これらのすべてを支える基盤が「一見さんお断り」という希少性である。限られた者だけが足を踏み入れることを許された空間であることが、このクラブの価値をより一層際立たせている。「選ばれた者だけが訪れる特別な場所」というプレミアム感は顧客のステータス欲求を刺激し、他では得られない満足感を引き出している。この空間では「選ばれた者である」という事実が大きな意味を持ち、顧客にとって一種の自己肯定感を高めるための象徴的な体験となっているのである。
銀座の会員制クラブは、「特別な自分」を実感し、さりげなく周囲にアピールするために巧妙に設計された舞台である。ここでは、時間、空間、すべての演出が絶妙に調和し、顧客の「特別感」を最大限に引き出すように作られている。この洗練された体験こそが、顧客に他では得られない唯一無二の価値を提供しているのである。
令和のマウントは9割が「さりげない」
一方で、「マウント」のスタイルは時代の流れとともに大きく変化し、社会の空気を反映する鏡のような役割を果たしている。かつて主流だった「あの人より自分の方がすごい」「自分にはこんなことができる」といった露骨な自慢は、もはや時代遅れとなりつつある。SNSが日常生活に深く浸透した現代では、あからさまな優越感のアピールはむしろ反感を招きやすく、場合によっては炎上のリスクが伴う。
しかし、「他者と比較して自分の価値を確かめたい」という人間の根源的な欲求が消え去ることは決してない。それどころか、この欲求は時代の洗練を受けた結果、より巧妙かつスタイリッシュな形で表現されるようになっている。これこそが令和の時代における「さりげなく自分を際立たせる」という新たなマウントのあり方なのである。
その極意は、直接的な自慢を避けながらも相手に対して自身の価値を自然に感じさせる点にある。たとえば、高級レストランでのディナーを投稿する際には「子供がどうしても食べたいと言うので仕方なく」といったコメントを添える。この「子供」という要素は巧妙なカモフラージュとして機能する。一見すると家族思いで謙虚な姿勢に見えるが、その背後には、経済力や洗練されたライフスタイルをそれとなく見せつける意図が潜んでいる。写真を目にした人々は、無意識のうちに漂う特別感を感じ取り、投稿者のセンスやステータスを自然に認識する。この絶妙なバランス感覚こそが、さりげないマウントの真髄なのである。
旅行の投稿も同様である。「家族でリフレッシュできました」という控えめな一言とともに、高級リゾートのプールや青い海を背景にした写真が添えられる。この投稿には「私の生活は充実している」とは一言も書かれていないが、それでも写真そのものがそのメッセージを雄弁に物語っている。このような事例は一見すると自然体を装いながらも、実際には緻密に計算された「自己表現のアート」とも言える産物だ。巧みに織り込まれた謙虚さと洗練された演出によって特別感が静かに伝わり、投稿者のライフスタイルやセンスを際立たせる。この絶妙な手法こそが、現代における洗練された自己表現の形態なのである。
この新時代のマウントスタイルの背景には、「自慢したいけれど嫌われたくない」という現代人の矛盾した心理がある。露骨なマウントが敬遠される一方で、さりげないマウントはそのリスクを回避しつつ、謙虚さと自己顕示を絶妙に両立させる手法として機能している。この高度なスキルは、「マウントIQ」とでも呼ぶべき現代的な社会知性の一つとして捉えられる。見る人に不快感を与えず、上品に自分の価値をアピールするこの技術は、情報が溢れる現代社会において、ますます大切な要素となっている。
特別すぎても平凡すぎても駄目
SNSの成功例と失敗例は、「さりげなさ」の重要性を如実に示している。かつて一世を風靡した音声SNSの「Clubhouse」は、「特別な空間」を過剰に演出しすぎたせいで、「自分は特別だ」と強調する態度が反感を招き、急速に失速した。
一方で、フランス発のSNSの「BeReal」は自然体を追求しすぎた結果、特別感に欠け、広範な支持を得るには至っていない。これらの事例は、露骨さと平凡さの間にある絶妙なバランスこそが、令和時代のマウント成功の分水嶺であることを示している。
近年、さりげないマウントの手法はさらに高度化している。「自虐マウント」では、「仕事が忙しくて疲れた。でも、この景色には癒される」と疲労感を装いながらも高級スパや絶景を上手い具合にアピールする。「感謝マウント」では「家族が素敵なディナーを準備してくれました。本当に感謝」と謙虚さを見せつつ、高級レストランの洗練されたテーブルセッティングをそれとなく映し出す。そして「困ったマウント」では、「急な誘いでこんなところに来てしまいました」と困惑を装いながらも、高級ホテルのスイートルームを何気なく披露する。このような手法は、直接的な自慢を避けつつも特別感を巧みに伝える、極めて洗練された自己表現の技術と言える。
さりげないマウントは、「匂わせ」の究極形とも言える。優越感を背後に隠しながらも確実に伝え、背景に「子供」「趣味」「偶然」といったストーリー性をちりばめることで、スマートで控えめな印象を演出するのだ。この「さりげなさ」が現代のSNSにおいて、多くの共感を引き出すための秘訣である。
露骨さが目立った「Clubhouse」も、平凡さに終始した「BeReal」も時代の波に飲まれた今、何気なく特別感を演出するための技術がこれからは求められる。このスキルを身につけた者こそが、令和のマウントゲームを制し、SNSという舞台で輝きを放つ真の勝者となるのである。