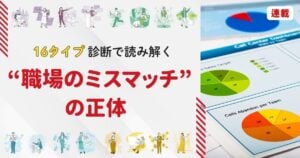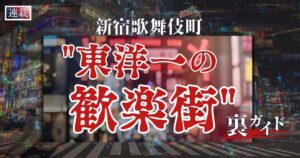「推薦入試の面接は陽キャが有利」は嘘!“面接なしの推薦”でも早稲田・慶應に行ける道がある

「大学の推薦入試」と効くと、「面接に得意な陽キャが選ばれがちだ」と考える人も少なくないだろう。だが受験ジャーナリストの杉浦由美子氏は、「大学の教授陣が陽キャ気取りの受験生に共感するかは疑問」と指摘する。昨今の面接事情を杉浦氏が紹介する。全3回中の1回目。
※本稿は杉浦由美子著「大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法」(青春出版社)から抜粋・再構成したものです。
第2回:“おだやかな面接”と“厳しい面接”をわけるのは「志望理由書」……AIが書いてもプロが書いても一目でバレる
第3回:偏差値40台で上智大も!「偏差値58未満」であれば推薦入試を検討すべし
目次
「面接はプレゼン能力が高い人が有利」の誤解
「どうして推薦入試を受験したんですか?」と総合型選抜で難関大学に合格した学生に訊くと、こう返ってきました。
「母が『おまえは人見知りしないし、話をするのが得意だから総合型選抜に向いているんじゃないの』と薦めてきたんです」
お母さまは今でも「うちの子は明るくて話すのが得意だから総合型選抜で大学に合格した」と信じているかもしれませんが、それは勘違いされています。
「総合型選抜や公募制は面接重視なのでプレゼン能力が高い生徒が合格していく」という誤解を塾や高校もしていることが非常に多いです。
ある大手塾の講師もいいました。
「真面目すぎる子は総合型選抜や公募制には合いません。コミュニケーション能力が高くて、明るい性格の子に向いています」
私も最初はそう思っていました。私はテレビのコメンテーターとなんどか食事をしましたが、彼らはとにかく話し方がうまく、プレゼン能力が高いのです。ある女性のコメンテーターは、会社員時代にアシスタント的な立場で関わったプロジェクトを「私が中心になって成功させた」と堂々と話していました。その会社とつき合いがあって、事情を知っている私がいるのにですよ。