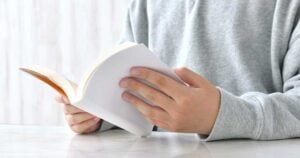「ドラゴン桜」監修・西岡壱誠氏、国語力を爆上げする「読みやすい本」を選ぶ方法

わが子に「読書を通じて自ら情報を獲得できるようになってほしい。心豊かな人格に育ってほしい」。それは多くの親が考えていることだろう。
しかし、その思いとは裏腹に、多くの親が誤ったアプローチをしていると株式会社カルペディエム代表取締役で、漫画「ドラゴン桜2」編集担当としても知られる西岡壱誠氏は語る。
「読書に対する考え方・感じ方、文字情報に対する認識の仕方、興味関心の持ち方は親子といえども異なります。わが子の特性を把握し、その子に合った読書スタイルを見つけてやることが親の役目です」
では、わが子を「読書好き」にするには、どのようなアプローチがあるのか。西岡氏に具体的な方法を伺った。連載全2回の第1回。
目次
ストーリーラインを掴んでから「読書に入る」
多くの子供が読書でつまずくのは、ストーリーや登場人物の把握に苦労するからです。読書への入り口のハードルを下げる工夫をすることで、子供は本により親しみやすくなります。
そこでハードルを下げるために役に立つアプローチが、おおよそのストーリーラインを掴んでから読書に入るという方法です。
映画版や漫画版であらすじを掴んでから原作を読むのも良いですし、文庫本の裏表紙に書いてある解説などに目を通すのも良いでしょう。
ハリーポッターのようなシリーズものもおすすめです。主な登場人物は次回作にも引き継がれますし、作品の舞台や主人公の目標も大きくは変わりません。そのため、1作目さえ読めて仕舞えば、その先を読むハードルがすごく低くなります。
シリーズものは「次も読んでみよう」というモチベーションにもつながりやすいので、読書の習慣化にはもってこいです。
「このシリーズは10作品あるよ」と最初に伝えると、子供も尻込みしてしまうので、初めは1巻だけ渡して「面白かった」と言われてから「続きもあるよ」と伝える方が良いでしょう。