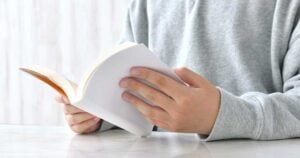国語力が身につかない・・・「ドラゴン桜」監修・西岡壱誠氏が教える「わが子を読書好きにする」方法

わが子に「読書を通じて自ら情報を獲得できるようになってほしい。心豊かな人格に育ってほしい」。それは多くの親が考えていることだろう。
しかし、その思いとは裏腹に、多くの親が誤ったアプローチをしていると株式会社カルペディエム代表取締役で、漫画「ドラゴン桜2」編集担当としても知られる西岡壱誠氏は語る。
「読書に対する考え方・感じ方、文字情報に対する認識の仕方、興味関心の持ち方は親子といえども異なります。わが子の特性を把握し、その子に合った読書スタイルを見つけてやることが親の役目です」
では、わが子を「読書好き」にするには、どのようなアプローチがあるのか。西岡氏に具体的な方法を伺った。連載全2回の第2回。
目次
思考力につながる読書体験の作り方
親御さんの中には、読書はしているのに「国語力」が伸びない、「思考力」に繋がらないと心配している方も多いかもしれません。本を読んでも思考力や国語力が身につかない子の特徴は明確です。
基礎となる「語彙力」か、文章の「要約力」のどちらかが欠けているのです。
東大の入試問題と他の大学の入試問題では、解答欄の大きさが違います。仮に「フランス革命について説明しなさい」という問題があった際に、他の大学が100文字以上の解答欄を受験生に与えるのに対し、東大は「フランス革命について30字で説明しなさい」とかなり制限した文字数での解答を求めます。
東大受験生であれば、レポート用紙何枚にもわたって説明できるのは、承知の上で「細かい説明はいいから、一言で説明しなさい」と本質的な部分を要約する力を求めるわけです。
要約力は文章を理解し、その核心部分を見抜く能力であり、これがないと読書量が多くても思考力の向上には繋がりません。読んでいる内容を自分の言葉で整理できないということは、結局何も理解していないのと同じなのです。
そこで親が「今読んでいる本はどういう話なの?」と聞くことが重要です。
大抵の子は「なんかこうでこうで、こんな人が出てきてこうでこうで」と長々とあらすじを説明しますが、大人の感覚では何を言っているのか全然わかりません。そこを「要するに、ハリーが魔法学校に行って活躍する話だよ」といった程度でもいいので、短い言葉で説明させることです。
短く伝えるという作業は、子供同士のコミュニケーションにはあまりありません。日々の親子の会話の中で簡潔に説明する力を鍛えてやってください。そこから情報を整理し、まとめる思考力が育ってくるはずです。