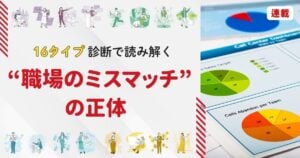名門校でも危険!9浪した教育インフルエンサーが警鐘を鳴らす「受験に失敗する子」のメカニズム

「わが子が名門私立中高に合格した。これで大学受験もひと安心だ」
過熱する中学受験を勝ち抜いた家庭の多くは、そう安堵しているかもしれない。
しかし、トップ校に合格したにも関わらず、受験に失敗する子、多浪に陥る子、無名大学に進学する子は一定数存在する。
「大学受験は単純な学力だけの勝負ではありません。模試や成績では目に見えにくい要素が、実は合否を分けているんです」。そう語るのは、9浪して早稲田合格を掴み、教育系インフルエンサーとして注目を集める濱井正吾氏だ。
受験における「失敗の共通点」とは何か、親としてはどう対策をとるべきか、全3回にわたって掘り下げていく。連載全3回の第1回。
目次
大学受験は「差を埋める競技」
私は浪人生活を9年経験し、またYoutube活動や講師業を通じてさまざまな大学受験生を見てきました。そのなかで感じているのは、「大学受験は自分の現状と第一志望との差を詰めていく作業だ」ということです。
学力面で言えば模試でD判定であれば、C判定にするために何が必要かを逆算して勉強をする。必要な参考書は何か、必要な学習量はどれくらいかを計算して学習計画を立てることが必須です。
これは受験生なら誰もが聞いたことのある話でしょう。しかし、ここで重要なのは、合格のために埋めなくてはいけない差は学力だけではないということです。合格者と自分を比較して、負けないレベルの学習習慣、熱量、情報量を身に着けなければ合格はおぼつかないのです。
仮に早大合格を目指しているのであれば、模試の判定の追求だけでは不十分。過去の合格者や他の早大志望者との差を知ったうえで、その差を縮めるように勉強をする必要があります。合格者たちは夏にどんな勉強をしているのか、どんな気持ちで勉強に向かっているのか、どんな学習方法をとっているのかなどを知り、それをベンチマークとして学習していくのです。
志望校に見合った「合格にふさわしい学習」を積み上げられているかどうかが、学力の伸びには非常に重要です。しかし、それができていない人は非常に多い。かつての私もそうでした。
では、なぜこの「差を埋める」ことができない受験生が多いのでしょうか。