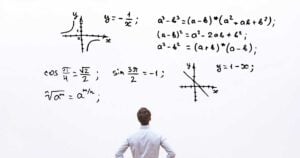あなたは「七五三現象」を知っていますか?数学塾トップが教える「文系のあなたが数学でつまずいた理由」

算数、数学の学習でつまずいてしまった、中学や高校でわからなくなって進路を変えた、今でもこの分野には苦手意識がある。そんなビジネスパーソンは多いはずだ。
教育の世界では「七五三現象」という言葉がある。算数、数学の授業についていけているのは、小学校で7割、中学で5割、高校では3割しかいないという意味だ。
「多くの人が算数、数学の正しい学び方を身に着けていません。量をこなして解法を覚えるという力技で乗り切ろうとし、中学・高校で壁にぶつかった人も多いのではないでしょうか」
そう語るのは永野数学塾の塾長、永野裕之氏だ。つまずかない算数、数学学習法とは何か、中学受験をさせる場合は何に注意すべきか、つまずいた際のリカバリー方法とはー。全3回の第1回。
目次
絶対に落としては行けない単元
算数、数学は「積み重ねの科目」だと言われます。前の段階であやふやな部分があると、より高度な単元を学ぶ際に正しい理解ができません。
「割り算」の理解が十分でなければ、中学受験算数のヤマである「割合」は解けません。
小学校で習う「場合の数」がわからなければ、高校の「確率」はわかりません。
中学で習う「一次関数」がわからないと、高校の「微積分」は理解できません。
算数・数学でつまずきやすい単元はコレだ
私はこれまで、数多くの小中高校生、社会人への算数・数学の指導を行ってきました。彼らの声を聞く中で算数・数学でつまずきやすい単元が見えてきました。
代表的な単元は下記のとおりです。
<小5 割合>
「2メートルのヒモの7割の長さは何メートルですか?」「4%の食塩水300gに塩は何g入っていますか」といった問題を扱う単元です。
割合は算数学習で初めて出会う抽象的な概念です。それまでは「3個のりんご」「5本の鉛筆」といったように数字自体が具体的な量を表していたのに対し、割合の単元では「もとの量に対する比」という抽象的な関係性を数で表現します。
数字が量や数の絶対量を表すわけではないという点が、子供にとっては混乱しやすいポイントです。
<小6 場合の数>
場合の数は「サイコロを2つふったときに、目の合計が5になるのは何パターンありますか」「6人の生徒で2人組を作る組み合わせは何パターンありますか」といった問題を扱う単元です。
確率は簡単に計算できることが多く、一見正しそうな答えが得られますが、実際には数え漏れや重複カウントが発生しやすく、本人がミスに気づきにくい特徴があります。
この単元は体系的に整理して数え上げる技術、樹形図や表を正確に作成する能力など、数学的思考力とは異なる「整理整頓能力」も必要です。
<中2 一次関数>
中学2年生で学ぶ関数では、「Y=aX」の式・グラフを扱います。XやYを使ってグラフの座標を求めたり、「X=3ときのYの値を求めなさい」といった問題が現れます。
子どもたちが混乱しやすいのは、XやYが場面によって変動する「変数」という概念です。方程式などで「わからない数字」をXやYと表現するのと異なり、「XやYが場合によって変わる」というのが、抽象的で難しく感じられるようです。
<高校数学A 整数の性質>
整数問題は「2019+m²=n² m,nは3桁の自然数であるとき、m,nを求めよ」「n³-7n+9が素数となるnをすべて求めよ」といった問題を扱います。
他の単元と異なり、問題にとっかかりが少なく柔軟な思考力が必要になります。一歩一歩確実に論理を積み重ねる必要があり、暗記では乗り切れない単元です。
<高校数学A 場合の数と確率>
小学校で学んだ場合の数の困難さ(数え漏れ、重複、見えないミス)に加えて、高校では論理的な厳密性と抽象的思考力が要求されます。