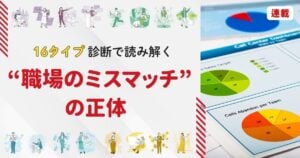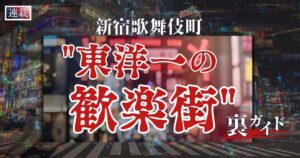「早稲田VS慶應どっち?」数学不要で私立文系が受けやすい大学というイメージは過去のもの、改革進める早稲田、対称的な慶應の入試制度

「早稲田と慶應、両方受かったらどちらに行く?」
この問いに対する答えは、長らく決まっていた。慶應義塾大学である。慶應がSFCを開設した1990年代から30年余り慶應優位の時代が続き、受験生・保護者・学校・受験業界から早稲田は格下と位置づけられてきた。
ところが2025年、この常識を覆す歴史的な出来事が起きた。両校に合格した受験生に対する調査で、進学先として早稲田が慶應の上位に立ったのだ。
「これは単なる一時的な人気の浮き沈みではありません。背景には早稲田の大胆な入試改革があります」
そう語るのは、東進ハイスクールを運営するナガセの市村秀二氏だ。戦前から続くライバル校「早稲田と慶應」、その人気の最新事情に迫る。連載全3回の第2回。
目次
躍進を生んだ早稲田の「無謀」と言われた改革
早稲田大学は2000年頃から継続的に学部改革を実施してきました。国際教養学部の新設、文学部の一文学部・二文学部から文学部・文化構想学部への再編、理工学部の基幹理工・創造理工・先進理工の三学部への改編など、大胆な組織再編を進めてきました。
2018年に就任した田中愛治総長は、さらに踏み込んだ教育改革を断行しました。教員採用では国際公募を徹底し、教育面では「5つの教育基盤整備改革」を推進しました。
全学生に「日本語の論理的発信力」「英語の発話と論理的文章作成」「数学的論理思考」「データ科学入門」「情報科学入門」を必修化し、文系学生にも数学やデータ科学を学ばせる文理融合教育を推進しています。
こうした一連の改革の延長線上に入試改革を位置づけました。そのなかで受験生に大きなインパクトを与えたのが、政治経済学部の入試改革です。
2021年、政治経済学部が共通テストで数学Ⅰ・Aを必須化したことは、受験関係者や大学関係者からは無謀とも言える動きでした。文系学部で数学を必須にすれば受験生の数は当然減少します。私立大学にとって志願者数の減少は、受験料収入の大幅な減少にも繋がりますし、偏差値の低下も引き起こしかねません。私立大学の経営戦略としては、志願者数を増やして難易度も偏差値も上げることでブランド価値を維持するのが王道です。
政治経済学部はこの改革により、志願者数が昨年比72%にまで激減しました。しかし、この改革はメディアでも広く報じられ、早稲田の改革の本気度が知れ渡ったこと、数学を得意とする東京大学や一橋大学からの併願者が数多く受験したことなどプラスに作用したのです。