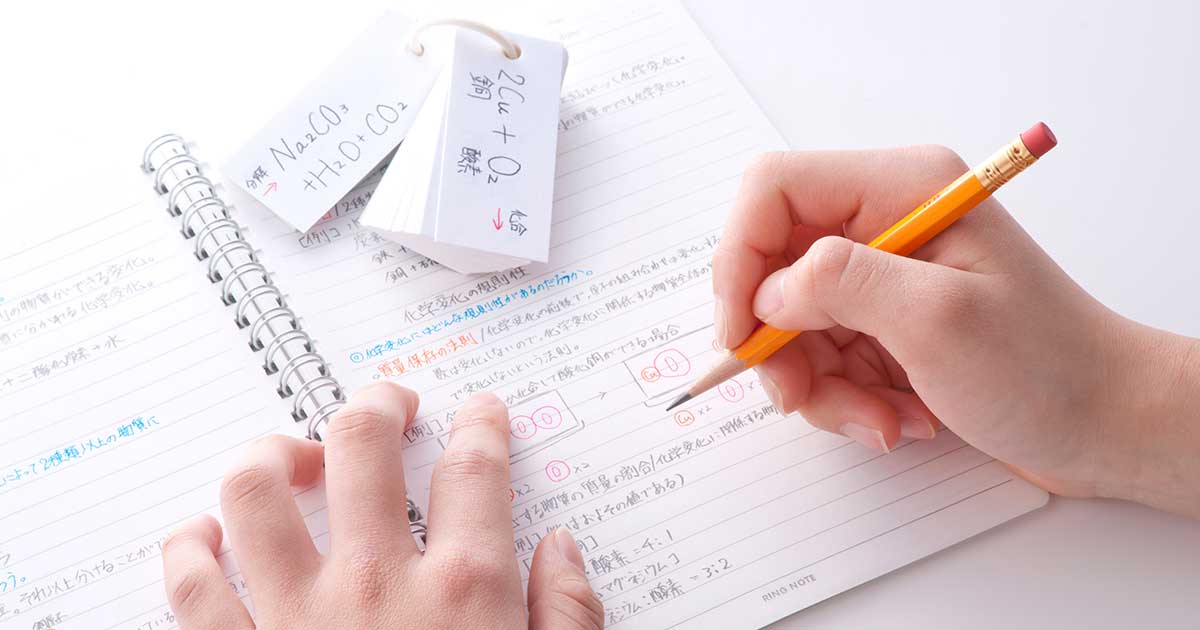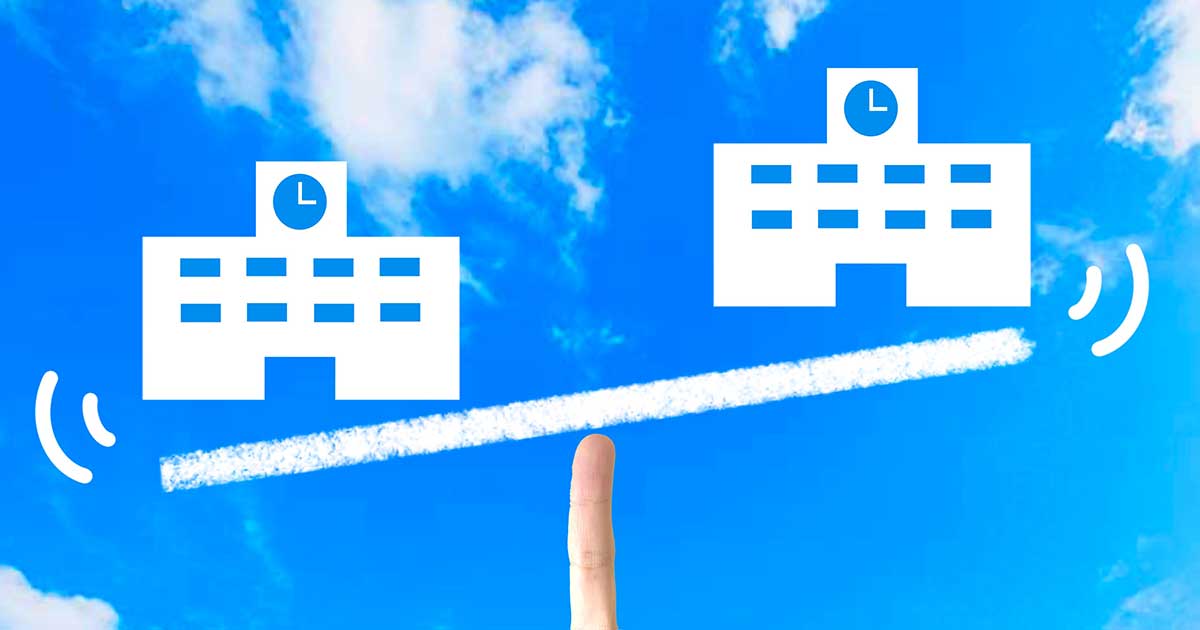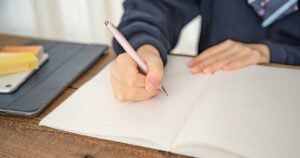「過去問」は早ければいいわけじゃない!中受プロが教える解き始めるタイミングの意味

夏が終われば、中学受験はいよいよ本番フェーズに突入する。
9月から1月校入試まで、残された時間はおよそ4ヶ月。自由に使える土日は、祝日を含めても約30〜35日ほどしかない。週末には志望校対策講座や模試があり、過去問にも取り組むとなると時間はいよいよ足りなくなってくる。
夏に思うような成果が出なかった子は、どうすれば巻き返せるのか。ここからライバルに差をつけるにはどうすればよいか。
「秋以降の学習は他人と同じことをしていても差はつきません」と語るのは、個別指導塾Growy代表のユウシン氏。
「それでも秋から本気で仕掛ければ、逆転はまだ十分に間に合います。R80偏差値で5くらいは逆転の範囲内です」
秋以降にすべき努力の方向性をユウシン氏が紹介する。みんかぶプレミアム特集「中学受験 最強戦略」第6回。
目次
基礎の穴を丁寧に埋めることを優先
夏までに受験に必要な単元はひと通り終わり、秋からは塾の授業も演習中心へと切り替わります。それに並行して、家庭では志望校の過去問にチャレンジしていく。この流れが、中学受験のスタンダードといえるでしょう。
ただし、過去問演習を始めるには、ある程度基礎が固まっていることが前提です。実際、9月の時点でしっかり基礎が定着しているのは、上位層のごく一部に限られます。多くの受験生にとっては、まだまだ「基礎固め」が必要な段階です。
たとえば、サピックス偏差値で50以下、四谷大塚で55以下、日能研で58以下くらいの子どもたちは、まだ基礎が不十分なことが多い。その場合は、無理に9月から過去問に取り組まなくても問題ありません。まずは焦らず、基礎の穴を丁寧に埋めていくことを優先してください。10月や11月からのスタートでも十分間に合います。
実際、多くの受験生が夏に初めて過去問を解いてみて、「全然解けない…」という経験をしています。そういう状態で続けても、演習の意味はあまりありません。力がつくどころか、自信を失ってしまうリスクもある。だからこそ、解き始める時期は“今の実力”を踏まえて見極める必要があります。