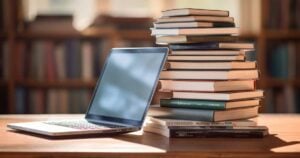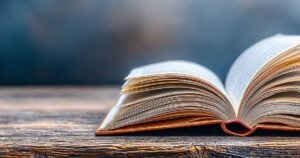「観光で学ぶ!」大河解説YouTuberが伝授する子どもを「歴史通」にするための親の接し方

中学受験で求められる内容は、ハイレベルな算数、高度な心情理解が求められる国語、複雑な実験考察が求められる理科など、深く、そして多岐にわたる。
そんななかで、家庭で求められる暗記量が非常に多く、受験生が苦戦しがちなのが歴史だ。授業だけでは到底覚えきれず、家庭での取り組みが学力に直結する。
「日本の受験教育で“歴史って単に暗記するだけの科目でしょ?”“年号や人名をひたすら覚えさせられて、嫌いになってしまった”という人は一定数います。しかし、これは非常にもったいない」
大河ドラマの解説を中心に、YouTubeチャンネル『戦国BANASHI』で歴史関連動画を発信しているミスター武士道氏によると、「歴史が楽しい」と思えるかどうかで、理解の深さや知識の身につき方が大きく変わるという。
子どもを歴史好きにさせるには、どうすれば良いのか。どうやれば歴史の知識が定着しやすくなるのか。ミスター武士道氏に聞いた。全3回の最終回。
目次
好奇心を刺激するには「近所を調べよ」
子どもに歴史を好きになってほしいと思ったとき、多くの親御さんは「まず知識を入れよう」と考えるかもしれません。でも、それよりも先に必要なのは、「これって何だろう?」「どうしてこうなったの?」と、好奇心をくすぐられる“きっかけ”です。
たとえば、近所の石碑や小さな神社、祠、地名などでもよいでしょう。その由来を調べるだけで、意外な歴史にたどり着くことがあります。
私自身、地名の由来を調べるのが好きで、「血洗島(ちあらいじま)」という名前に出会ったときは、「なんだこの怖い名前は」と衝撃を受け、そこから色々と調べたことがあります。
そういった身近な不思議から辿っていくと、自由研究のテーマにもなりますし、調べ方やまとめ方といった能力も身につくはずです。
都会に住んでいると、こうした歴史との接点が少ないと感じるかもしれませんが、きっかけがゼロということはないはずです。東京にも大手町に将門塚のような不思議な史跡がありますし、言い伝えが残る神社や歴史的出来事ゆかりの寺院も意外と身近にあります。
お祭りや神社を入り口にするのもおすすめです。「このお神輿は何のため?」「お祭りって何を祝ってるの?」「祀られてるのはどんな神様?」といった素朴な疑問から調べていくと、神社の由緒や宗教的な背景にも触れられるようになります。
そして何より大事なのは、子どもが好奇心を向けたその瞬間を大人が見逃さないこと。「調べてみようか」と一言かけてあげたり、地域の博物館へ誘導してあげるだけで子供の世界がぐんと広がると思います。