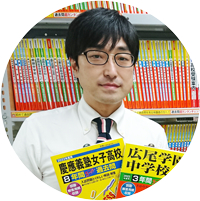中学受験で注目すべき「特進コース」プロが教える進学実績の見方

中学受験では進学校、伝統校、大学付属校など、さまざまな選択肢が存在する。そのなかで魅力的な選択肢の一つが「特進コース」のある学校だ。大学受験に特化したクラス編成やカリキュラムを特徴とし、中堅校に設置されているケースが多い。 「大学受験に向けて6年間手厚く見てくれる学校が多いので、保護者から見るとお得な進学先になるかもしれません。しかし、学校によって制度や進学実績がかなり違うので、選ぶうえでは慎重な検討と情報収集が必要です」
そう語るのは、中学受験過去問の出版社として知られる声の教育社 後藤 和浩社長だ。
志望校、併願校として「特進コース」をどう探すべきか。正しい選び方とは。連載全3回の第2回。
目次
同じような名前や制度でもさまざまな「特進」
特進コースは大学合格実績を高めることをおもな目的に設置されています。
学校側としては、優秀な生徒を集め、教育環境を整えることで学校の実績を上げたい、保護者としてはコスト面の納得感がありつつ面倒見の良い学校で、わが子を成長させてほしいと考えています。
しかし、特進コースは多くの学校が設置しており、同じような名前や制度でもさまざまです。事前にしっかり下調べをしておきましょう。
見ておくべきポイントの1つ目が「合格実績」です。有名大学に多くの合格者が出ていたとしても、一部の受験生の成果である場合があります。
早稲田大や慶應義塾大に2桁の合格者が出ていたとしても、実際の合格者数は数名ということは十分ありえます。実際の進学先を公表している学校もありますから、その場合はそちらもあわせて確認しておくと安心です。
また、東大コースであってもまだ東大合格者が出ていなかったり、医学部コースでも医学部医学科への合格者がほとんどいない学校もあります。
合格実績の上積みは「特進コース」に限った話ではありません。ただし、「特進コース」では、学校の合格実績をより多くするために、生徒に「幅広く受験」することが推奨される場合があり、実際の成果と数値に差が出やすい傾向があります。
2つ目が「総合型選抜」や「指定校推薦」が使えるかどうかです。
学校側は「特進コース」の生徒に、一般入試で有名大学の合格者数に貢献してほしいと考えています。そのため、受験校数が限られる「総合型選抜」や「指定校推薦」の利用を制限している学校もあります。
すでに大学入学定員の半数近くが「総合型選抜」や「指定校推薦」で入学しており、旧帝大などでも活用が進んでいることを考えると、受験方式が一般入試に限られてしまうのは、生徒によっては機会を逃してしまうように感じるかもしれません。
3つ目が「部活動の制約」です。
特進コースの生徒は部活が制限されたりする場合もあります。また、明確に制限はないものの、特進コースは授業のコマ数が多く、事実上部活に参加しにくい学校もあります。
学校側から「禁止」とされていなくても、「特進コースは帰宅部で勉強に時間を使うもの」という雰囲気が自然に根付いている学校もあるようです。