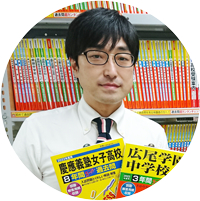中学受験「特進コース」選び、プロが伝授する「見落としてはいけない」親の責任とポイント

中学受験では進学校、伝統校、大学付属校など、さまざまな選択肢が存在する。そのなかで魅力的な選択肢の一つが「特進コース」のある学校だ。大学受験に特化したクラス編成やカリキュラムを特徴とし、中堅校に設置されているケースが多い。
「大学受験に向けて6年間手厚く見てくれる学校が多いので、保護者から見るとお得な進学先になるかもしれません。しかし、学校によって制度や進学実績がかなり違うので、選ぶうえでは慎重な検討と情報収集が必要です」
そう語るのは、中学受験過去問の出版社として知られる声の教育社 後藤 和浩社長だ。
志望校、併願校として「特進コース」をどう探すべきか。正しい選び方とは。連載全3回の最終回。
目次
「特進コース」を止めた学校も
特進コースは、大学受験に向けた学力強化を目的に、多くの学校で導入されてきました。一方で、近年はあえて特進コースを設けず、別の仕組みで学習支援を行う学校も増えています。
たとえば、富士見中学高等学校は、かつて特進コースを持っていましたが、現在はコース制を採用していません。学校全体の一体感を重視しつつ、キャリア教育や探究学習に力を入れる方針へ転換したためです。クラスを分けるのではなく、多様な進路希望に応じて選択科目やプログラムを広げる形で対応しています。
こうした学校で導入される傾向にあるのが、アラカルト型の授業選択や習熟度別授業です。アラカルト型とは大学の履修のように、複数の選択科目から生徒が自分の関心や進路に応じて学ぶ方式です。
英語だけでも「基礎英語」「英語リスニング」「難関大英作文」といった多彩な講座が用意されており、自分に必要な内容・難易度の授業を選択できます。
習熟度別授業は、特進・一般のように固定的なクラス分けをせず、科目ごとにレベルに応じた授業を受ける方式です。数学や英語は上級クラス、理科は標準クラスといった形で、得意不得意に応じて学ぶことができます。
こうした仕組みによって、学校は全体的に幅広い進路に対応できるようになり、生徒一人ひとりに合わせた学習環境を整えることができます。
「特進コースを設ける学校」がプロが選んだコース料理のような形式なのに対し、「アラカルト型や習熟度別の学校」は自分で選ぶセットメニューのような形式になっています。
学校が目指す教育の方向性によって制度設計が分かれているので、保護者や受験生にとっては、自分の希望や適性に合った仕組みを選ぶことが重要です。