中学受験「勝者」たちのリアルな就職先をカリスマ塾長が暴露…令和のトップエリートたちが本当に目指すキャリアとは
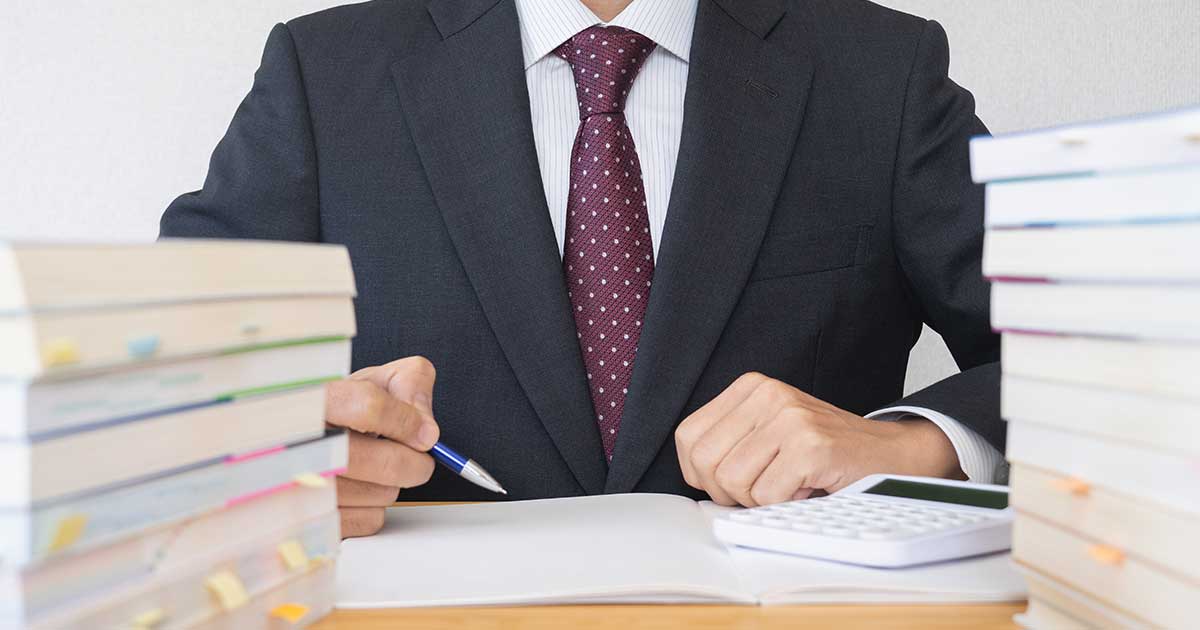
首都圏を中心に過熱する中学受験。多くの親が「周りもやっているから」という漠然とした思いでその渦に飛び込んでいないだろうか。長年、数々の生徒を難関校合格へ導いてきた中学受験を考える塾長氏は、こうした「なんとなく中学受験」に警鐘を鳴らす。
最近出版された著書『中学受験は戦略が10割: 東大生の親が絶対やらないこと (みんかぶマガジン新書)』の売れ行きも絶好調な同氏に、中学受験に向く子の素質や家庭の経済的条件といった現実的な側面から、中学受験とその後のキャリアの意外な関係性、AI時代のビジネスに直結する子どもの思考力の鍛え方まで、幅広く語っていただいた。全3回の第3回。みんかぶプレミアム特集「キャリアから考える中学受験」第6回。
目次
ビジネスの現場で通用しない“視野の狭い大学受験エリート”たち
大学受験の勉強は、どうしても科目が限定的になりがちです。例えば、理系の学生は社会の科目に疎くなりがちですし、逆もまた然りです。私の知る限りでも、中学受験を経験していない東大の理系の学生の中には、驚くほど社会のニュースに興味がない人がいます。彼らは受験に必要な科目だけを深く掘り下げてきたため、知識に偏りが生じてしまっているのです。
ビジネスの現場では、文系・理系といった垣根を越えた、総合的な知識や教養が求められます。歴史の知識が新たな企画のヒントになったり、地理的な知見がマーケティング戦略に活きたりすることは日常茶飯事です。その土台となる、広く満遍ない教養を身につけられるのが、中学受験の大きな魅力なのです。
公立中で固定化される「人間関係」と「生活圏」の限界
もう一つ、見過ごされがちな中学受験のメリットがあります。それは、多様な地域的バックグラウンドを持つ仲間と出会えることです。
地元の公立中学校に進学した場合、そのコミュニティは基本的に同じ小学校の出身者で構成されます。友人関係も、生活圏も、非常に限定的な範囲にとどまります。その後、都立高校に進学したとしても、ほとんどが都内在住の生徒です。
しかし、偏差値の高い私立中学校となると、その通学圏は一気に広がります。ドアツードアで1時間以上かけて、千葉や埼玉、神奈川から通ってくる生徒も珍しくありません。













