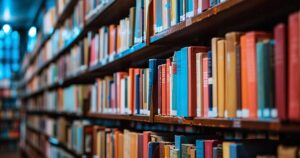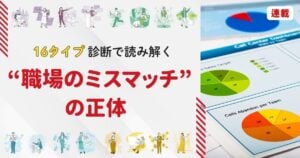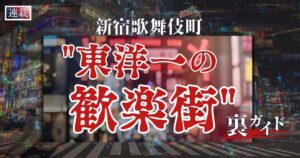大学受験の「序列」に激震…早慶W合格者はなぜ早稲田を選ぶのか 慶應の“ブランドイメージ低下”を招いた意外な要因とは

わが子の教育にかけた費用は、本当に「元」が取れるのか――。これまで教育の世界では「品がない」とタブー視されてきた「コスパ」という視点から、今注目の2人が対談。学歴活動家として独自のポジションを築くじゅそうけん氏と、保護者目線で業界の闇に切り込む教育投資ジャーナリストの戦記氏が、中学受験のリアルを徹底的に語り合った。
中学受験にかかる衝撃的な費用の実態から、中学受験からの「賢い撤退」戦略まで、綺麗事なしの本音トークは中学受験を検討するすべての保護者にとって必見だ。短期連載全10回の第4回。(対談日:10月3日)
お二方の書籍が大好評発売中です!
目次
激変する大学の“序列” 早慶W合格者はなぜ早稲田を選ぶのか
――ここで、少し話を大学の話題に移したいと思います。じゅそうけんさんがみんかぶマガジンで連載を始めた当初、早慶の学部の序列に関する記事が大きな反響を呼びました。そして最近、大学受験の世界では、早稲田と慶應にダブル合格した場合、かつては慶應を選ぶ受験生が多かったのが、早稲田を選ぶ受験生が増えているというデータが出てきています。この早慶の序列の変化について、お二方のご意見をお聞かせください。
じゅそうけん: これは我々が常にウォッチしているテーマですね。ここ20年ほど、早稲田大学と慶應義塾大学の両方に合格した受験生は、圧倒的に慶應に進学する傾向が続いていました。ところが今年のデータで、ついにその比率が逆転し、早稲田を選ぶ受験生が慶應を上回ったんです。
早稲田と慶應の明暗を分けた“たった1つの科目”
戦記: 歴史的な転換点ですよね。その最大の要因は、早稲田大学が断行した「入試改革」にあると見ています。特に象徴的なのが、看板学部である政治経済学部が、一般入試で数学を必須科目にしたことです。
これまで早慶の文系学部は、国語・英語・社会の3科目で受験するのが一般的でした。そこに数学を課すことで、東大や一橋大といった最難関国立大学を第一志望とする、数学のできる優秀な受験生を併願者として取り込めるようになった。受験生のレベルが、質的に向上したわけです。一方で、慶應の文系学部は、今でもほとんどが数学なしで受験できます。この差が、国立大学からの併願者を早稲田ががっちり確保できるようになった大きな理由だと考えています。