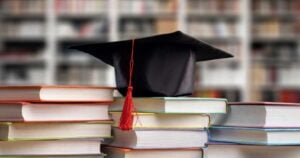つくばEXPの地味駅・八潮が「ヤシオスタン爆誕」で流山おおたかの森に完全勝利している…ブルーカラーもパキスタン人も排除しない近未来型都市を歩く
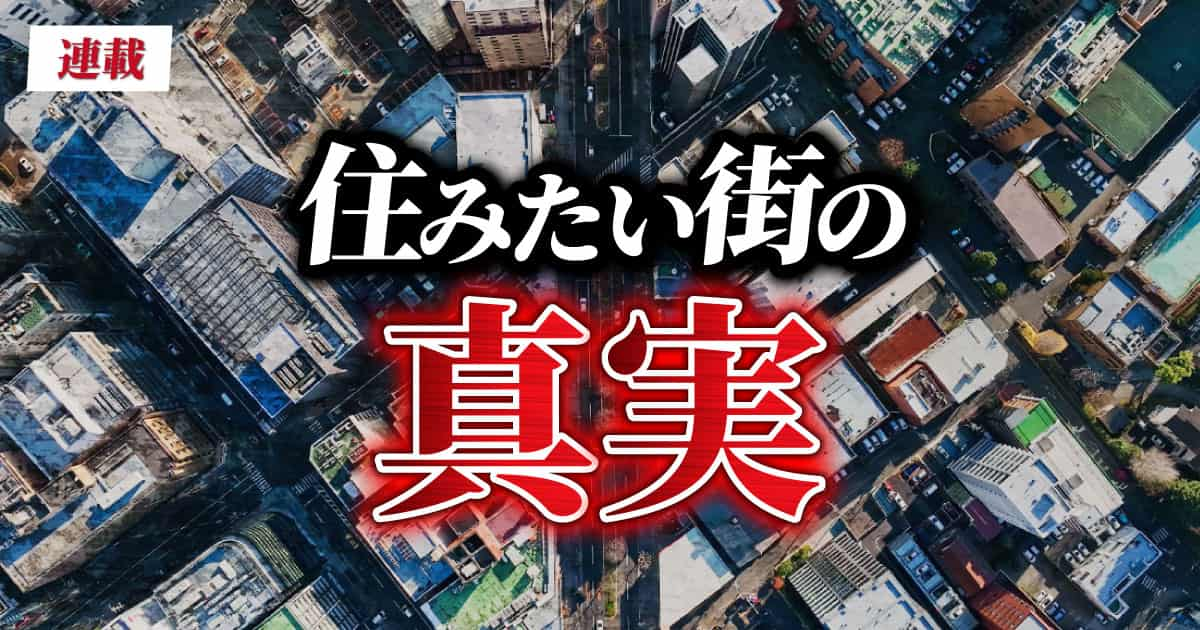
「住みたい街」と評される人気のエリアにも、掘り起こしてみれば暗い歴史が転がっているものだ。そんな、言わなくてもいいことをあえて言ってみるという性格の悪い連載「住みたい街の真実」。
書き手を務めるのは『これでいいのか地域批評シリーズ』(マイクロマガジン社)で人気を博すルポライターの昼間たかし氏。第9回は、「2025年 LIFULL HOME’S みんなが探した!住みたい街ランキング(埼玉県版)」において、“借りて住みたい街”の第6位にランクインし、「ほぼ都内駅」として人気を集めている八潮市を歩く。
目次
地味な街の「ガチ」な異国「ヤシオスタン」
埼玉県八潮市は東京都に接する地味な街。そんな街の名物はパキスタン料理である。
市の統計によれば、2025年10月時点の人口は9万3779人。市役所で配布されていた『広報やしお』11月号によれば、10月時点で外国人人口は54カ国5398人となっている。パキスタン人の総数は中国人・韓国人ほどではないが、ハラールマーケットが成立するくらいには存在感がある。なにより、日本人向けにアレンジしてないガチのパキスタン料理の店が複数あるのが、ポイントだ。

【010: 住宅地の中にハラールマーケット。完全に市民の生活になじんでいる】
そこで、まずは舌で探訪するべく、市役所近くにある「アルカラム」という店に。昼過ぎの店内は日本人と中東系の客が半々くらい。中東系のいかにもなオジサンたちは日本語でずっと商売の話。
お店の人は日本人とみるとちゃんと日本語で話しかけてくれる。ちゃんとメニューも日本語……いや、料理名の発音を片仮名にしているだけで、まったくどんな料理か皆目見当がつかない。でも、尋ねたら「チキンとマトンとどっちがいい?」と丁寧に教えてくれる。

【014: アルゴーシトとかいわれても、なにがアルゴーシトかまったく理解できない】
問題は、テーブルに運ばれてきた料理のサイズ。並々とカレーが注がれた皿に肉がゴロゴロ。そして、チャパティとナンもビッグサイズで、ラッシーにいたってはほぼジョッキである。それでも猛烈な美味さゆえに手が止まることはなかった。でも、その日は深夜になっても満腹感から解放されることはなかった。

【015: これで一人前とかどういうこと? でも、ほかのお客もみんな完食してた】
そんなガチなスタイルが当たり前の八潮市。色々と外国人問題が騒がれる昨今だが、不思議とネガティブな話題はない。多種多様な人々が見事なまでに共存している世界がここにある。
そんな世界が成立しているのは、なぜだろうか。
「陸の孤島」から「ほぼ都内」へ。八潮の多様性を生んだ背景
昭和の高度成長期まで、八潮市は純然たる農村地帯であった。昭和30年代以降、東京への近さゆえに工場進出が本格化し、農村は内陸工業地帯として発展していった。これによって、八潮市は従来の居住者に加えて、様々な出身・属性を持つ人々が移り住む土地となった。
そこにさらに変化を加えたのが2005年のつくばエクスプレスの開通だ。これによって、市内には八潮駅が開業した。それまで八潮市は、東京に隣接しながらも鉄道駅のない文字通り陸の孤島のような土地であった。
しかし、つくばエクスプレスの開通は八潮市を、秋葉原駅まで最短17分の都心に直結した郊外へと変えた。これにより、八潮市は都心のベッドタウンとして注目されるようになり、今まさに移住者を増やしている。
わかるだろうか。八潮市はもともとの居住者である農民層に、雇用を求めて各地から集まってきたブルーカラー。そして、つくばエクスプレス開業以降に移住してきたホワイトカラーと様々な階層と属性が集まる土地である。ゆえに、外国人人口の増加も当然のこととして受け止められているわけだ。
八潮市の暮らしやすさとは、この階層と属性が混在することにほかならない。
コメダ珈琲の進出が表す「新住民」と「余裕」の正体
そんな八潮市だが、実際に生活利便性はどうなっているのだろうか。