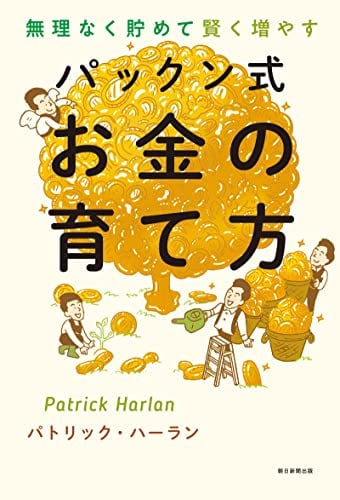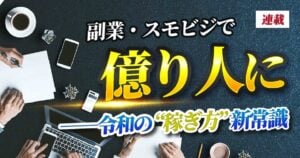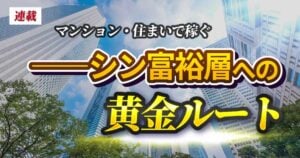ハーバード卒パックン、Xmasは子供に現金80万円プレゼントの理由…漫画は「友達に借りな」

ハーバード大卒芸人のパックンは「アメリカには何事もお金で測るような側面があり、超現実的なお金の教育が行われている」と話す。今、日本では終身雇用制度の前提が崩壊し、アメリカ型の雇用に近づいてきた。だからこそ日本でも金融教育が必要だと指摘するパックンが、自身の経験や家庭で実践している子どもへの教育について語る――。全4回中の2回目。
※本稿はパトリック・ハーラン著『無理なく貯めて賢く増やす パックン式お金の育て方』(朝日新聞出版)から抜粋・編集したものです。
目次
「先月の給料いくら?」が当たり前のアメリカ
みなさんに投資を考えてもらいたいのは「時間をかければかけるほど、お金は急速に増えていく」からです。これを専門用語で「複利」と言います。
たとえば、100万円を年間10%の利益率(年利10%)で投資したとしましょう。10年間投資しておくと、10万円×10年=100万円が稼げます。こういうシンプルな形で利益を計算する方法が「単利」です。
これももちろんありがたいですが、これと「複利」はまったく別物。複利は最初に投資したお金だけでなく、利息を元本に足していくから、その利息に対しても利息がつくわけです。そうするとすごいことが起きます!
もともとの100万円が、倍の200万円になるまでに単利だと10年かかりました。でも複利だと、もともとのお金が倍になるまでに、7年強で済みます。3年近く短い期間でお金が倍になるなんて、魔法みたいですよね?
複利は、預金や借金、投資など、生活のいろいろな場面で登場しますので、誰もが知っておいて損はないでしょう。でも、こんなに大事な話なのに、日本では複利のことを知らない人が少なくないよね。
今まで日本の学校では教えてこなかったから、知らなくても当然かもしれませんが、複利を知らないまま社会に出るということは、アメリカ出身の僕からするとちょっと不思議に思います。
アメリカでは、普段の会話の中でお金の話が出てきます。だから、普段の会話を通じて、投資のことや複利のことなどに自然と馴染んでいきます。「先月の給料はいくらだった?」「どこの株に投資しているの?」みたいな会話は日本では珍しいかもしれないけれど、アメリカでは比較的ノーマルです。
おそらく、これは文化の違いだけではなく、日本人が環境的に恵まれていたことも影響していると思います。日本はアメリカと違って、終身雇用の企業が多いと言われています。最近は少しずつ変わってきているようですが、それでもアメリカのように「転職が普通」という感じではありません。実際、統計によると、日本人の勤続年数は世界トップクラスです。
一方で、アメリカでは、大学を卒業して就職しても、すべてを会社まかせにできません。 自己責任で自分の経済的な安定を保たないといけませんので、友達同士でも給料や投資などの情報共有をするのです。
アメリカのようにお金のことを考えなくてもいいのは、ある意味で日本の優れた点だと思います。親が大学卒業まで面倒を見てくれるし、あとは入った会社のレールの上を走れば安全。一度、会社に入ってしまえば、年功序列で賃金が上がって、それなりの生活ができる。健康保険や年金などの福祉制度もしっかりしているから、お金のことを考えずに生きていける。
でも、だからこそ、日本ではお金のことを学ぶ機会が少ないという側面も、きっとありますよね。僕は、日本とアメリカのどちらが優れていると言いたいわけではありません。
しかし、今は日本でも、雇用環境や働き方が変わってきました。方向性としては終身雇用から、アメリカ型の働き方に近づいているのです。そんな現代だからこそ、お金の基本を学ぶことは大事です。国や会社に依存するのではなく、自分の頭でお金のことを考えていきましょう!
中学校で「リアル人生ゲーム」
アメリカ文化には良い面、悪い面があります。しかし、ここでは良い面を取り上げたいと思います。それは、学校教育にもお金のことがしっかり取り入れられていること。
僕がいた中学校は、とくに金融教育に力を入れていたようです。そうした授業の中でも印象に残っているのが、超リアルな「人生ゲーム」。日本で知られている人生ゲームは、ルーレットを回して、止まったマス次第で勝敗が決まりますよね。
「ミスコンで優勝したから○○○ドルプラス」「財布を落としたから○○○ドルマイナス」みたいな感じ。基本的には運の勝負なので、面白いけれどリアルとは違います。しかし、僕が中学校でやった人生ゲームはこんな感じでした。
ゲームを始めるにあたり、まず僕らは住みたいエリアを決めます。「LA(ロサンゼルス)のおしゃれな街に住みたいな」とか「カントリーサイドでのんびり暮らしたいな」とか、何となく考えます。
その次に行うのが、そのエリアで生活するための予算作りです。「このあたりの家賃はどれくらいだろう」と調べて、さらに家具などの予算も見積もる。たとえば革張りのソファが欲しかったら、その金額を予算に加えます。
でも、革張りのソファを買えるだけのお金がなければどうする? 大丈夫。そんなときは「分割払い」も選べます。手数料がかかるけれど。生活費の予算を見積もったら、収入の予測も立てないと。ここでは職業選びが肝になります。
たとえば建築家を選んだとしましょう。建築家は高収入な職業です。建築家になれば、都会で暮らすのも大丈夫そうだよね。ただ建築家になるためには、奨学金を借りて学校に行く必要があります。それに働いて最初の数年間は給料が低い。だから、低い収入で奨学金を返しながら、生活ができるのかを計算する必要があります。
この人生ゲームには、病気などのリスクも考慮されていました。日本のように手厚い公的医療皆保険制度はアメリカにはありません。なので、大病をすると大変です。せっかく生活が軌道に乗ってきたと思っていたら、先生が「みんなさいころ振って……。はい、1が出た人、突然の入院です!」という具合にハプニングが起きたりしました。
医療費を支払うために、せっかく買った革張りのソファを手放さなくてはならないかも……。といった感じで、パーティなどでは絶対にやりたくない、すごくリアルな人生ゲームだったのです。
「80万円」のプレゼントで金融教育
僕は今、2人の子どもを育てています。親として、彼らに向けて「お金の教育をしたい」と思っていますが、実際にやってみると「難しい!」と感じることが少なくありません。
そもそも、僕は子どもたちにお金の心配はさせたくない、と思っています。子どもの頃の僕みたいに、経済的な不安からやりたいことを諦めてほしくはない。自分が望む未来に気兼ねなくチャレンジできるように育ってほしいのです。
ただ、その一方で、お金は無限にあるものではなく、手に入れるためには努力も我慢も計画も必要であることは理解してもらいたい。僕たちは家族でよく海外旅行に行きますし、子どもたちはいろいろな習い事もやっています。でも「それが当たり前」だとか「何でも苦労なく手に入る」などとは思ってほしくありません。
そこで僕がやっているのは、「何でもすぐに手に入る」という状況をなるべく作らないこと。子どもたちが欲しいものを買おうとしたとき、必ず話し合いをしています。
まず話すのは「買わずに済む方法」について。「本が欲しいというけれど、図書館で借りればいいよね」「その漫画が流行っているなら、友達と貸し借りできない?」「その洋服、似たのを持ってなかったっけ?」といった感じです。
こうやって、まずはお金を払わなくても欲しいものを手に入れる方法がないか、を考えてもらいます。それでも「どうしても買いたい」と言うなら、「1週間家の手伝いをしたら買う」などの条件をつけます。
さすがに僕のように10歳から新聞配達をさせることはないにしても、「自分で稼ぐ」という疑似体験はしてもらいたい。買い物に一緒に行くのも、いい教育の機会です。たとえば「今日は3000円以内に収めよう。1円単位は四捨五入して、パッと計算してみよう!」みたいに、ゲーム感覚でお店を巡ります。
これは金銭感覚を鍛えることにも、算数の勉強にもなるから、一石二鳥。レジで会計をするときは、クレジットカードの分割払いや手数料の仕組みなどを話すチャンス。「とにかくリボ払いはダメ!」とかね。こんなふうに日常の中で金銭感覚を育てることは、結構大事なことだと思います。