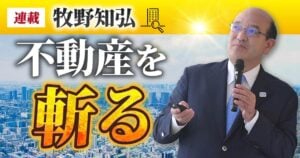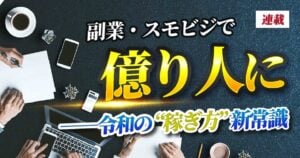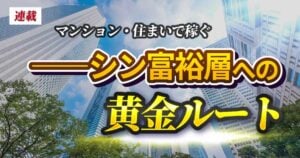タワマンは短期で転売せよ!投資マネーが流れ込んでいるタワマンの落とし穴

駅近、豪華な共用部、見晴らしのよさなど、憧れる人も多いタワマン。ただし不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏は、「タワマンに長期間住む、あるいは保有することには疑念がある」と話す。タワマン投資をどう捉えるべきなのか、牧野氏が解説する。全3回中の3回目。
※本稿は牧野知弘著「不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問」(大和書房)から抜粋、再構成したものです。
第1回:金利の上昇=タワマン投資の終わりの始まり?!ローン返済シミュレーションを考える
第2回:お金持ちは“2種類”にわけられる……伝統的なお金持ちの「財産を守る」不動産の持ち方とは
目次
タワマンの将来は不透明すぎる
ここでは「投資商品としてのタワマン」について掘り下げるとともに、投資性能だけではない、タワマンの機能性について掘り下げていきましょう。
近年、急速にその存在感を増したタワマンは多くの物件で中古価格が値上がりしたことから、資産形成の一助になると喧伝され、タワマン売買によって富裕層に仲間入りしたと称するSNS動画なども多数アップされるようになっています。
いっぽうでタワマンという超高層建物ならではの高額の管理費や修繕、設備更新費用などについては今後も不透明な部分が多く、将来的に負の資産となることを懸念する声も増え、値上がりに対する怨嗟の声も含めて侃々諤々の状態です。
このタワマンという不動産を考える場合には、私は取得しても短期間での転売を勧めしています。
都心のものが多く、通勤にも便利。さまざまな都心ならではの利便性については言うまでもありません。私自身も、平日は文京区に在住しているのでこのメリットを享受しています。
ただ資産としてのタワマンを見た場合には、長期にわたって住むこと、あるいは投資用として保有することには疑念を持っています。
多くの人がタワマンを賞賛する裏には、近年の急激な値上がりによる要素が強いことに着眼する必要があります。
特に大規模金融緩和が行われた2013年以降、タワマン中古価格は急騰しています。たとえば東京の湾岸エリアのタワマンは当初は坪250万円から300万円程度で販売されたものが現在では坪600万円から700万円台に急騰しています。ざっくり倍になった物件が数多く出現しています。
この間で日本国民の年収は増えるどころか下がっているのにもかかわらず、タワマン価格はうなぎのぼりでした。
この現象を読み解くには投資や節税需要の高まりが背景にあります。つまりタワマンは実需のためのものというよりも金融商品に近い性質のものに変質したといってよいのです。
人気のタワマンは市場での流通性も高く、転売益を狙った売買が続いているため、手軽に買って売り抜ける投資家の動きが絶えることがありません。晴海フラッグなど、実需ではなくまさに金融商品のように、売買を目的とした投資マネーが流れ込んでいるのがタワマンに代表される都心高層マンションなのです。