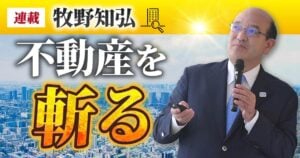「五輪後にマンション暴落」予測はなぜ外れたのか 外国人から見れば“半額セール”状態になってしまった日本の不動産の悲惨な末路

都心マンション価格は天井知らずの高騰を続け、溢れる情報と「バブル崩壊」の警鐘に、多くの住宅購入検討者が迷いを深めている。こうした状況に振り回されないための“基礎体力”こそ重要だと語るのは、不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏だ。
土地の本質的価値を読み解く方法から、コロナ禍以降のマンション価格高騰のカラクリ、将来的な不動産価値の見極め方、さらには首都圏の穴場エリアまで、同氏に縦横無尽に論じていただいた。短期連載全4回の第2回。(取材日:8月12日)
目次
なぜ専門家の「五輪後にマンション暴落」予測は外れたのか
――「金融商品」としてマンション相場が過熱している状況を見ると、いつか下落する局面が来るのではないかと感じます。一方でかつて、2020年の東京五輪が終われば不動産価格は落ち着く、あるいは下落するといった予測が多くありました。しかし、現実は真逆の爆上がりでした。これはなぜなのでしょうか。
金融商品である以上、未来永劫右肩上がりのものなど存在しません。必ず上がったり下がったりする。不動産、特に区分所有マンションが金融商品化しているということは、今後、まだ上がる可能性はあるにせよ、下がる局面も必ず来るということです。ただ、多くの方が「不動産だけは別だ」と信じてしまっている傾向が強いですね。
そして、なぜ2020年以降に価格が暴落するという予測が外れたのか。これを「専門家は外したじゃないか」と結果論で批判する人がいますが、彼らは、なぜそうなったのかという要因をきちんと分析していません。
五輪後にマンション価格が“爆上がり”した本当のカラクリ
この問いに対する答えは、実は非常に明確です。2020年には何が起こったでしょうか。そう、「コロナ」です。
2013年頃から始まったアベノミクスによる大規模金融緩和で、日本は長らくゼロ金利、マイナス金利という状況が続いていました。そうした中、2020年を迎えようとしていた当時、日銀はそろそろ利上げのタイミングを見計らっていたのです。物価も上がり始めていましたから。しかし、その利上げをしようとした矢先に、コロナ禍が襲来しました。
経済活動が止まり、多くの産業が打撃を受けたことで、日本政府と日銀が何をしたかというと、「さらなる金融緩和」です。そして、コロナ支援という名目で十数兆円もの補助金や支援金を市場に投入しました。このお金がどこへ向かったのかというと、一部は貯蓄に回りましたが、その多くが株式や不動産といった投資市場に流れ込んだのです。
つまり、もともとお金が「ジャブジャブ」だった市場に、さらに大量のお金が注ぎ込まれた。これが多くの専門家の予測とは裏腹に、五輪後もマンション価格が上昇し続けた大きな要因です。
「円安×低金利」のコンボが日本の不動産市場にもたらした恐るべき影響
――世界的な要因もあったのでしょうか。
まさにそうです。コロナは世界的なパンデミックでしたから、世界中の中央銀行が日本と同様に利下げを行い、「世界同時金融緩和」という状況になりました。世界中で大量のお金が刷られたのです。
その後、コロナが収束に向かうと、アメリカをはじめとする欧米諸国は急激なインフレを抑えるために、一斉に利上げに踏み切りました。アメリカのFRBは約4%もの利上げを実行しました。しかし、日本だけが利上げをしなかった。ゼロ金利政策を頑なに守り続けたのです。
その結果何が起こったかは、皆さんご存じの通りです。欧米と日本の金利差がどんどん広がり、歴史的な円安が進行しました。コロナ前の2019年、1ドル=110円前後だった為替レートが、今や150円前後になっています。
外国人から見れば日本の不動産は“半額セール”状態になってしまった
この極端な円安によって、外国人投資家から見ると、日本の不動産が「激安」に見えるようになりました。そして、大量の外資マネーが日本の不動産市場、特に注目度の高い湾岸のタワーマンションなどに流れ込み、爆買いが始まったのです。
つまり、2020年以降の不動産価格の爆上がりは、「コロナによる国内のさらなる金融緩和」と、「世界同時金融緩和後の日本の“利上げしない”政策が生んだ極端な円安」という、二つの巨大な要因によって引き起こされたものです。これを事前に予測できた専門家は、おそらく一人もいなかったでしょう。ですから、2015年や2017年にたまたま湾岸マンションを買って、価格が2倍、2.5倍になったという方は、あくまで結果として幸運だった、と考えるべきです。
長期金利の上昇は“不動産バブル終了のサイン”なのか
――なるほど。そうなると、今後の不動産市場を占う上では、やはり金融政策、特に日銀の金利の動向がカギになるということですね。