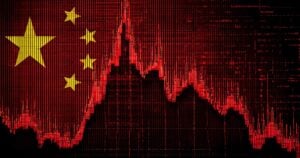長期的なリターンを逃すのは“売買のタイミングを測る”から……億越え投資家「最後はインデックス投資に帰ってくることになる」

会社勤めのかたわら、2002年からインデックス投資を始めたベテランインデックス投資家の水瀬ケンイチ氏。“26歳貯金なし”から20年で1億円超を達成した水瀬氏が、「ふつうの人」のインデックス投資の始め方について語る。全3回中の2回目。
※本著は『彼はそれを「賢者の投資術」と言った 水瀬ケンイチのインデックス投資25年間の道のり全公開』(Gakken)から抜粋、再構成したものです。
第1回:「これこそ私の求めていた投資法だ」山崎元氏がもっと信頼した個人投資家が、インデックス投資にたどりついた理由
第3回:投資にかけたその時間、無駄じゃないですか?億越え投資家がたどり着いた「手間をかけない投資」の魅力
目次
最初は「緊急時の資金の確保」から
財務計画の専門家は、緊急時のための資金を持つことが投資成功の前提条件であると強調している。JPモルガン・アセット・マネジメントの「Guide to the Markets」(2019年第4四半期版)によると、緊急資金を持たない投資家は市場暴落時に資金が必要となり、最悪のタイミングで投資を引き出す確率が3倍高くなる。
私も2008年のリーマン・ショック時に、この重要性を痛感した。当時、ポートフォリオポートフォリオの損益はプラス10%~20%あたりで順調に推移していたものが、あっという間にマイナス50%近くまで暴落した。金額にして1000万円近くが軽く吹っ飛んだことになる。それでも冷静でいられたのは、生活防衛資金の預貯金がたっぷりあり、たとえリストラされても当面は生きていけるという安心感があったからだ。
フィデリティ社の「Emergency Savings Research」(2019年調査)では、6カ月分以上の生活費を現金で保有している投資家は、市場暴落時でも95%が投資計画を維持できることが示されている。
生活防衛資金の目安は、単身者なら月の生活費×6カ月、家族持ちなら月の生活費×12カ月が望ましいといわれている。しかし、私はリーマン・ショック、東日本大震災の経験から、生活費の2年分まで用意することを目標にしてよいと思う。
20年、30年といった長期投資の間、もっといえば人の長い人生で一度や二度くらいは、勤務先の倒産、リストラ、大病、大災害といった特大リスクに見舞われてもおかしくない。被災地での生活の立て直し、自分を安売りしないで済む転職先探し、長期間の療養などの際には、投資のことなど気にせずどんどん取り崩しても何の問題もない生活防衛資金の存在があなたと家族を救うだろう。
実際、私も職場のストレスから体調を崩したとき、休職という選択をためらわなかった。生活費が確保できていたからこそ、自分の健康を優先できたのだ。
「生活防衛資金を貯められなければ投資を始めてはいけない」とまでストイックに考える必要はない。生活防衛資金と積み立て投資を半々くらいで始めればよいだけだ。いずれ、必要な生活防衛資金が貯まり、安心感とともに投資ができるようになるだろう