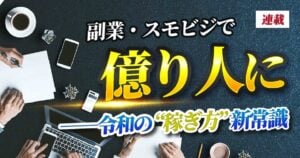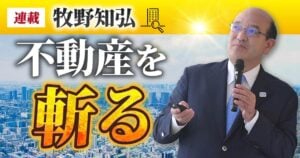東京の“不動産序列”が完全崩壊でマンション市場は新時代へ…たった1つの数字でわかる「買ってはいけない物件」の見抜き方とは

都心マンションの価格は高騰を続け、「普通の会社員にはもう手が届かない」といった悲観論が渦巻いている。だが、本当に諦めるしかないのだろうか。SNSで単身者や一次取得者向けに情報を発信する不動産インフルエンサー・ちょうすけ氏は、「正しい知識と戦略があれば、十分に勝機はある」と断言する。
自身も昨年都心1LDKを購入し、わずか1年で約1,300万円の含み益を出しているという同氏に、その戦略の全貌を解き明かしてもらった。全4回の第2回。みんかぶプレミアム特集「マンションはまだ稼げるか」第5回。
目次
「現金派」vs.「不動産派」インフレ時代に笑うのはどちらか
今のマンション市況はバブルとは言えないと考える最後の理由は、人々の心理的なマインドの変化です。食料品や日用品など、身の回りのあらゆるものの値段が上がり、「インフレ」が日常のものとなりました。多くの人が、「現金(日本円)を銀行に預けておくだけでは、その価値はどんどん目減りしていく」という不安を感じています。
このインフレマインドが、「価値が下がりにくい実物資産に換えておこう」という動きを加速させています。その代表格が、都心のマンションです。「どうせ物価が上がるなら、値上がりする資産をローンで先に手に入れてしまおう」という考え方は、非常に合理的です。
たった1つの数字でわかる「買ってはいけないマンション」の見抜き方
ここまでさまざまな理由を述べましたが、それでも「バブルではないのか?」という疑問は残るかもしれません。僕が考える「バブル的な物件」と「実需に支えられた物件」を見分ける一つの指標が「表面利回り」です。
表面利回りとは、「年間想定賃料 ÷ 物件価格」で計算される数値で、その物件の収益力を示すものです。
たとえば、港区の超高級タワーマンションの中には、4億円で売られているのに賃料は月50万円(年600万円)しか取れない、といった物件があります。この場合の表面利回りはわずか1.5%です。これは、物件価格の上昇に賃料がまったく追いついておらず、実態の価値(収益力)と価格が大きく乖離している状態と言えます。表面利回りが2%台前半、あるいはそれを下回るような物件は、バブル的な値付けがされている可能性を疑うべきです。
一方で、購入価格に対して相応の賃料が取れる物件は、実際に「そこに住みたい」という実需がしっかりと存在している証拠です。現在の市況で言えば、表面利回りが最低でも3%以上、できれば3.5%程度確保できるのであれば、その価格は実需に支えられた底堅いものだと判断できます。
要するに、賃貸需要が価格を支えているかどうかが、バブルか否かを見極める重要なポイントなのです。
2026年以降の東京で“本当に価値ある街”を見つける方法
現在の市況を踏まえた上で、僕が今、一次取得者の方に特におすすめしたいのが「浅草橋・蔵前」エリアです。なぜこのエリアなのか。それには明確な理由があります。
まず指摘したいのが、「都心回帰」の流れと、都内「東エリア」への注目です。かつて、東京のマンション市場には「西高東低」という言葉がありました。渋谷や新宿に近い西側エリアがブランド価値も価格も高く、東側はいわゆる「下町」として、一段低い評価をされてきた歴史があります。
しかし、この構図は今、大きく変わりつつあります。いや、なんなら逆転し始めているとさえ言えます。
東京の“不動産序列”が完全に崩壊した根本的な要因
その最大の理由は、オフィス街が東側に集中していることです。大手町・丸の内・東京・日本橋といった日本のビジネスの中枢は、昔から東京の東側にあります。昔は、夫が東側のオフィスに長時間かけて通勤し、妻は西側の「お洒落な街」での暮らしを優先する、といったライフスタイルも成り立ちました。
しかし、共働き世帯がマジョリティとなった現代では、そうはいきません。女性の社会進出が進み、妻も夫と同じように通勤の利便性を重視するようになりました。女性側の思考も「西側ブランド」から「東側へのアクセス」へとシフトしているのです。夫婦双方の職場が都心にある場合、「じゃあ、二人ともアクセスが良い東側のほうが合理的だよね」となるのは自然な流れです。この共働き世帯の増加が、東エリアの需要を根本から押し上げています。
都心高騰がもたらす“おこぼれ需要”で資産価値が上がる街
では、東京の東エリアの中でも、なぜ浅草橋・蔵前なのか。